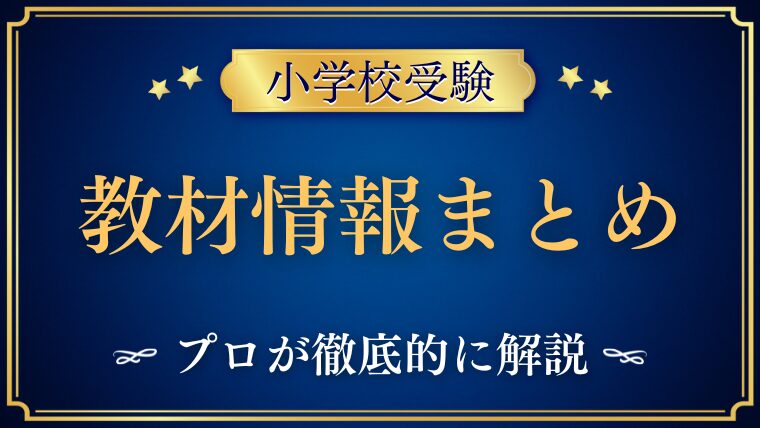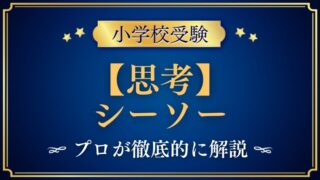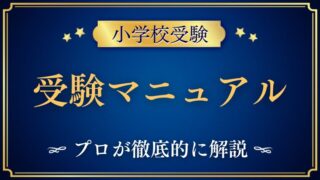【小学校受験】記憶
「記憶」の問題は、先生のお話を聞いて質問に答える聴覚系の記憶問題と、絵を見て形などを覚える視覚系の記憶問題の2種類があります。聴覚記憶と視覚記憶のどちらが得意かはお子さまの特性によって異なるため、苦手な方の記憶問題は基礎的な問題から徐々にステップアップしながら能力を高めていく必要があります。
聞き取り
小学校受験では、ペーパーテスト・行動観察・面接などにおいて、お話をきちんと聞けることが非常に重要です。また、日常生活や幼稚園・保育園での生活においても、お話をきちんと聞けることは大切です。しかし、「きちんと話を聞きなさい」と言っても、子どもは「何をどう聞けばいいのか」が分からず、聞く力は伸ばすことはできません。
本問題集では、ご家庭でお子さまの「聞く力」を効果的にトレーニングできるように、難易度や出題パターンに分けて問題集を構成しています。
方眼上の記憶
「方眼上の記憶」とは、ます目に記された形やイラストを覚える問題で、お子さまによって得意不得意が大きく分かれる問題です。問題自体は複雑でないにも関わらず、苦手なお子さまはほとんど問題が解けずに終わってしまうこともあります。それなのに、「こう教えたら絶対に解けるようになる」という指導法が確立されていない分野であるため、十分に対策をできていないお子さまも多いようです。
本問題集では、「方眼上の記憶」をどのように解くべきかの解説からしています。本問題集を解くことで、「方眼上の記憶」の基礎を一通り学習することができます。
絵の記憶
「絵の記憶」は、視覚的記憶に関する問題です。記憶力は、それまでの生活経験や学習経験に大きく左右される能力です。一方で、日々のトレーニングや生活習慣によって向上させることができる能力でもあります。ぜひ、本問題集をご活用いただき、視覚的記憶力を高めるトレーニングをして、地道に記憶力の向上を図っていただけたらと思います。また、本問題集にはご家庭でトレーニングするための付録を収録していますので、併せてご活用ください。
お話の記憶
「お話の記憶」は、小学校受験で定番の問題で、お話を聞いてその内容を覚えて、質問に答えるタイプの問題です。お話の内容は多岐に渡りますが、日常的な内容や動物が出てくる物語を扱っていることが多くなっています。
本問題集ではお話の記憶を効率的に学習することができるように、昔話を使ってオリジナルの問題を作成しました。この問題集を解くことで、お話の記憶の対策と昔話の対策を同時にすることができるようになっています。
【小学校受験】数量
「数量」は、数や量に関する問題です。小学校のように数字を書いたり、式を立てて計算したりすることはありませんが、日常の中で常識的に身につけているべき数や量に関する基礎的な問題を扱います。
計数
「数量」は、数を正しく数えられるかを問う問題です。数を正しく数えられることは、「お話の記憶」「常識」「推理」「位置」など、各分野の問題を解く時にも必要な能力になっているので、正確に速く数を数えることができるようになるまで丁寧に学習を進めて欲しいと思います。本問題集では、小学校受験に頻出の「数」の問題について、特に「計数(数を数えること)」を取り上げて、基礎からしっかりと理解できるように配慮して作成しています。
同数発見
「同数発見」は、いくつか提示されたもののうち、同じ数のものを見つけるタイプの問題です。「同数発見」は、「計数」が理解できないと正しく問題を解くことができませんので、「計数」がまだ身についていないお子さま「計数」の学習から始めてみてください。また、「同数発見」は「計数」のトレーニングにも向いていますので、「計数」を理解し始めたら「同数発見」にチャレンジしてみてください。
異数発見
「異数発見」は、いくつか提示されたもののうち、異なる数のものを見つけるタイプの問題です。「異数発見」は、「同数発見」と同じように解くことができる問題ですので、「同数発見」と一緒に対策をするのがおすすめです。
すごろく
「すごろく」とは、昔遊びのすごろくを題材にした問題です。デジタルなおもちゃが増えた昨今では、すごろくやサイコロに馴染みがないお子さまも増えていますので、「すごろく」がよくわからないお子さまでも基礎からしっかりと理解できるように配慮して本問題集を作成しました。
すごろくの問題は、「サイコロで出た目の数だけますを進む」という基本ルールにいろいろな条件を加えて、さまざまな出題パターンがある問題です。本問題集でも、さまざまな出題パターンを扱っていますので、「何を問われているのか」「どう答えればいいのか」を考えながら問題を解くようにしてください。
積み木の数え方
「積み木の数え方」は、積み木の数を数えることに特化した問題集です。積み木を数える場面は意外と多く、例えば、「てんとう虫と同じ数の積み木を選んで、丸で囲みましょう。」のような問題が出されます。また、見えない積み木を数える問題は、ある程度慣れが必要になります。積み木の数を正しく数えられることは、小学校受験を有利に進めるために重要ですので、本問題集で積み木を数える練習をしてください。
数量の系列
「数量の系列」は、理科的常識にも分類される問題で、数や量の大小を取り扱う問題です。「数量の系列」を含め、理科的常識は生活経験の豊かさが濃厚に反映される分野ですので、体験的に学習できるとよいです。
また、本問題集は出題パターンに分けて出題していますので、体系的に数量の系列について学べるようになっています。
和差
「和差」とは、数の和(合計)を求めたり、数の差(違い)を求めたりするタイプの問題です。小学校受験では、式を立てて計算するような問題は出されませんが、「合わせていくつ?」や「違いはいくつ?」というのは、幼児期に身につけておくべき数の感覚です。
本問題集では、基礎的な問題の解き方から丁寧に解説しています。
数の分割
「数の分割」とは、数を分けた時に一人分がいくつになるかを求めたり、数をまとめた時にいくつのまとまりができるかを求めたりするタイプの問題です。「数の分割」は、小学校3年生のわり算の基礎になる問題で、比較的難易度の高い問題です。しかし、問題の意味をきちんと理解して操作的に考えることで、正しく解くことができるようになります。
本問題集では、わり算における「等分除」「包含除」を網羅的に扱っています。
【小学校受験】言語
「言語」に関する問題は、言葉の音を扱った問題が中心に出題されます。小学校受験ではひらがなやカタカナを書かせる問題は出されませんので、文字が書ける必要はありません。ただ、語彙力がないと解けない問題もあるので、さまざまな言葉を知っておくことが重要になります。
音の数
「音の数」とは、言葉の中に含まれるモーラ数(拍数)を答えるタイプの問題です。言語に関する問題の中では初歩的な問題ですので、音の数の数え方に慣れていれば比較的簡単に答えられる問題です。
しかし、数の数え方を知らないとうまく解けません。特に、拗音・促音・長音・撥音の音の数え方に注意して、音の数を数えられるようにしましょう。こちらの問題集では、これらの音の数え方をマスターできるように配慮して作成しています。
はじめの音
「はじめの音」とは、言葉の1番目の音に関する問題の総称です。小学校受験では出題頻度が非常に高い問題で、基本問題から応用問題まで幅広い難易度の問題が出されます。
さまざまな出題パターンがあり、慣れていない問題が出ると解けなくなってしまうお子さまもいらっしゃいますので、さまざまな問題に慣れておくようにしましょう。
終わりの音
「終わりの音」とは、言葉の最後の音に関する問題の総称です。小学校受験では、「はじめの音」と同様に基礎的な言語力が試される問題で、出題頻度も高くなっています。
「同尾音・異尾音を答える問題」「特定の音を探す問題」「終わりの音を組み合わせる問題」などの出題パターンがあるので、「はじめの音」と同様に、さまざまな問題に慣れておくようにしましょう。
しりとり
小学校受験における「しりとり」とは、言葉の中の指定された文字を使って、言葉をつなげていくタイプの問題です。しりとりは子どもたちに馴染みがある遊びですので、楽しく問題を解くことができると思います。しかし、通常のしりとりとは異なるルールの「しりとり」が出されることもありますので、しりとりで遊ぶだけではなく、ペーパー上で十分に対策をしておくことが大切です。
あたまとり
「あたまとり」とは、「逆さしりとり」とも呼ばれ、前の言葉のはじめの音で終わる音の言葉で繋げるしりとりです。例えば、「りんご→ごりら→らっぱ」のように繋げるのが通常のしりとりで、「らっぱ→ごりら→りんご」のように繋がるのがあたまとりです。通常のしりとりとは異なるため難易度が高く、解き方に慣れていないとほとんど解けずに終わってしまうこともあります。また、「はじめの音」「終わりの音」の理解が前提になっている問題ですので、発展的な問題であると言えます。
同音異義語
「同音異義語」とは、同じ音でも違う意味を持つ言葉を答えるタイプの問題です。静止画(イラストや写真)から動きを判断しなければならず、小学校受験の問題の中でも難易度の高い問題です。
こちらの問題集では、動詞(動きを表す言葉)に関する同音異義語を扱っています。
【小学校受験】図形
「図形」では、平面図形や立体図形を扱った問題が出されます。例えば、折り紙・ブロック・パズル・点つなぎなど、身近な遊びを題材にした問題がよく出されるので、遊びを通して日常的に空間認識力や観察力、推理力、論理的思考力、運筆力などを鍛えることが大切です。
受験問題では、形を重ねたり、切ったり、折ったり、回したりするなど、多様な問題が出題されます。また、基礎的な問題から発展的な問題まで出題されますので、幅広い対策が求められます。
図形模写
「図形模写」とは、お手本の図形を正しく描き写すタイプの問題です。正しく描き写すだけでの問題ですので確実に正解したいところですが、正しく描き写すためには観察力、運筆力、空間認識力などの力が必要になります。制限時間内に正しく描き写すことができるように、しっかりと練習を重ねてこれらの力を鍛えるようにしましょう。
欠所補完
「欠所補完」とは、図形の欠けた所を描き足したり、絵の中の欠けた部分に合う絵を選ぶタイプの問題です。「欠所補完」という言葉は小学校受験特有の言葉なので馴染みがないかもしれませんが、間違い探しやジグソーパズルのイメージを持ってもらうとわかりやすいかもしれません。選択肢から正解を選ぶ問題は似た選択肢がたくさん出てくるので、ポイントを押さえて問題を解くことが大切になります。
回転図形
「回転図形」とは、ある形を回転させた時にどのように見えるかを考えるタイプの問題です。図形問題の中でも頻出のテーマのひとつですので、確実に得点できるようにしたいところです。
「回転図形」の解き方は、合成図形や回転点描写などの問題でも活用することができますので、解き方をしっかりと身につけることが大切になります。
回転点描写
「回転点描写」とは、点つなぎ(点描写)の応用問題で、お手本の点図形を回転させた形を描写するタイプの問題です。点つなぎと回転図形が合わさった問題で、回転図形を苦手とするお子さまは苦戦を強いられます。ただ、回転点描写ができるようになると回転図形の問題の正答率も上がっていきますので、繰り返し問題を解いてしっかりと対策しておくことが大切です
重ね図形
「重ね図形(重なり図形)」とは、図形を重ねた順番を答えたり、複数の図形を重ねた時にできる形を選んだり、描いたりするタイプの問題です。色紙を重ねた順番を答えるような問題は比較的簡単な問題ですので、確実に正解できるようにしましょう。
ただ、回し重ねたり、折り重ねたりすると難易度が高くなるため、回転図形や線対称図形と併せて対策しておくようにしてください。
合成図形
「合成図形」とは、複数の図形を組み合わせて指定された形を作ったり、指定された形を作るときに余るブロックを選んだりするタイプの問題です。また、「同図形発見」と似たような問題が出されることもあります。
分割図形
「分割図形」とは、ある形を分けた時に、どのような形に分かれるかを考えたり、余分な形を選んだりするタイプの問題です。
「分割図形」と似た問題に「合成図形」があり、これらの問題は同じ解き方で解くことができますので、「分割図形」と「合成図形」は一緒に対策しておくのがおすすめです。
線対称図形
「線対称図形」とは、「展開図形」「折り紙展開」「鏡図形」「水面図形」などと呼ばれることもある問題で、小学校受験で頻出の図形問題です。「線対称図形」が正しく解けるようになると、他の図形問題にも応用することができるので、基礎からしっかりと解き方をマスターしましょう。
折り紙展開
「折り紙展開」とは、展開図形に関する問題の一種で、折り紙を半分や1/4に折ったとき、その一部を切って開くとどのような形ができるかを問うタイプの問題です。折り紙を切って展開した形をイメージするのは高度な思考力が必要なため、小学校受験の中でも難易度が高くなっています。ただ、正しい解き方を理解することで、論理的に問題を解くことができるので、解き方をしっかりと身につけておくことが大切です。
展開図形
「展開図形」とは、サイコロの形(立方体)を展開したり、折り紙(平面図形)を折って切った後に展開するタイプの問題です。頭の中で展開するところをイメージするには高い思考力が必要で、幼児期のお子さまには難易度の高い問題になっています。しかし、解き方のコツを知れば、簡単に解けるようになる問題がたくさんありますので、しっかりと対策をしておくことが望まれます。
鏡図形発見
「鏡図形発見」とは、鏡に映った時の形を推理するタイプの問題です。「同図形発見」や「異図形発見」と複合的に出題されることもあり、日常的に鏡を見慣れているお子さまでも間違えてしまうことがあります。また、出題のされ方によって難易度も上がるので、基礎的な問題ながらもきちんと学習をしておくことが必要です。
鏡図形描写
「鏡図形描写」とは、鏡に映った形を描くタイプの問題です。鏡に映った形を正しく描けるようになるためには、鏡図形についてしっかりと理解していることが必要です。そのため、反転した形をイメージするのが難しいようであれば、「鏡図形発見」の教材から学習するのがおすすめです。
推理〜図形〜
「推理〜図形〜」とは、図形分野において推理力を必要とする問題の総称です。「推理」と言っても、基礎的な図形問題の解き方を理解していれば解ける問題がほとんどですので、論理的に問題を解決していくことが大切です。
また、解き方をパターン化して覚えてしまえば簡単に解ける問題もありますので、しっかりと解き方を身につけておきましょう。
図形の置き換え
「図形の置き換え」とは、ある図形を別の図形と対応させて描き換えるタイプの問題です。「図形模写」に似た問題ですが、図形を置き換えるという性質上、より高い思考力や作業力が必要になります。
「図形の置き換え」は、継続的にトレーニングすることで、作業スピードや頭の回転の速さの向上が期待できます。
【小学校受験】思考
「思考」は、規則性、条件理解、比較、想像力など、多面的な思考力が求められる問題の総称です。試行錯誤が必要な問題もあり、幼児期には難易度の高い問題も多くなっています。ただ、日常生活に即した問題もありますし、解き方を理解していれば作業的に解ける問題もありますので、さまざまな問題を解く経験をしておくことが大切です。
置き換え
「置き換え」は、思考分野の問題の中では基礎的な問題です。一方で、小学校受験のペーパーテストで頻出の「シーソー」や「釣り合い」などの問題の基礎となる問題ですので、他の問題を解くためにも「置き換え」の考え方をしっかり理解しておくことが大切です。
釣り合い(重さ比べ)
「釣り合い(重さ比べ)」は、シーソーや天秤に物を乗せたときの左右の重さのバランスを考えるタイプの問題です。「シーソー(重さ比べ)」と似た問題ですが、「シーソー」はどちらに傾くかに主眼を置いた問題であるのに対して、「釣り合い」は重さのバランスが取れるかどうかに主眼を置いた問題になっています。
シーソー(重さ比べ)
「シーソー(重さ比べ)」とは、遊具のシーソーを題材にして、重さの順序を考えるタイプの問題です。子どもたちに身近なシーソーという遊具を題材にしているため、問題のイメージをしやすいと思います。ただ、シーソーを4台や5台使って、5つや6つの物を比較するような問題も出されますので、効率のよい解き方を知っておくことも必要です。
濃度
「濃度」は、理科的常識に分類される問題のひとつで、水に物を溶かした時の濃さを考えるタイプの問題です。「同じ量の水に違う量の塩を溶かす」という問題なら簡単に解けますが、「違う量の水に違う量の塩を溶かす」というような問題では高い思考力が要求されますので、解き方を身につけておくことが大切です。
右左
「右左(みぎひだり)」とは、方向の理解や基礎的な空間認識力を図るための問題です。左右を適切に判断できると、「地図上の移動」や「方眼上の移動」などの問題も解きやすくなります。また、行動観察において「右にあるカゴにボールを入れましょう」などの指示も理解しやすくなります。左右を即座に判断できるようになるまで、繰り返し問題演習をするようにしましょう。
四方図
「四方図」とは、ある立体を別の方向から見た時に見える形を答えるタイプの問題です。積み木やコップを別の角度から見た時にどのように見えるかを答える問題が代表的で、「四方観察」と呼ばれることがあります。見えない部分を類推する論理的な思考力が必要な問題もあるため、高い思考力が必要です。
方眼上の位置移動
「方眼上の位置移動」とは、方眼(ます目)の上での動き(位置の変化)を把握して、最終的に移動した場所(位置)を答えるタイプの問題です。上下左右を正しく判断しながら平面上の座標を移動するのは、関数的(座標的)な見方に慣れていないお子さまにとっては難しい問題になります。
地図上の移動
「地図上の移動」は、示された地図をもとに、移動した経路や到着地点を答えるタイプの問題です。日頃から地図を見慣れているお子さまは少ない上に、進行方向によって左右が変わるため、高い空間認識力が求められます。地図の見方に慣れるためには繰り返し問題を解くことが必要です。
条件迷路
「条件迷路」とは、与えられた条件に従って進む迷路問題です。小学校受験では「迷路」の問題がよく出されますが、「条件迷路」はさまざまな条件が追加されるため、比較的難易度が高い問題になっています。学齢の低い時期は「迷路をたどりながら論理的に考える」というのが難しいこともあるため、ある程度出題パターンに慣れておくことも大切です。
系列
「系列」とは、形や色などの並びから規則性を発見し、その規則性を適用しながら解くタイプの問題です。闇雲に問題を解いてしまうと、並び方のきまりを見つけるのに時間がかかってしまうことがありますので、解き方を身につけておくことが重要です。
「系列」の問題の解き方はいくつかありますので、本問題集を活用して解き方をきちんと身につけておくようにしましょう。
魔法の箱
「魔法の箱」とは、箱に入ったものと箱から出たものの変化の関係を推理して、他のものに適用しながら解くタイプの問題です。規則性を発見する力が求められるため「閃き」が大切だと思われがちですが、ほとんどの問題は「経験」で解くことができます。そのため、本問題集を活用して、さまざまなパターンの問題に慣れておくことが大切です。
紐の切断
「紐の切断」とは、紐を切った時に、紐が何本に分かれるかを答えるタイプの問題です。どのお子さまもはさみで何かを切った経験はあると思いますので、紐を切る場面を具体的にイメージしながら問題を解くようにしましょう。ただ、いざペーパーテストで解くとなると間違ってしまうお子さまも多くいらっしゃいますので、問題集を活用して対策しておくことも必要でしょう。
想像絵画
「想像絵画」とは、与えられたテーマをもとに絵を描く課題で、「条件画」や「想像画」と呼ばれることもあります。与えられるテーマにはさまざまな種類がありますし、制限時間も短いため、絵画制作が苦手なお子さまは苦戦を強いられることになります。
他の問題と違い明確な解答がないことから対策がお座なりになってしまうことがあります。また、巧緻性の発達や想像力の育成には時間がかかりますので、他の受験生に遅れを取らないようにコツコツと対策をしておきましょう。
【小学校受験】知識
「知識」に分類される問題は、知っていれば解けるけれど、知らないと解けないという問題が多くなっています。知識の積み重ねはできるだけ早期に始めた方が受験を有利に進めることができます。ただ、意味もなく知識を詰め込むだけでは、勉強に対して嫌悪感を抱いてしまうお子さまもいるかもしれません。そのため、体験や遊びを通して知識を定着させることが重要になります。
季節
「季節」とは、行事・植物・食べ物など、四季に関わるタイプの問題で、多くの小学校で出題されます。生活経験の豊かさが重要な問題ですが、経験しただけでは知識としてなかなか定着しません。また、最近では見かけなくなったものやお子さまに馴染みのないものが出題されることもあるので、しっかり対策しておくことが重要です。
水の浮沈
「水に浮くもの沈むもの」とは、あるものを水に入れた時に浮くか沈むかを判断するタイプの問題です。「理科的常識」に分類される問題で、いろいろなものを水に入れてみる経験があるかないかで正答率が大きく変わってきます。ただ、水に入れた経験がないものが出題されたとしても問題を解くことができるように、本問題集で解説している解き方を身につけておきましょう。
覚える系問題
「覚える系問題」とは、「覚えるカード」を使って出題・解答するタイプの問題です。「覚えるカード」とは、「花木」「野菜」「果物」「爬虫類」「哺乳類」「鳥類」「魚類」「食品」「文房具」「用具」「肢体」などを幅広く扱い、理科的常識・社会的常識を覚えることができるカードです。「覚える系問題」を解くことにより、お子さまの知識量を圧倒的に増やすことができるようになっています。
理科的常識(植物)
「理科的常識」とは、生物・科学・気象・物理などにおける知識を問うタイプの問題です。その中でも、幼児に馴染みのある植物(草花、花木、野菜)に関する出題頻度が多くなっています。ただ、私立小学校が多い都市部では日常的に植物を見かけることは少ないですし、小学校受験では生活に馴染みのない問題が出てくることがよくあるので、しっかりと本問題集で対策しておく必要があります。
【小学校受験】教材情報完全ガイド|まとめ
今回ご紹介したように、小学校受験ではさまざまな分野の問題が出題されます。これらを網羅的に学習するためには、適切な教材選びが大切です。今回ご紹介した教材は、ご家庭で効率よく学習できるように解説がついているのが魅力の教材になっています。ぜひこれらの教材を活用して、志望校への合格を叶えていただけたらと思います。
1.jpg)