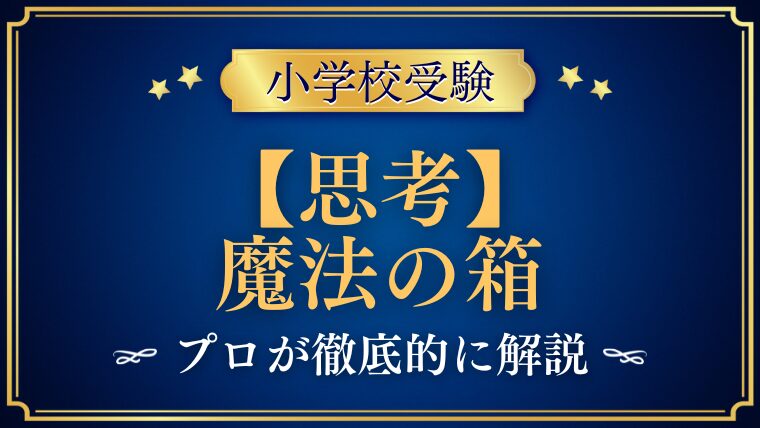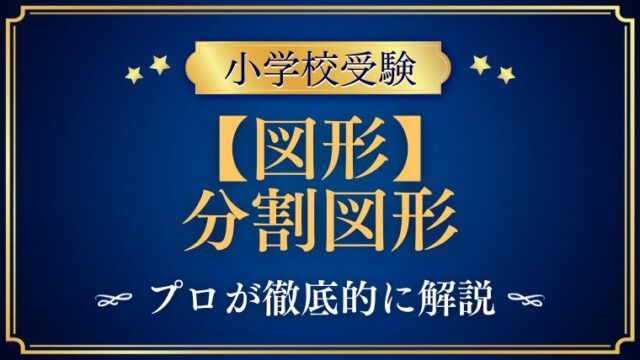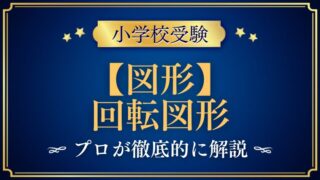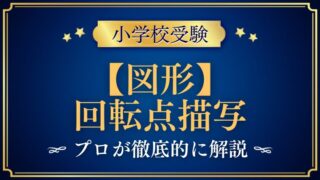【小学校受験】魔法の箱の出題意図は?
「魔法の箱」は、入ったものと出たものの変化の関係を推理するため、数量感覚や言語感覚、論理的思考力などが問われます。
観察力があるか
「魔法の箱」では、入ったものと出たものを観察して、その違いを見極めることが大切です。例えば、入ったものと出たものではクッキーの数が変わっていたり、三角の向きが変わっていたりするはずです。入ったものと出てきたものの違いを見つける観察力があるかどうかが重要です。
数量・図形・言語などの感覚があるか
入ったものと出てきたものの違いを見つけて変化の関係を推理するためには、数量感覚・図形感覚・言語感覚などの基本的な感覚を持っていることが必要です。例えば、「イカ→貝」と変化しているのならば、「言葉が逆さまになった」と直感的に判断できるのが望ましいです。感覚が豊かなお子さまであればこのような変化の関係を直感的に捉えることができますが、そうでなければ経験を積んで知識を増やすことが大切です。
論理的思考力があるか
規則性を見つけて、それを他の問題に応用する論理的思考力も必要です。「お手本では言葉が逆さになっているから、この言葉も逆さまにしてみよう」など論理的に考えられるようになると、正答率を上げることができます。
発想力があるか
どのような規則性があるかを発想する力も大切です。例えば、数の変化において「2→4」と変化した時に「2増えた」と考える場合と、「2倍になった」と考える場合があります。1つの考えに固執していては問題が解けないことがあるので、柔軟に発想して問題を解くようにしましょう。
【小学校受験】魔法の箱の出題方法は?
「魔法の箱」の出題方法には、大きく2つの方法があります。
個別テスト・口頭試問
個別テスト・口頭試問による出題では、先生が例を説明してくれた後に、口頭で問題に答えます。例えば、「この箱に積み木を2個入れると3個になって出てきます。3個入れると4個になって出てきます。では、5個入れたらいくつの積み木が出てきますか。出てくる積み木の数を教えてください。」のように、口頭で問題が出されます。実物を使ったり、変化の関係が描かれた用紙を見せられたりすることもあります。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、変化の関係が「お手本」として示されていて、それをヒントに解答するパターンがほとんどです。解答の仕方は、選択肢が示されている問題や、答えの数だけ丸を描く問題などがあります。
【小学校受験】魔法の箱の出題内容は?
「魔法の箱」の主な出題内容には、数量・図形・常識・言語があります。
数量
数や量が増減するタイプの問題です。数や量が増減するタイプの問題です。「1→2」や「1→3」、「2→1」や「3→1」のように、数量が増えたり減ったりします。また、「2→4」や「3→6」、「4→2」や「6→3」のように、数が倍になったり、半分になったりする問題が出されることもあります。「数量」の分野に関連した問題は、「魔法の箱」で頻出の問題になっています。
図形
形が、反転したり、回転したり、切られたり、増えたり、色が変わったりするタイプの問題です。「数量」と同様に、「図形」に関連する問題も、「魔法の箱」で頻出の問題です。このタイプの問題を解くためには、図形の基礎を理解していることが必要です。小学校受験では、「図形が苦手」というお子さまも多いので、図形の理解が不十分な場合は、「魔法の箱」に取り組む前に「反転図形」「回転図形」「重ね図形」などの問題集で、図形の基礎をきちんと理解しておきましょう。
常識
季節の変化や生き物の関係など、「常識」の分野タイプの問題です。「数量」や「図形」に比べて出題の頻度は低いものの、このタイプの問題に慣れていないと、「問題の意味がわからない」という事態になりかねません。問題の種類や解き方を確認して、しっかりと解答できるようにしておきましょう。
言語
言葉を逆さまにしたり、言葉を入れ替えたりするタイプの問題です。「常識」の問題よりもさらに出題頻度が低い問題ですが、どのような種類の問題が出されるのかを知っておくだけでも有用です。
【小学校受験】魔法の箱の解き方は?
「魔法の箱」の問題を解く時には、「数」「形」「色」「物」「時間」「言葉」に着目するのがポイントです。この中でも「数」と「形」は出題頻度が高いので、まずはこの2つの変化に着目するとよいです。
また、各問題には、それぞれ解き方のポイントがあります。例えば、図形の変化に関する問題では、主に「向き」「表裏」「色」「形」が変化します。よく出題される問題に慣れておくことは、正答率を高めたり、解答速度を速めたりするのに効果的です。
こちらの教材では、数量・図形・常識・言語の出題内容を網羅し、解く時のポイントを丁寧に解説しています。
【思考】魔法の箱(教材サンプル)
【思考】11 魔法の箱サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
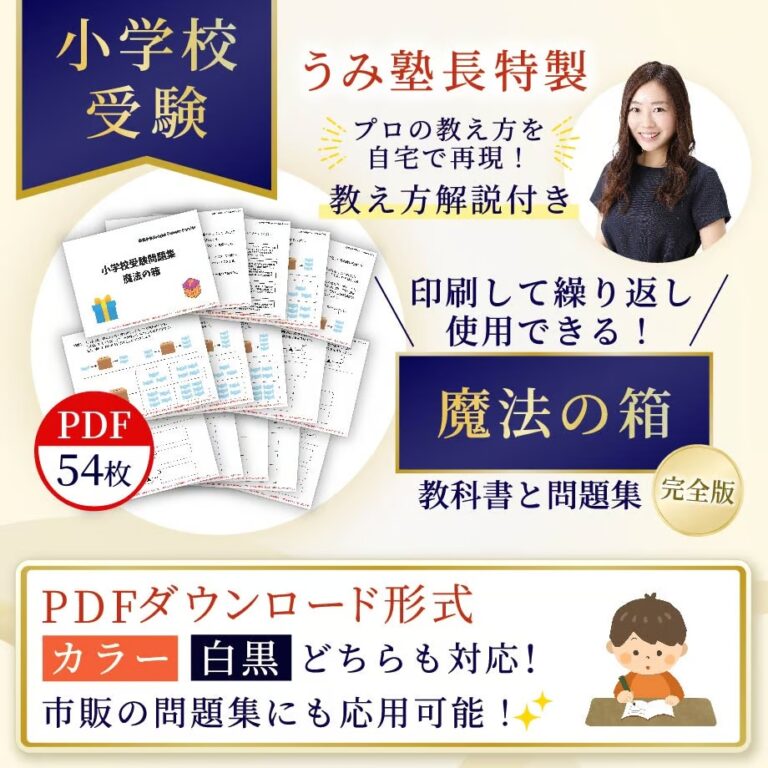
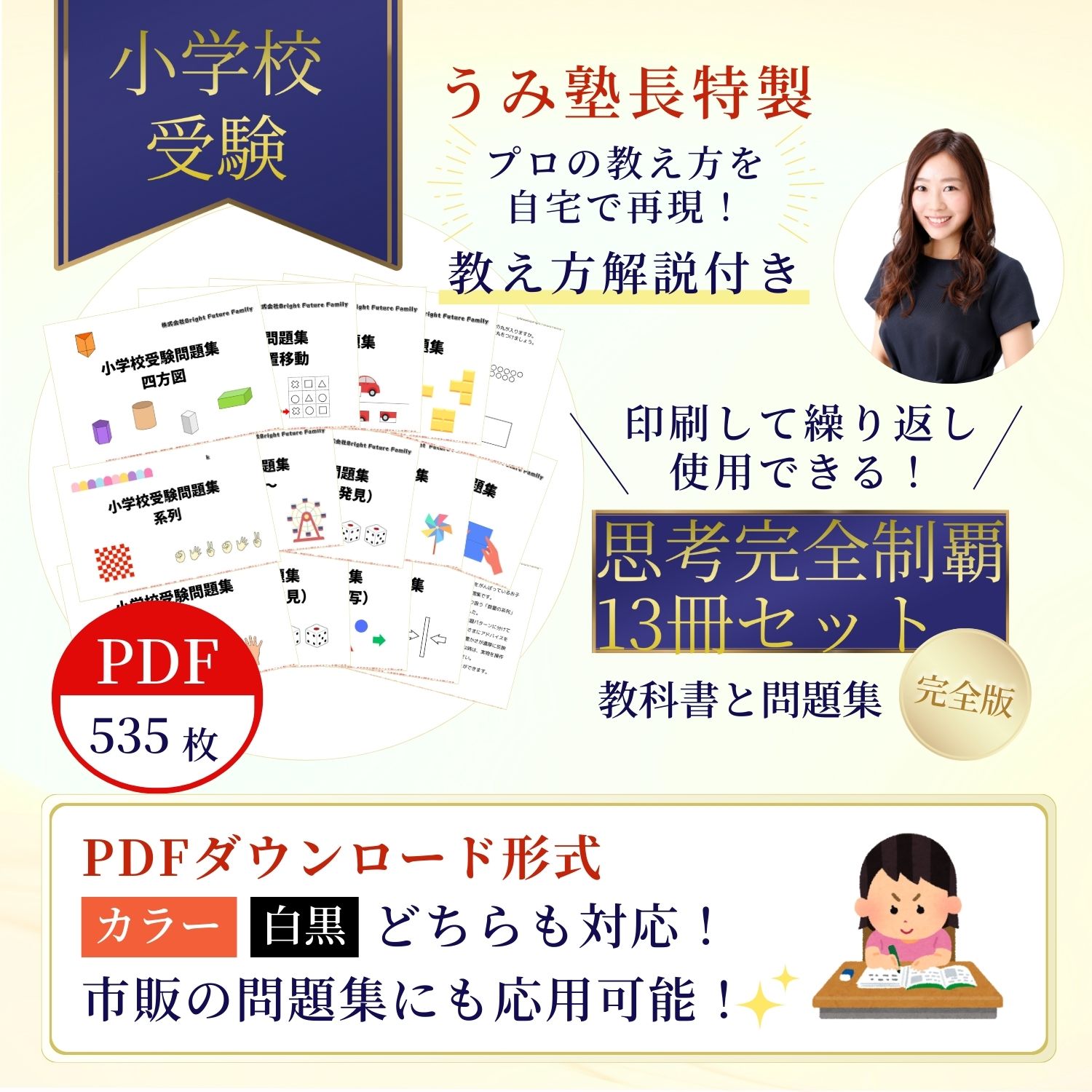
【小学校受験】魔法の箱|まとめ
「魔法の箱」は発想力が必要な問題ですが、発想力は経験を通して育むことができます。いろいろな問題に慣れておくことで、発展的な問題も解けるようになりますので、幅広い対策を心がけるようにしてください。本記事でご紹介した教材をご活用いただき、ぜひ効果的な対策をしていただけたらと思います。
1.jpg)