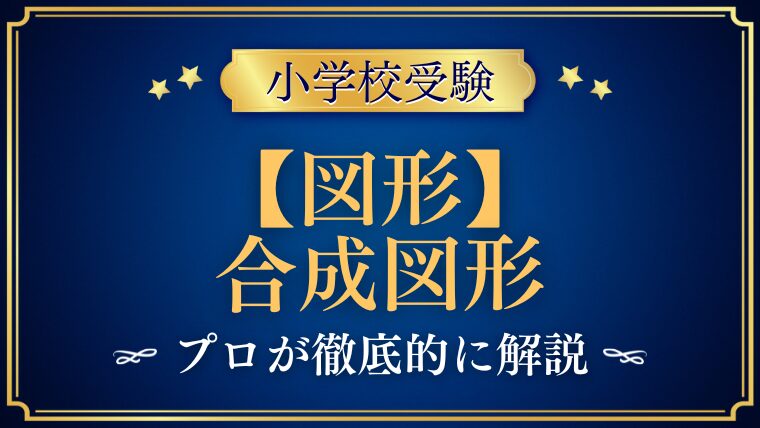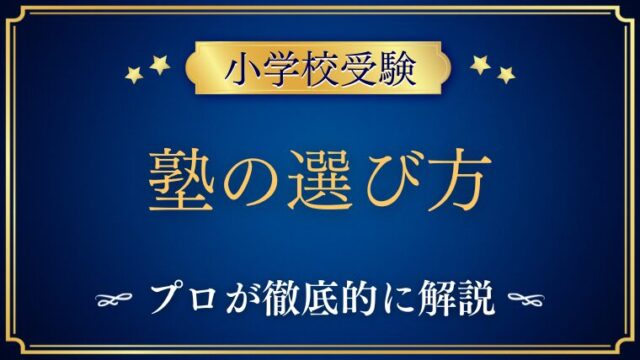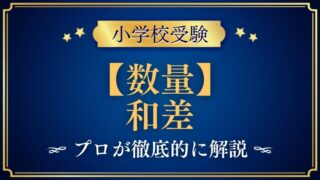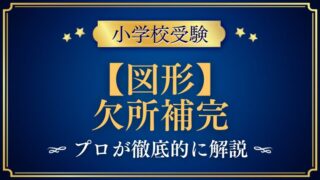【小学校受験】合成図形の出題意図は?
「合成図形」の問題は、「分割図形」と同様に、図形のイメージ力、構成力・分析力、論理的思考力などがあるかを見ています。
図形のイメージ力があるか
「合成図形」の問題を解くためには、与えられた形を頭の中で組み合わせて、全体をイメージする力が必要です。頭の中で形を回転させたり、裏返したりしてできる形を考えるためには、高い思考力が要求されます。
構成力・分析力があるか
「合成図形」では、与えられた形を正しく認識して、どの部分とどの部分がぴったり合うのかを考えなければいけません。そのためには、形の要素に着目してパーツを組み立てたり、もとの形からどのようなパーツに分かれるのかを分析したりする力が必要です。特に、「同図形発見」のような問題では、一つひとつの図形の構成要素に着目することが大切です。
論理的思考力があるか
「合成図形」では、「この形は絶対に当てはまらない」「この形を使うとこの形は使えない」などと消去法で問題を解くことがあります。消去法で解く際にも、順に形を当てはめながら考える際にも、「どの形から考えるべきか」という戦略を立てる論理的な思考をすることで、効率よく問題を解くことができます。
忍耐力があるか
「合成図形」では、試行錯誤が必要な場面が多々あります。特に、形を回転したり、裏返したりする問題だと、形の組み合わせのパターンがたくさんできてしまい、何度も試行錯誤しなければいけないこともしばしばです。なかなか答えを見つけられない時でも、忍耐強く問題を解く姿勢が大切です。
【小学校受験】合成図形の出題方法は?
「合成図形」の出題方法には、個別テストとペーパーテストの2つの方法があります。
個別テスト
個別テストによる出題では、実際にパズルやブロック、カードなどを操作して図形を合成させる問題が出されることがあります。また、ごく稀にですが、積み木などを使って立体的な形を組み立てる課題が出されることもあるようです。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、お手本の形が描かれていて、どのブロックを組み合わせたらお手本の形ができるかを選んだり、お手本の形を作る時に使わない形を選んだりする問題がよく出されます。ブロックを回転して使ったり、裏返して使ったりする問題が出されることもあります。
【小学校受験】合成図形の出題内容は?
「合成図形」の出題内容には、大きく3つのパターンがあります。
同図形発見
複数の図形が重なり合っていて、どの図形があるか、またはないかを答える問題です。基本的には、同図形発見のように図形を見つけていけば解ける問題です。ただ、図形が重なっている分、見落としや見間違いが起こるので注意してください。また、一部が影で隠れているなど、思考力を試す問題も出されます。一方で、同図形発見よりも形はシンプルなことが多いのがメリットです。
ブロックの合成
複数のブロックを組み合わせて、指定された形を作る問題です。どのブロックを使うか問われる場合と、使わないブロックを答える場合があります。いわゆる「テトリス」のように、正方形を複数組み合わせたブロックを使うことが多くなっています。ブロックやパズルでよく遊んでいるお子さまは、このタイプの問題が得意なことが多いです。
組み合わせ図形
「タングラム」や「シルエットパズル」のように、図形を組み合わせて指定された形を作る問題です。図形の構成要素に着目して、どの形とどの形を組み合わせるのかを適切に判断することが求められます。
【小学校受験】合成図形の解き方は?
「合成図形」の問題が解けるようになるためには、頭の中で図形を回転させたり、反転させたり、移動させたりする思考力を鍛えることが重要です。これらの能力は、タングラムやジグソーパズル、テトロミノやペントミノパズルなどの遊びを通して楽しく鍛えることができます。また、問題を解く時も、手元に問題の形を用意して、実際にパズルやブロックを操作しながら問題を解くのがおすすめです。実際に操作することで、より理解を深めることができます。
「合成図形」を解く時に大切なポイントは3つあります。1つ目は、大きい形から考えることです。小さい形から考えると当てはまるパターンが多くなって、試行錯誤の回数が増えてしまいます。大きい形から順に考えた方が、効率よく問題を解くことができます。
その他のポイントについては、こちらの教材で解説しています。また、こちらの教材では実際に操作しながら問題を解けるように印刷用のブロックを用意しているので、ぜひ活用ください。さらに、各問題の解き方を具体的に解説していますので、図形問題が苦手なお子さまでも段階的に理解できるようになっています。
【図形】合成図形(教材サンプル)
【図形】6 合成図形サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
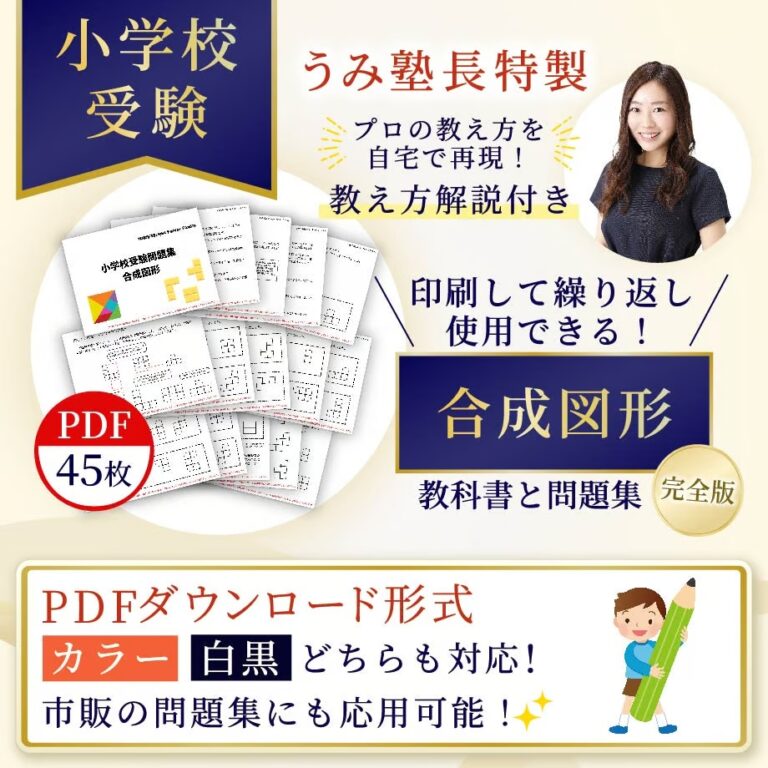
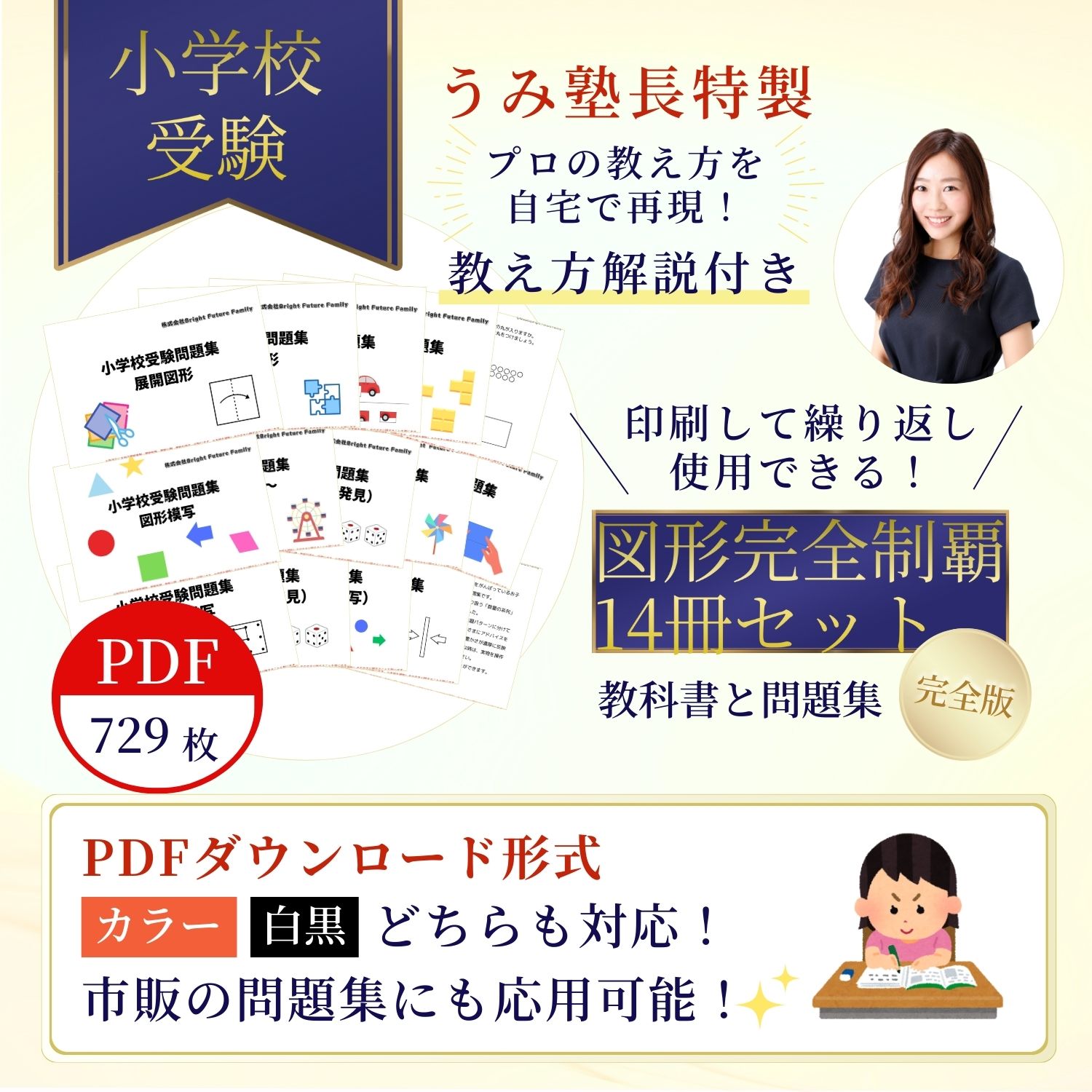
【小学校受験】合成図形|まとめ
「合成図形」は、図形をイメージしたり、図形の構成要素に着目したり、論理的に考えたりすることが大切な問題です。これらの力は一朝一夕に鍛えられるものではないので、パズルやブロックなどの遊びを通して、楽しく力を伸ばしていきましょう。また、問題を解く時には本記事でご紹介した教材をご活用いただき、実際に図形を操作しながら丁寧に学びを深めていただけたらと思います。
1.jpg)