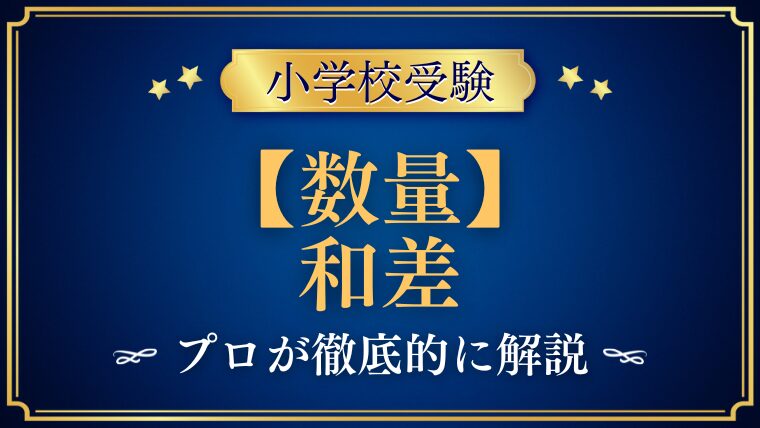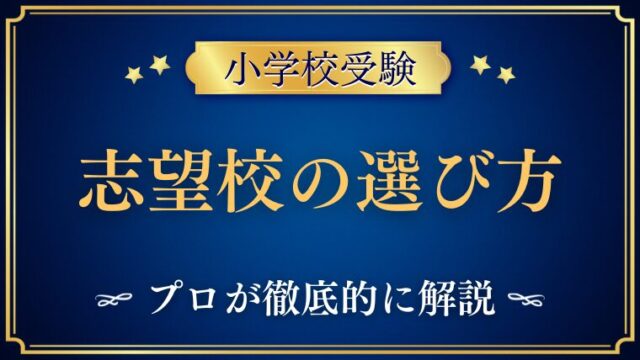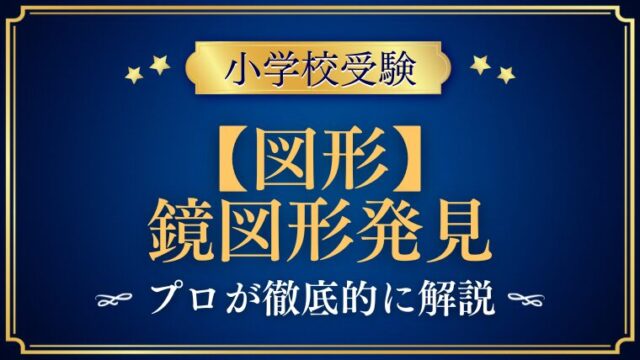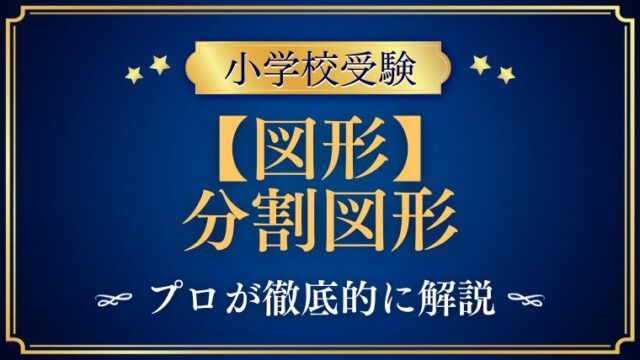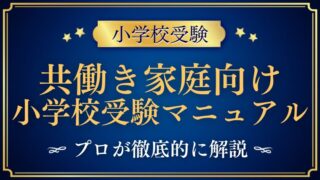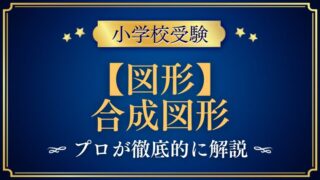【小学校受験】和差の出題意図は?
「和差」の問題を通して、数に関する基礎的な感覚があるかどうかを判断しています。
数を数えられるか
「和差」の問題を解く上では、数を正しく数えられないといけません。そのためには、数唱(数を1から順に数えること)ができること、集合数について理解していることが必要です。なお、10程度までの数について数唱ができるようになるのは3〜4歳ごろと言われています。
数を比べられるか
「和差」の問題の中には、数を比べる問題もあります。数唱と数量を対応させて理解し、数の大小が判断できるようになるのは4歳ごろからと言われています。もしこのことが理解できていないと、「スイカ(3個)といちご(4個)はどちらが多いですか。」という問題で、「スイカの方が大きいからスイカの方が多い」などと考えてしまうことがあります。
簡単な計算ができるか
「和差」の問題では、小学校のたし算やひき算の基礎になる問題も出されます。ただ、たし算やひき算について理解している必要はなく、数が数えられば解けるような問題になっています。一方で、「合わせるとはどういう意味か」「数が違うとはどういう意味か」について基礎的な理解をしていることが重要です。
【小学校受験】和差の出題方法は?
「和差」の出題方法には、大きく2つの方法があります。
個別テスト・口頭試問
個別テスト・口頭試問による出題では、実物や絵が書かれた紙を見せられて、「赤いおはじきと青いおはじきを合わせると、おはじきは全部でいくつになりますか。」や「赤いおはじきと青いおはじきでは、どちらが多いですか。」などと聞かれるのが定番です。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、絵を見て数を判断し、多い方に丸をつけたり、合わせて5になるものを線で結んだりする問題が出されます。個別テスト・口頭試問よりも難しい問題が出されることが
【小学校受験】和差の出題内容は?
「和差」の出題内容は、大きく分けて次の4つがあります。また、「赤いお花と青いお花を合わせた数と同じ数のブロックに丸をつけましょう。」のように、「積み木の数え方」と関連する問題が出されることもあります。
合わせた数を求める
例えば、メロンとスイカの絵が描かれていて「果物は全部でいくつですか。」と問われるような問題が出されます。あるいは、「上にあるいちごと合わせると全部で5個になるいちごのお部屋を見つけて、線で結びましょう。」のように数を合わせることもあります。
ペーパーテストでは、合わせた数と同じ数の丸を描いたり、同じ数の積み木を選んだりするのが定番ですので、数字が書けるようになる必要はありません。
数の大小を判断する
「どちらの動物が多いですか。」や「どの色鉛筆が1番少ないですか」など、「計数」と同じ内容の問題が出されることもあります。絵がきれいに並んでいないことがあるので、数え間違えないように気をつけましょう。
数の違いを答えるもの
数の大小に加えて、数の違いを求める問題もあります。例えば、「男の子と女の子では、どちらが何人多いですか。多い方の子を丸で囲んで、横の四角には多い人数と同じ数の丸を描きましょう。」のように出題されます。数の「差」について理解していることが大切です。
足りない数を求める
例えば、「6枚入りのお菓子の袋を作るためには、袋の中にあと何枚のクッキーを入れればいいですか。」のように、足りない数を求める問題です。小学校では、ひき算で答えを求めるような問題になっています。
【小学校受験】和差の解き方は?
「和差」の問題を解けるようになるためには、計数が正しくできることが大前提です。もしまだ計数が正しくできないようであれば、計数の学習からスタートしましょう。
また、「和差」の問題を正しく理解するためには、具体物を操作しながら考えることが大切です。幼児期の学習では、机上の説明だけで十分に学習内容を理解できないことがあるため、具体物を操作しながら「和」や「差」について学習してください。
具体的な解き方としては、「数え足し」や「数え引き」、「一対一対応」を使うことになります。これらの解き方を使うことで、たし算やひき算のように式を立てて計算する必要がなくなります。「数え足し」とは、数を数えながら数を足していく方法です。例えば、「りんご3個となし2個が合わせていくつあるか」という問題の解き方を考えてみましょう。まずは、りんごを「1,2,3」と数えたら、なしを「4,5」と数えます。こうすることで、「3+2=5」のように計算しなくても問題を解くことができます。
このような解き方を解説していると、「たし算やひき算を教えた方が早いのではないですか?」という質問を受けることがあります。しかし、たし算やひき算ができたとしても、計算の意味についてわかっていないと、本質的に問題を理解するのが難しいお子さまもいらっしゃいます。そのため、計算の先取り学習をするよりは、数の意味についての理解を促すような指導法が望ましいと言えます。
「数え引き」や「一対一対応」の解き方については、こちらの教材で詳しく解説しています。計算に頼らず確実に問題が解ける方法が気になる方は、ぜひこちらの教材をチェックしてください。
【数量】和差(教材サンプル)
【数量】7 和差サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
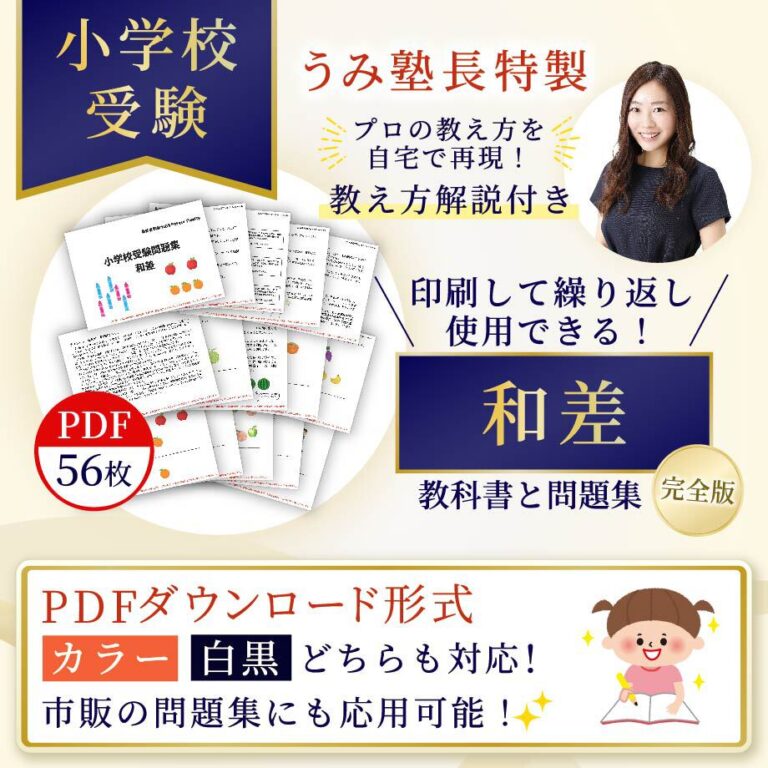
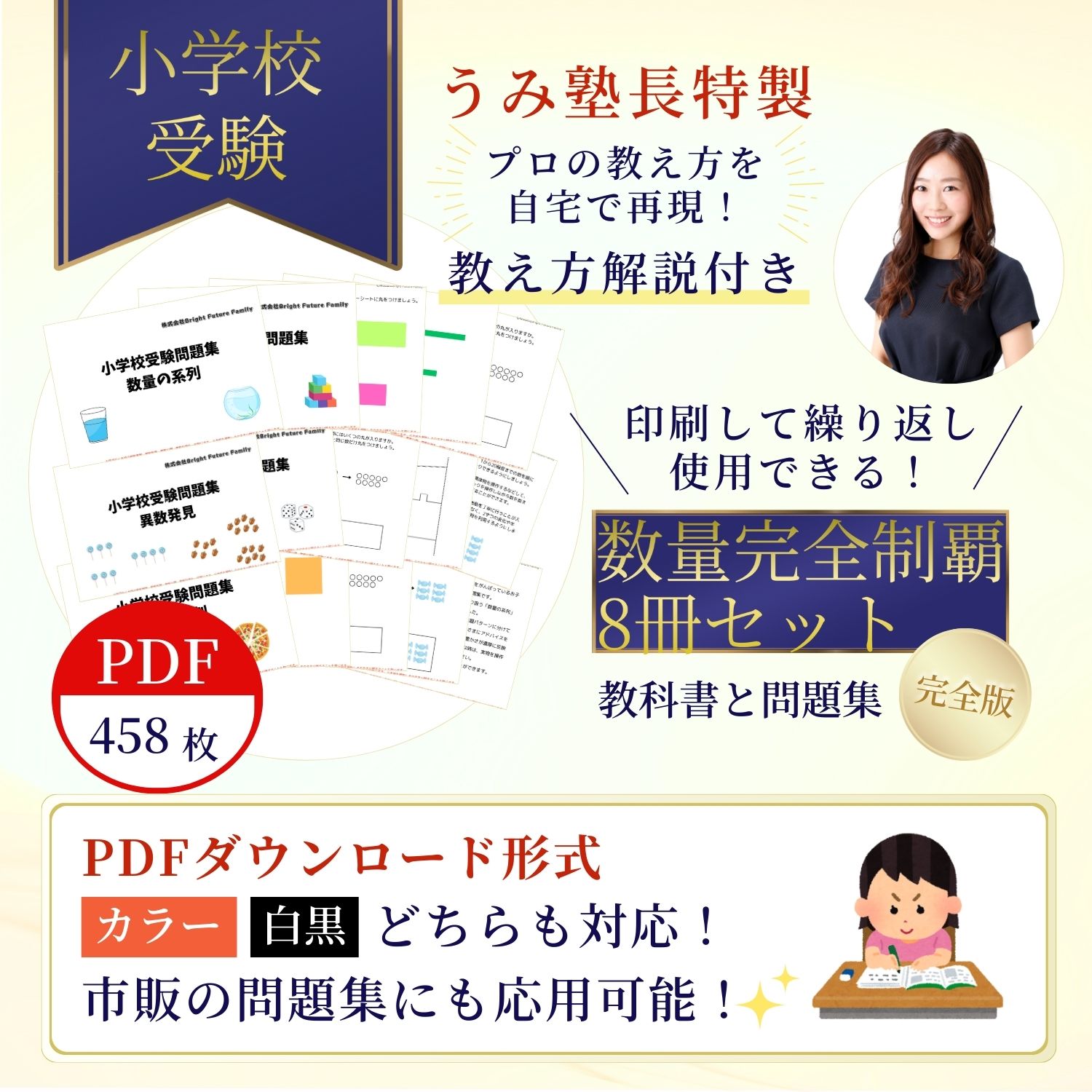
【小学校受験】和差|まとめ
「和差」は、小学校のたし算やひき算の基礎になる問題ですが、計算に頼らなくても問題が解けるようになっています。ぜひ本記事でご紹介した教材をご活用いただき、問題の意味について本質的に理解できるように学習していただけたらと思います。
1.jpg)