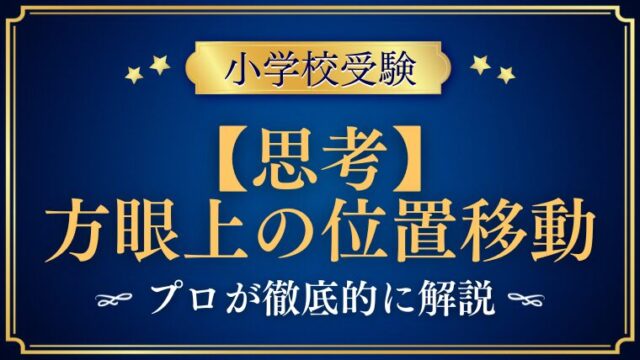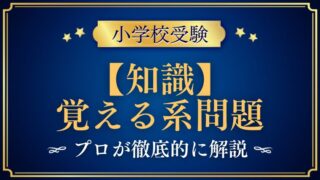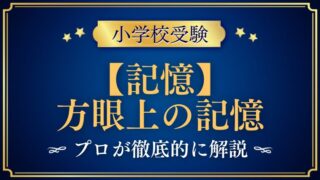【小学校受験】理科的常識(植物)の出題意図は?
「理科的常識(植物)」を出題する意図として、「自然や社会への興味・関心があるか」「ご家庭の教育力があるか」「生活力があるか」という要素が挙げられます。
自然や社会への興味・関心があるか
幼稚園や保育園に咲いている花木、公園に咲いている花木、通園路の途中にある花木、お花屋さんに売られている花木など、身の回りには植物がたくさんあります。身の回りの自然や社会に対して興味・関心が持てるような知的好奇心の高いお子さまは、学力も高い傾向にあります。
ご家庭の教育力があるか
必ずしもご家庭で植物を育てる必要はありません。しかし、教育力のあるご家庭では、公園に咲いた花を見て「パンジーが咲いているよ。」「コスモスが見頃だから一緒に見に行こう。」などと、積極的にお子さまの教育にとってよい選択をされています。幼児期に自然と触れ合うことは心身の発達にとってよいことですので、進んで自然と関わる教育環境をつくっていただきたいです。
主体的に学びに向かう態度があるか
例えば、幼稚園や保育園で植物を育てていたとしても、何の植物を育てているかをよく理解していないお子さまもいらっしゃいます。しかし、主体的に物事に関わろうとする態度があるお子さまなら、「何のお花を育てるの?」「どんな種なの?」「いつ咲くの?」「水はどれくらいあげたらいいの?」など、主体的に考えて行動することができます。身近な植物をテーマに出題することで、身近な物事に主体的に関わるお子さまかどうかを判断しています。
【小学校受験】理科的常識(植物)の出題方法は?
「理科的常識(植物)」の出題方法には、大きく2つの方法があります。
個別テスト・口頭試問
個別テスト・口頭試問による出題では、フラッシュカードの要領で問題を出されたり、問題に合ったカードを選んだりするのが定番です。比較的難易度の低い問題が多いため、じっくり考えるのではなくテンポよく答えられるのが望ましいです。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、植物の花と種の組み合わせを見つけて線で結んだり、果実と果実の断面図の組み合わせを見つけて線で結んだり、土の中にできる野菜に丸をつけたりするなど、比較的難易度の高い問題が出題されます。そのため、幅広い知識を持っておくことが大切です。
【小学校受験】理科的常識(植物)の出題内容は?
「理科的常識(植物)」の問題では、植物のつくりや生態に関する内容が出されます。
断面図
断面図の問題では、野菜や果実を切った時の断面図がよく出されます。身近な野菜や果物と、その断面図を対応させて理解している必要があります。ピーマン、玉ねぎ、りんご、キウイフルーツなど、よく問題に出される野菜・果物は、実際に断面図を見せてあげるのがよいでしょう。
植物のつくり
例えば、「上にある花と下にある葉で、正しい組み合わせになるように線結びをしてください。」のように、植物のつくりに関する問題です。花の形だけではなく、葉や茎の形まで含めて覚えておくことが肝心です。
植物の成長
例えば、「上にある種が育つと、その花が咲きますか。」のように、植物の成長に関する問題です。植物の成長に関する問題では、種・花・実の3つの成長段階が出題されやすくなっています。
植物の生態
例えば、「土の中にできる野菜に丸をつけましょう。」など、植物の生態に関する問題です。草花と花木、土の上にできる野菜と土の中にできる野菜などを区別することができるようにしましょう。
季節
どの花がどの季節に咲くか、どの野菜がどの季節によくとれるか(旬)などを答える問題です。季節の対策を十分にしているお子さまなら、このタイプの問題もしっかりと答えられると思います。
【小学校受験】理科的常識(植物)の解き方は?
「理科的常識(植物)」を解く上で重要なのは、体験を知識として定着させてあげることです。お花見をしたことがあるお子さまでも、桜が春の季節だと答えられないことがあります。あるいは、たんぽぽを見たことがあるお子さまでも、たんぽぽの花と茎の組み合わせを間違えてしまうことがあります。このような間違いが起こるのは、体験したことが知識として定着していないからです。そのために、例えば「体験を振り返る」「体験したことを言語化する」「既存の知識と組み合わせる」などの方法を活用して、知識として定着させてあげることが大切です。
「理科的常識(植物)」の具体的な解き方は、出題内容によって異なります。例えば、断面図の問題を考えてみましょう。断面図では、野菜や果物の「内側の様子」がどうなっているかを問う問題です。もちろん、知っていれば簡単に解ける問題です。しかし、もし知らない問題が出てきたなら、注目すべきは「外側の様子」です。
この解き方は、「合成図形」の考え方と共通しています。例えば、りんごとバナナとぶどうでは、明らかに果物の輪郭が異なります。また、キウイフルーツには細かい毛が生えていたり、みかんにはヘタが付いていたり、メロンには網目があったりと、それぞれに特徴があります。そのため、「中側」がわからなくても「外側」に着目すれば、答えを判断できる場合があります。
ただ、もちろん知識をたくさん持っていることに越したことはないので、実際に体験をしたり、問題集を解いたりするなどして、知識を増やしていくことも大切です。
【知識】理科的常識(植物)(教材サンプル)
【知識】7理科的常識(植物)
教材サンプルのダウンロードはこちらから

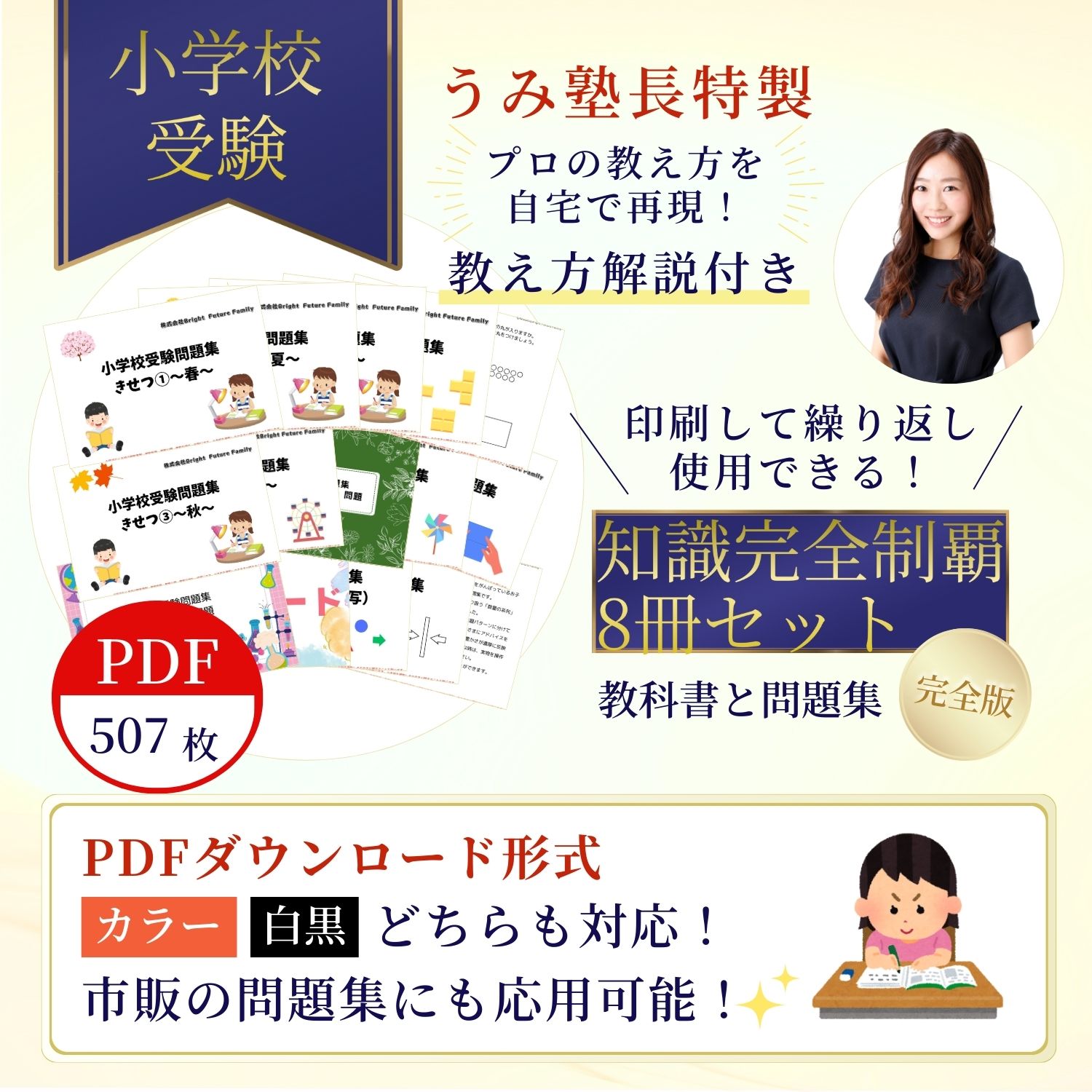
【小学校受験】理科的常識(植物)|まとめ
「理科的常識(植物)」のような知識系の問題では、「知っているか知らないか」で正答率が大きく変わります。小学校受験では、できるだけ多くの知識を持っていると有利です。しかし、一つひとつの知識をバラバラに覚えようとすると、学習効率が悪くなってしまいます。そのため、本記事でご紹介した教材をご活用いただき、効果的な学習をしていただけたらと思います。
1.jpg)











.jpg)