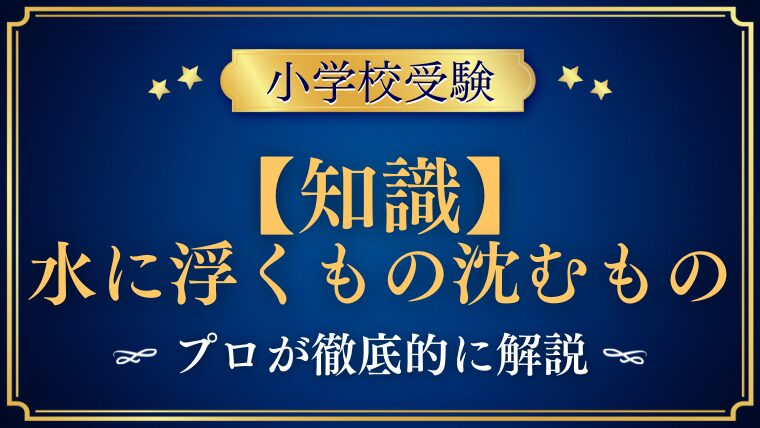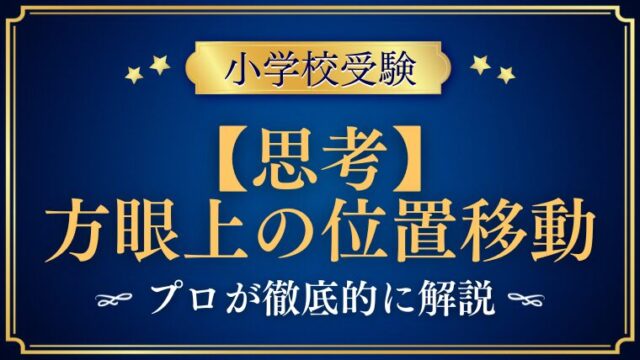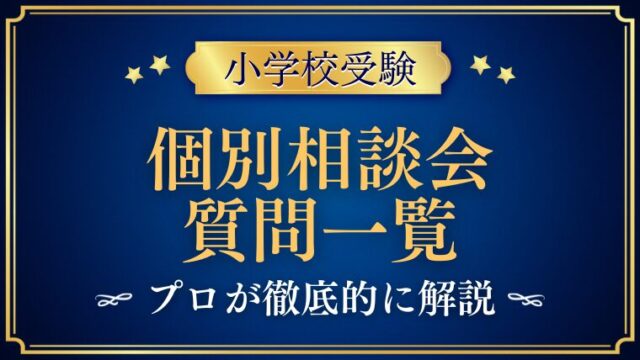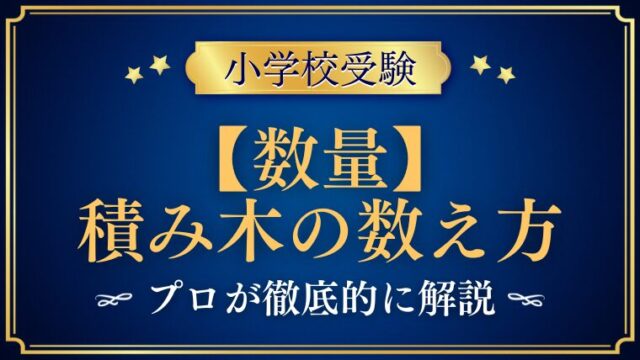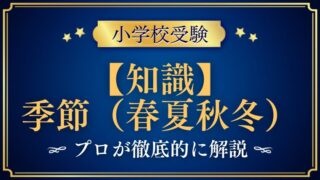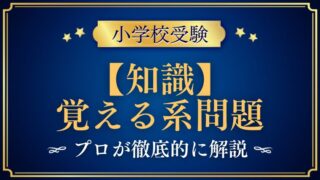【小学校受験】水に浮くもの沈むものの出題意図は?
「水に浮くもの沈むもの」を出題する意図としては、主に次の3つが考えられます。
生活経験の豊かさがあるか
お風呂の入浴剤、プールの浮き輪、水たまりの小石、池の落ち葉、コップに入った氷、料理中のなす、炊飯器に入れたお米など、日常生活の中でも水に何かが浮いていたり、沈んでいたりするのを目にすることがあります。これらの豊かな経験を知識として蓄え、それを活用できるようにしましょう。
科学的な好奇心・探究心があるか
自然現象に興味を持ち、「なぜそうなるのか」「他のものはどうなのか」を探求する心も大切です。理科的常識に関する問題は、身の回りの事象を扱った問題が多くなっています。そのため、日常の様子や出来事に気づき、興味を持ち、調べてみるという心が育つように、適切な声かけをしてあげてください。
論理的思考力があるか
例えば、「レタスを水に入れたとき、水に浮きますか。それとも沈みますか。」という問題が出されたとしましょう。もしレタスが水に浮くか沈むか分からないときでも、「キャベツは水に浮くから、レタスも水に浮くかもしれない。」と推理できるのが望ましいと言えます。経験のないことが出題された時でも、これまでの経験から推論できる論理的な思考力を持っていることが大切です。
【小学校受験】水に浮くもの沈むものの出題方法は?
「水に浮くもの沈むもの」の出題方法には、大きく2つの方法があります。
個別テスト・口頭試問
個別テスト・口頭試問による出題では、イラストや写真を見せて、「どの野菜が水に浮きますか。」と問われるのが定番です。また、一問一答形式ではなく、ひとつの問題に答えたら、その答えに対して追加質問が行われることが多いのも特徴です。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、いくつかの野菜や果物の絵が描かれていて、「水に入れた時に浮くものに丸をつけましょう。」と出題されるのが一般的です。浮くものを選ぶ問題もあれば、沈むものを選ぶ問題もありますので、先生の指示をよく聞いて答えるようにしましょう。
【小学校受験】水に浮くもの沈むものの出題内容は?
「水に浮くもの沈むもの」の出題内容は、水に入れるものの種類で分類することができます。
野菜
「水に浮くもの沈むもの」でよく出される問題のひとつが野菜です。野菜は、お料理をする時にボウルに水を張って野菜を洗ったり、水に浸してアク抜きをしたりすることがあるので、出題されやすくなっているようです。普段からお料理のお手伝いをしているお子さまなら、体験的に理解していることもあるでしょう。
果物
果物も、「水に浮くもの沈むもの」で出題されやすい問題のひとつです。野菜と同様に、料理で目にすることがあるというのが、よく出される理由になっているのだと思われます。ただ、果物を水に浮かべる経験をしたことのあるお子さまはほとんどいないのではないでしょうか。
野菜・果物以外のもの
野菜と果物以外に出題されるものとしては、「木・木製製品」「紙」「プラスチック」「ゴム」「陶器」「金属」「ガラス」「石」「その他」があります。「その他」としては、乾電池や卵などが挙げられます。
【小学校受験】水に浮くもの沈むものの解き方は?
「水に浮くもの沈むもの」の問題が解けるようになるためには、水にものを浮かべる経験をさせてあげることが大切です。水にものを浮かべる経験をさせてあげることで、感覚的に水に浮くかどうかを判断できるようになっていきます。
その上で、解き方を身につけるためには、「水に浮く(沈む)ものの共通点を考えること」が重要になります。共通点を知っておくことで、水に浮かべた経験がないものでも、論理的に答えを導くことができるようになります。
まず、水に浮く野菜の共通点は、「土の上で育つ」ということです。例えば、きゅうり、とうもろこし、白菜などは、水に浮く野菜です。一方で、じゃがいも、れんこん、大根などの「土の中で育つ」野菜は、水に沈む野菜です。
大雨が降って畑が水浸しになってしまった時のことを考えてみましょう。土の上で育っている野菜がどんどん雨水の中に沈んでいってしまったら、野菜は生きていくことができません。また、土の中の野菜が雨水の影響を受けてどんどん地表に出てきてしまったら、やはりそれ以上育つことはないでしょう。このように考えると、「土の上で育つ=水に浮く」「土の中で育つ=水に沈む」というのがイメージしやすいのではないでしょうか。ただし、例外の野菜があることに注意が必要です。
こちらの教材では、「果物」や「野菜・果物以外のもの」が水に浮くかどうかの共通点(覚え方)について詳しく解説しています。また、「水に浮くもの沈むもの」に関する追加質問も掲載しているので、個別テスト・口頭試問対策としても効果的です。
【知識】水に浮くもの沈むもの(教材サンプル)
【知識5】水に浮くもの沈むものサンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
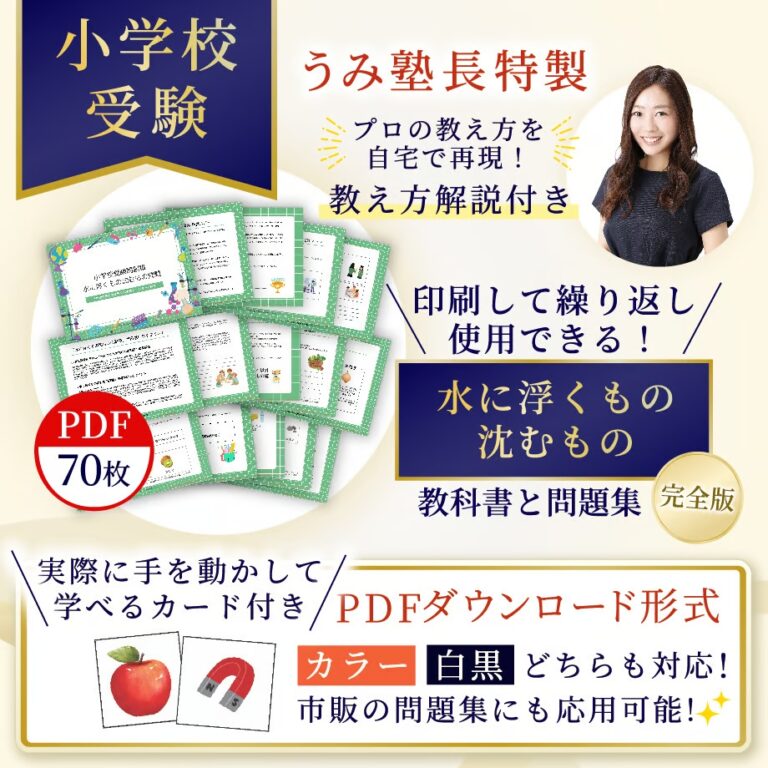
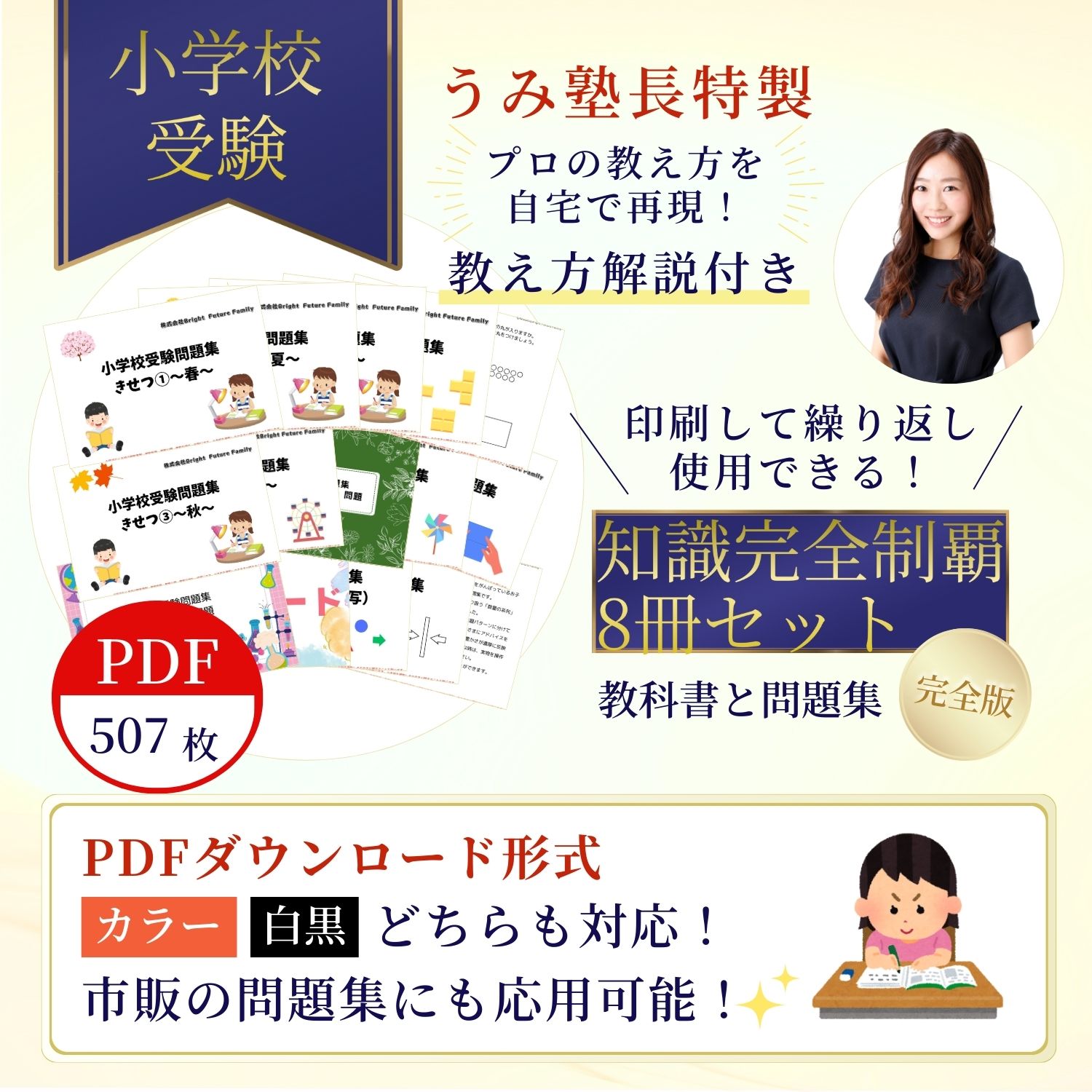
【小学校受験】水に浮くもの沈むもの|まとめ
「水に浮くもの沈むもの」の問題が解けるようになるためには、水に浮かべる経験をすることと、共通点を覚えることが大切です。すべてのものを水に浮かべる経験をすることはできませんから、本記事でご紹介した教材をご活用いただき、解き方(覚え方)を身につけていただけたらと思います。
1.jpg)