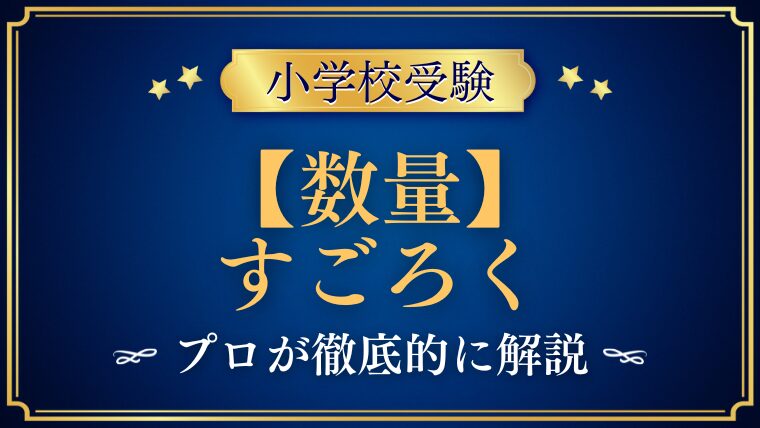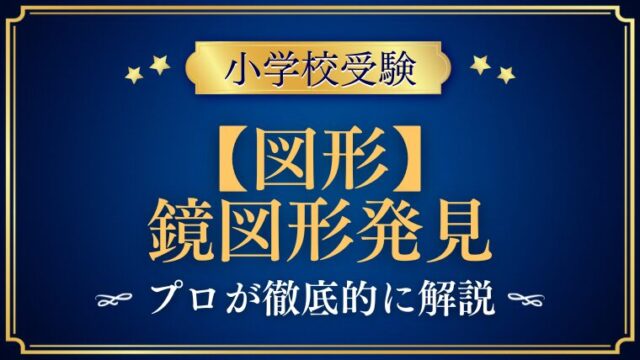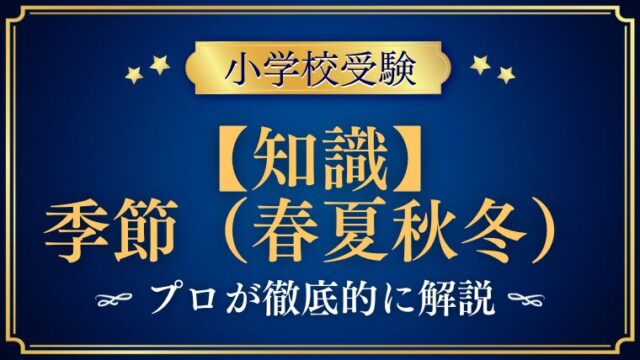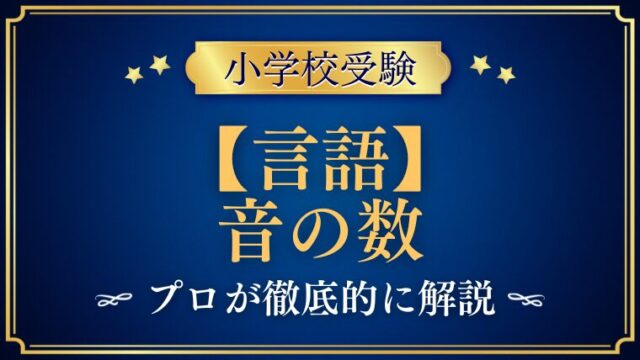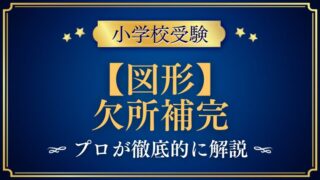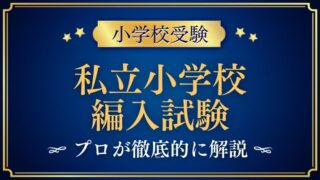【小学校受験】すごろくの出題意図は?
「すごろく」の問題では、生活経験が豊かであるか、基本的な数の概念を理解しているか、条件の理解力があるかなどが見られています。
生活経験が豊かであるか
小学校受験では、数量感覚、図形感覚、語彙力、常識力など、生活経験の豊かさが大切になります。また、すごろくに限らず、お正月、節分、桃の節句、端午の節句、お月見など、伝統的な行事について経験している方が有利に学習を進められます。生活経験が豊かなご家庭は教育熱心なご家庭で、小学校での学習にも協力的であることが多い傾向です。そのため、小学校受験の問題を通して、教育熱心なご家庭かどうかを評価されています。
基本的な数の概念を理解しているか
すごろくのゲームでは、「3ます進む」「2ます戻る」など、数を正しく数えられることが大切です。また、サイコロの目を見て、的確に数を判断できないといけません。「すごろく」という題材を通して、これらの基本的な数の概念を理解しているかどうかが見られています。
条件の理解力があるか
例えば、「じゃんけんで勝ったら振ったサイコロの数だけ進める時、どちらが先にゴールに着きますか」のように、様々な条件を提示されて問題を解くことがあります。このような条件を指示された時には、「どのようなルールですごろくをするのか」を正しく理解する力が必要になります。
【小学校受験】すごろくの出題方法は?
「すごろく」の出題方法には、大きく2つの方法があります。
個別テスト・口頭試問
個別テスト・口頭試問による出題では、実際にすごろくを使った問題が出されることがあります。また、1人でゴールまですごろくをしたり、サイコロの代わりに数字カードを使ったり、口頭での指示を聞きながらすごろくをしたりするなど、ルールや方法を工夫した出題がされることもあります。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、ペーパー上にサイコロの絵とます目が描かれていて「最後にいたますに丸をつけましょう」と出題されるのが定番です。また、「丸の位置まで進んだ時にでたサイコロの目は何でしょう」のように、逆思考型の問題もあります。ペーパーテストでは、実際にサイコロを振ったり、駒を動かしたりすることがないため、数え間違えないように注意しましょう。
【小学校受験】すごろくの出題内容は?
「すごろく」の出題内容は、大きく4つあります。また、「すごろく」のルールを工夫したバリエーションの出題もあります。
最後に到達したますを答える問題
「すごろく」の基本的な問題です。サイコロをしている人や動物、サイコロの目が描かれていて、「サイコロの目だけ進んだら、男の子はどのますまで進めますか。」のように聞かれます。サイコロの目が1つだけの問題もあれば、サイコロの目が3つ程度ある問題もあります。
サイコロを振る前にいたますを答える問題
移動した後の位置と振ったサイコロの目を見て、移動する前にいたますを答える問題です。どこにいたのかを遡って考えるため、「すごろく」の逆思考型の問題になっています。「最後に到達したますを答える問題」と同様に、複数のサイコロが示されていることがあります。
振ったサイコロの目を答える問題
スタートの位置と移動した後の位置を見て、出たサイコロの目を答える問題です。サイコロを1つ選ぶ問題なら比較的簡単ですが、サイコロを2つ以上振る問題ではある程度の思考力が必要になります。
先にゴールした人を答える問題
「四角の中の順番でサイコロの目が出た時、先にゴールした人はどちらですか。先にゴールした人を丸で囲みましょう。」のように、どちらが先にゴールしたかを答えるタイプの問題です。実際のすごろくを問題に落とし込んだような内容で、ペーパー上ですごろくの様子をイメージできることが大切です。
ルールを工夫したすごろく
上記の4つの出題内容に加えて、ルールを工夫したタイプの問題が出されることがあります。例えば、「じゃんけんグリコ」のように、「パーで買ったら3ます、チョキで勝ったら2ます、グーで勝ったら1ます進めます」というルールになったり、「サイコロを振ってりんごが出たら3ます進んで、バナナが出たら2ます進んで、ぶどうが出たら1ます戻ります」というルールになったり、学校ごとに工夫した問題を出すことがあります。
【小学校受験】すごろくの解き方は?
「すごろく」の問題を理解する上で大切なことは、すごろくに慣れておくことです。すごろくに慣れているお子さまは、「すごろく」の問題に対する飲み込みが早く、ほとんどの出題内容をきちんと理解することができます。
「すごろく」の問題の解き方では、鉛筆を駒の代わりにするのがポイントです。ペーパーテストで難しいのは、実際に駒を動かして考えられないことです。頭の中だけで考えようとすると、数え始めるますを間違えたり、到着したますを数え落としたりして、間違えてしまうお子さまがいます。しかし、鉛筆を駒の代わりにして考えることで、問題をイメージしやすくなりますし、このような間違いをしなくなります。
また、サイコロを2つ以上振るような問題では、たし算を使わないのもポイントです。小学校受験の問題は、計算ができなくても解けるように作られているので、わざわざたし算をする必要がありません。
たし算を使わない解き方や逆思考型の問題の解き方、ルールを工夫した問題の解き方などについてはこちらの教材で解説しています。「すごろく」の問題が解きやすくなる方法を解説していますので、学力の向上にお役立てください。
【数量】すごろく(教材サンプル)
【数量】4 すごろくサンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
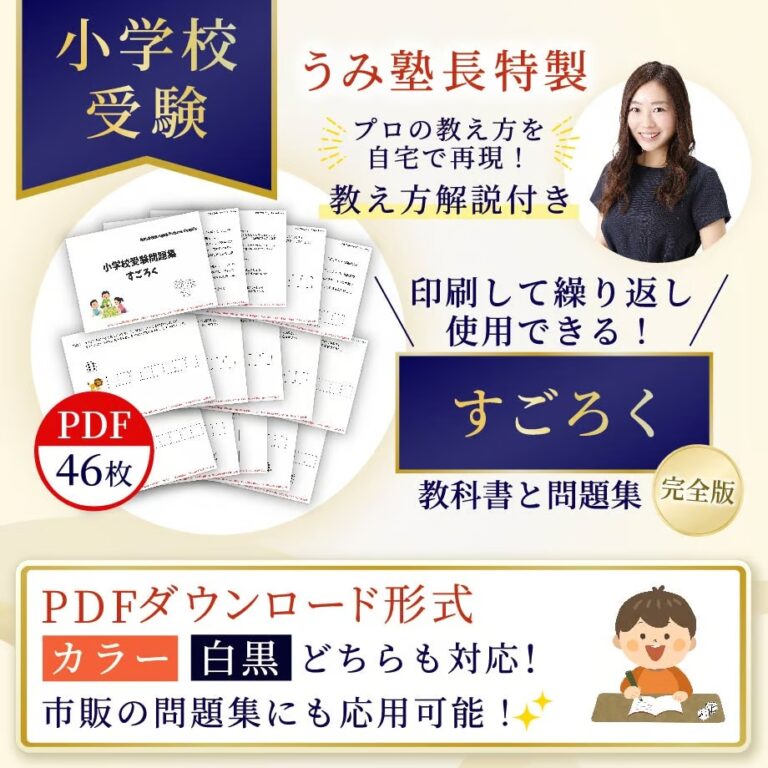
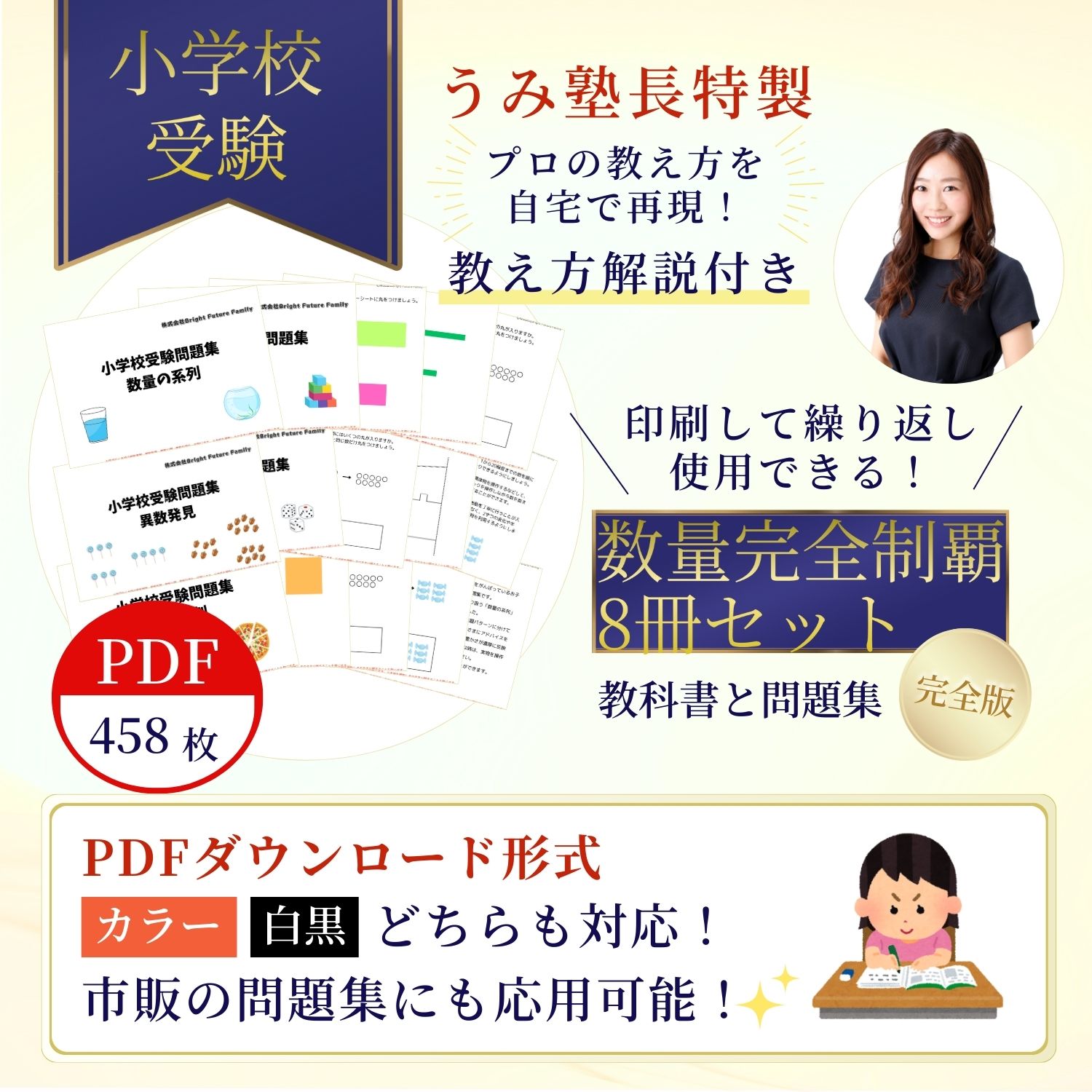
【小学校受験】すごろく|まとめ
「すごろく」の問題は、お子さまの生活経験により得意不得意が分かれやすい問題です。すごろくで遊ぶことは、数量感覚を養ったり、社会性を向上させたりするのにも効果がありますので、ぜひご家庭でもすごろく遊びをしていただけたらと思います。ただ、ペーパーテストとなるとうまく解けないお子さまもいらっしゃいます。そのため、すごろくで遊ぶと同時に、本記事でご紹介した教材をご活用いただき、効率よく学習をしていただけたらと思います。
1.jpg)