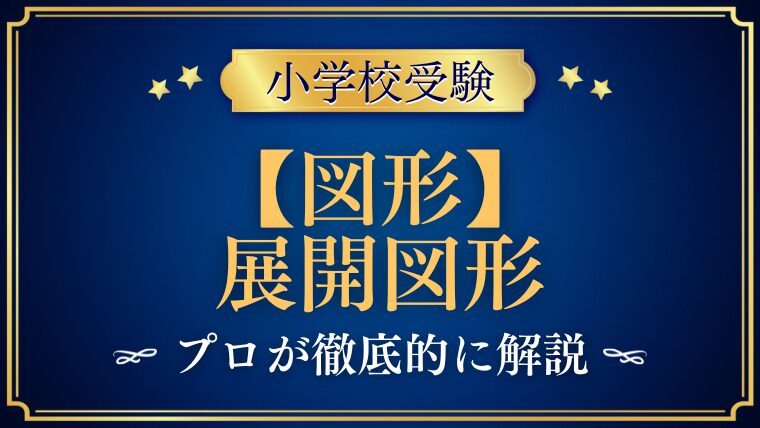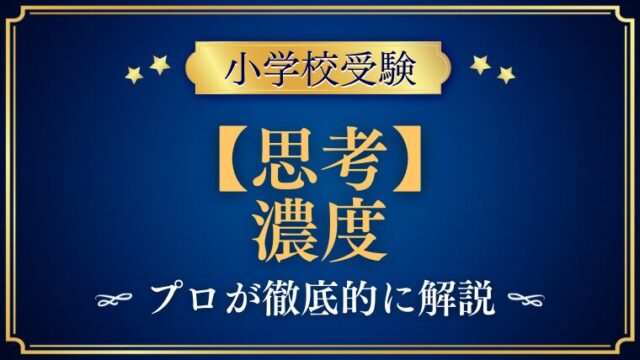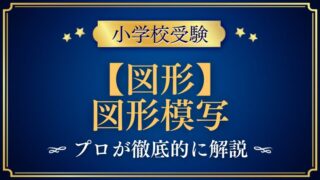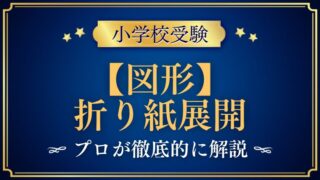【小学校受験】展開図形の出題意図は?
「展開図形」の問題を出すことで、主に次のような能力があるかを評価されています。
空間認識力があるか
頭の中で図形を展開したり、組み立てたりするには、高度な空間認識力が必要になります。「切った折り紙を展開したらどのような形ができるのか」「サイコロの形に組み立てるとどの面とどの面が向かい合うのか」など、頭の中で具体的に図形をイメージできるようにしましょう。
論理的思考力があるか
「展開図形」の問題は、サイコロの形を展開する問題も、折り紙を切って展開する問題も、論理的に考えることで正解の形がイメージしやすくなります。特にサイコロの形を展開する問題は、出題パターンが3つしかないので、論理的に思考することが大切です。
ご家庭での教育力があるか
折り紙を切って開く活動も、サイコロの形を展開する活動も、日常生活の中ではなかなか経験することがないと思います。保育園や幼稚園で七夕飾りを作るときに折り紙を切って開く活動をしたことがあるお子さまもいると思いますが、それを知識として学習することは少ないでしょう。つまり、「展開図形」がすらすら解けるお子さまは、ご家庭で図形に関する体験を積極的にしていると考えることができます。そのため、「『展開図形』ができる子は、家庭でも教育的な活動を積極的に取り入れているのだろう」と小学校の先生は判断することになります。
【小学校受験】展開図形の出題方法は?
「展開図形」の出題方法には、大きく2つの方法があります。
個別テスト・口頭試問
個別テスト・口頭試問による出題では、展開図形を見せられて、「この形を組み立てると、りんごの反対にはどの果物が来ますか。」や「この折り紙を線のところで切って開くと、どの形ができているか選んでください。」と質問されるのが定番です。図に描き込みながら考えることができないので、直感的な図形認識と正解をすぐに見つける判断力が必要になります。
ペーパーテスト
ペーパーテストでも、展開されたサイコロの形を見て組み立てたサイコロの形を考えたり、折り紙を切って開いた時にできる形を答えたりする問題が出されます。サイコロを展開する問題では「組み立てた時にサイコロの形になるものをすべて選びましょう。」と言われたり、折り紙を展開する問題では折り紙が二つ折りになっていたりして、個別テスト・口頭試問よりも難しい問題を出されることが多くなっています。
【小学校受験】展開図形の出題内容は?
「展開図形」には、大きく分けて「サイコロ展開」と「折り紙展開」の2つの出題内容があります。
サイコロ展開
立方体を展開した時にできる形や、展開図を立方体に組み立てた時にできる形を考える問題です。通常のサイコロのように1〜6までのドットがある場合もありますし、果物や動物が描かれている場合もあります。サイコロ展開はパターン化された問題が多いので、確実に正解したい問題です。
折り紙展開
折り紙などを切って開いた時にできる形を考える問題です。折り紙の折り方により、展開した時の形が異なる点に注意して問題を解く必要があります。
なお、「折り紙展開」については、『小学校受験問題集 折り紙展開』でも基礎から応用まで幅広い問題を扱っていますので、そちらも参考にしてください。
【小学校受験】展開図形の解き方は?
「展開図形」には、「サイコロ展開」と「折り紙展開」があり、それぞれに解き方が異なります。先述の通り、「折り紙展開」は、別の教材で詳しく解説していますので、ここでは「サイコロ展開」の解き方について解説します。
「サイコロ展開」の問題を解けるようにするためには、サイコロに親しむところから始めるのがよいでしょう。「サイコロは6つの面でできていること」「面には1から6の数があること」「向かい合う面の合計が7になること」などに気づけるといいですね。このようなサイコロの性質にお子さまだけで気づくのは難しいこともありますので、「今6が出ているね。じゃあ、反対側の数は幾つだと思う?」など、クイズ形式で問題を出しながら、楽しくサイコロの性質について学べるとよいでしょう。
サイコロの性質がわかったら、サイコロの展開図の性質についても学習します。サイコロの展開図には11パターンありますが、さらに区分すると3パターンに分けることができます。たった3パターンを覚えてしまえば、「組み立てた時にサイコロになる形はどれですか」という問題は確実に正解することができます。気をつけていただきたいのは、ただ暗記するだけにならないことです。実際に展開図形を組み立てたり、展開したりする活動を通して、体験的に学習するようにしてください。
サイコロを組み立てた時に向かい合う面を聞かれるのも、「サイコロ展開」で定番の問題です。向かい合う面を答える問題も、3つのパターンに分けて考えると考えやすくなります。詳しい解き方の解説はこちらの教材で扱っています。体験的に学習しながらパターン化することで、「サイコロ展開」の問題が簡単に解けるようになりますよ。
【図形】展開図形(教材サンプル)
【図形】10 展開図形サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
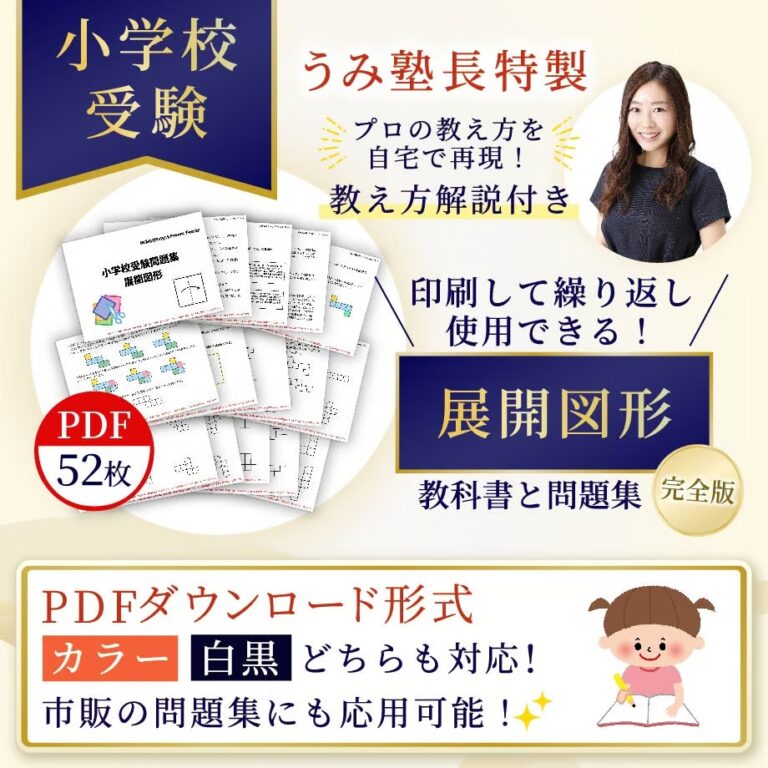
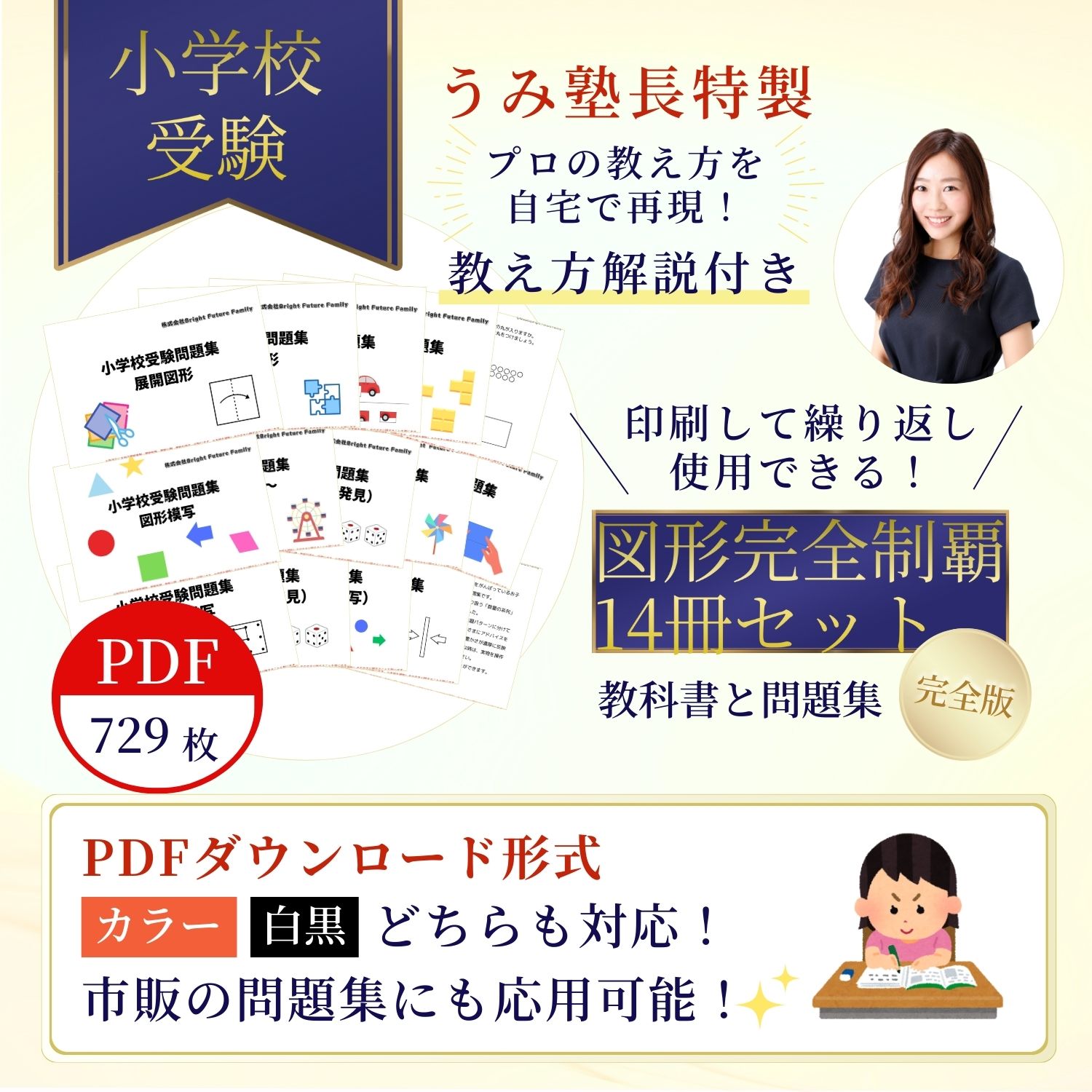
【小学校受験】展開図形|まとめ
「展開図形」には、大きく2種類の問題内容があります。「サイコロ展開」は、体験的に学習しながらパターン化することで、簡単に解けるようになります。「折り紙展開」の解き方は、本記事でご紹介した教材と、別冊「小学校受験問題集 折り紙展開」で解説しています。ぜひこれらの教材をご活用いただき、難易度の高い「展開図形」の効果的な対策をしてください。
1.jpg)