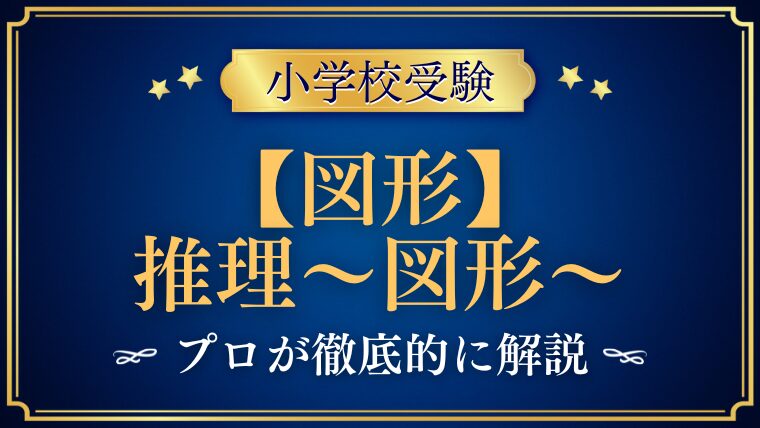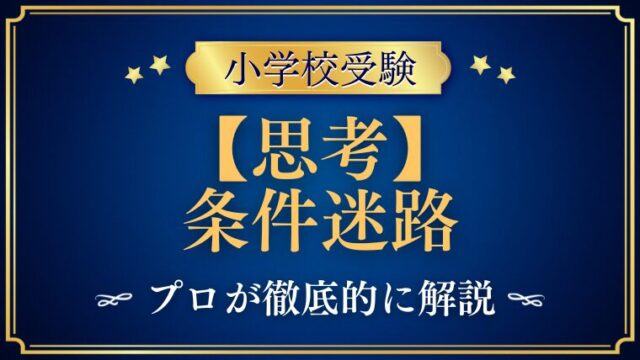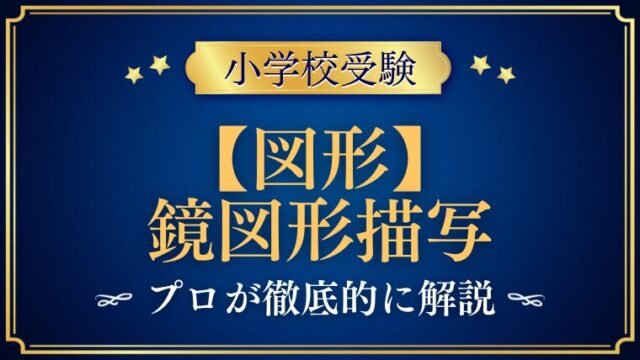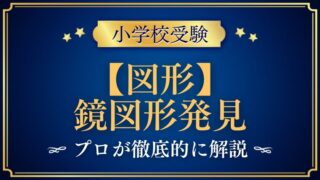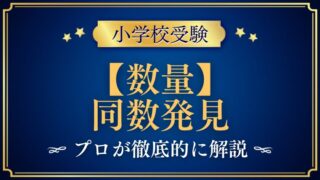【小学校受験】推理〜図形〜の出題意図は?
推理力を必要とする図形分野の問題では、次のような力があるかを評価されています。
論理的思考力・推理力があるか
「推理」に関する問題ですので、当然ながら推理力が必要になります。ただ、図形分野における「推理」では、論理的に考えることで解ける問題がほとんどです。そのため、感覚的に問題を解くだけでなく、「どうしてこの答えになるのか」「どうしてこの答えは間違いなのか」を考えながら解くことが大切です。
観察力があるか
「形のどの部分に違いがあるのか」「形が並んでいる順番はどうなっているのか」など、よく観察して問題に答えることが大切です。特に、「同図形発見・異図形発見」では細かい違いにも気づくことができる観察力が必要になります。
空間認識力があるか
「空間認識力」とは、ものの位置関係や形、向きなどを認知する力のことです。「図形」に関する問題は、空間認識力が高いお子さまほど有利に解くことができます。特に「鏡・水面」や「四方図」などの問題では高い空間認識力が必要になる問題があります。
忍耐力があるか
「推理」に関する問題は、他の単純な問題に比べて難易度が高い問題が多くなっています。そのため、じっくり考えたり、諦めずに答えを探したりする忍耐力も大切です。問題を解いている姿勢も評価されていることを意識するようにしましょう。
【小学校受験】推理〜図形〜の出題方法は?
「推理〜図形〜」の出題方法には、大きく2つの方法があります。
個別テスト・口頭試問
個別テスト・口頭試問による出題では、「観覧車に乗るために、動物さんたちが列に並んでいます。この中で、赤い観覧車に乗れる動物さんは誰ですか。」など、先生との会話の中で「推理」の問題が出題されるのが一般的です。絵や図形を示されて答えることになりますので、よく絵や図形を見て答えるようにしましょう。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、「観覧車に乗るために、動物さんたちが列に並んでいます。この中で、赤い観覧車に乗れる動物さんに丸をつけましょう。」など、先生が問題を読み上げて、ペーパー上で答える問題が一般的です。丸をつける以外にも、「バツをつけましょう」「赤鉛筆を使って丸で囲みましょう」などの指示が出されることがあるので、最後までしっかりと問題を聞くようにしましょう。
【小学校受験】推理〜図形〜の出題内容は?
「推理〜図形〜」に出題パターンはいろいろとありますが、次の5つの問題がよく出されます。
観覧車
観覧車などが回ったときに、どのような配置になるかを問う問題です。小学校受験では頻出の問題ですが、難易度はそれほど高くありません。また、「回転図形」と解き方が似ていることも特徴です。
ルーレット
「ルーレット」は、「観覧車」と似ていて、図形が回転したときにどのような配置になるかを問う問題です。この問題も観覧車と同様の解き方で解けるので、「観覧車」と一緒に対策をしておきましょう。
鏡・水面
「鏡・水面」は、鏡や水面に映った物がどのように見えるかを問う問題です。基本的には「展開図形(反転図形)」と同じ考え方で、問題によって水平方面に反転するか、垂直方面に反転するかが決まります。
四方図
「四方図」は、ある物を別の角度から見たときにどのように見えるかを問う問題です。前後左右から見た図を考えるので「四方図」と呼びますが、上から見た図(俯瞰図)が出題されることもあります。
同図形発見・異図形発見
「同図形発見・異図形発見」は、いわゆる間違い探しのような問題です。このパターンの問題は、『小学校受験問題集 回転図形』で扱っていますので、詳しくはそちらの教材で学習していただけたらと思います。
【小学校受験】推理〜図形〜の解き方は?
図形分野における「推理」の問題は、主に「回転図形」と「展開図形(反転図形)」の解き方を活用することになります。
まず、「回転図形」の考え方は、「観覧車」「ルーレット」の問題で活用することができます。「回転図形」で大切な考え方の1つが、「順番は変わらない」ということです。どんなに回転しても形の並び(順番)は変わりませんので、並び(順番)を手がかりに問題を解くようにしましょう。頭の中で回転をイメージするのが難しいお子さまでも、順番を確認するだけで解ける問題はたくさんあります。
その他にも、押さえておくべきポイントや出題内容ごとのポイントは、こちらの教材に収録しています。一見難易度の高そうな問題でも、解き方のポイントを知っていれば簡単に解ける問題もありますので、こちらの教材を活用して解き方を身につけていただけたらと思います。
【図形】推理〜図形〜(教材サンプル)
【図形】13 推理〜図形〜サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
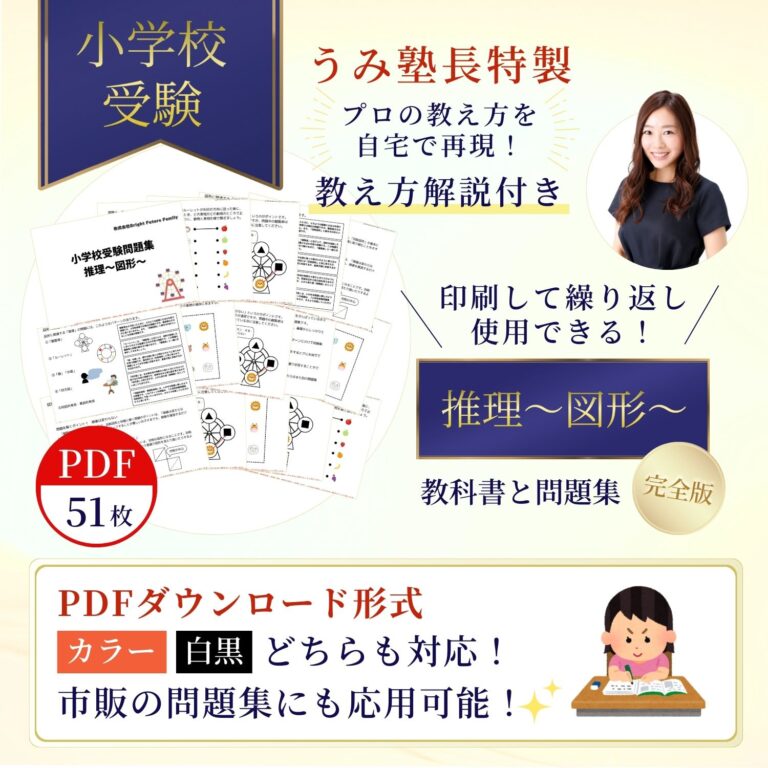
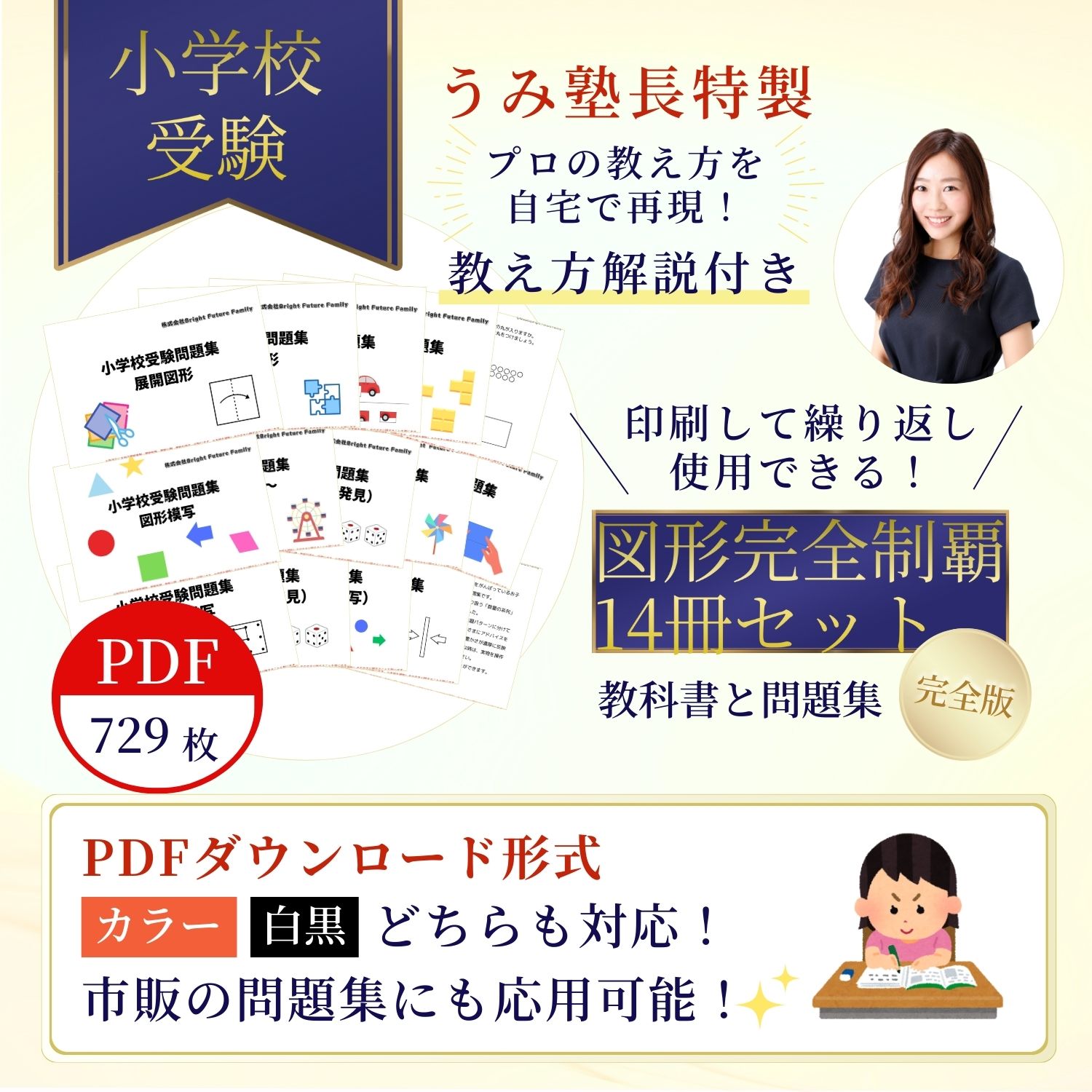
【小学校受験】推理〜図形〜|まとめ
「推理〜図形〜」は、推理力だけではなく、論理的に考える力が必要な問題です。ただ、解き方を知っていれば簡単に解ける問題がたくさんありますので、きちんと解き方を身につけさせてあげましょう。ぜひ本記事でご紹介した教材をご活用いただき、正しい解き方で効率よく学習できるようにしてください。
1.jpg)