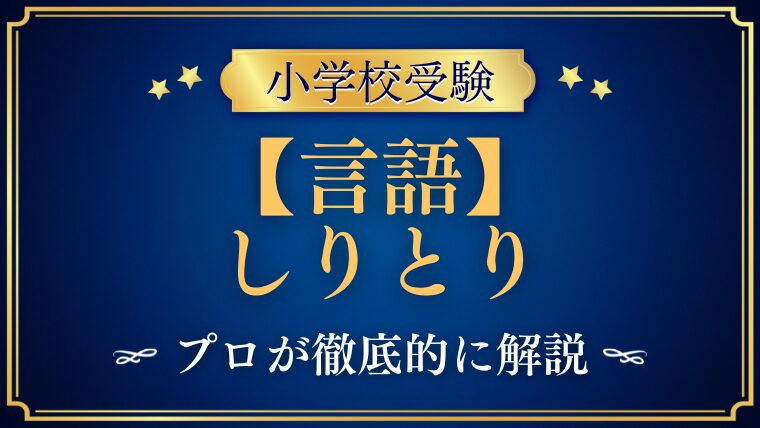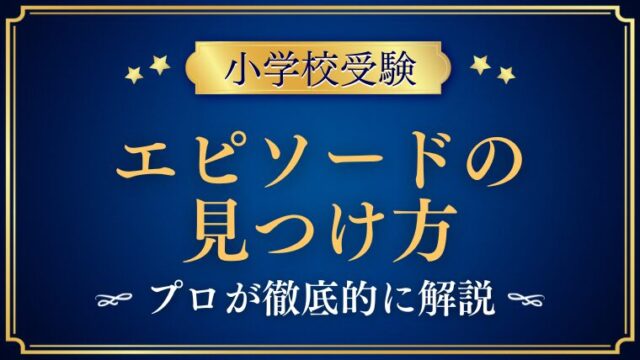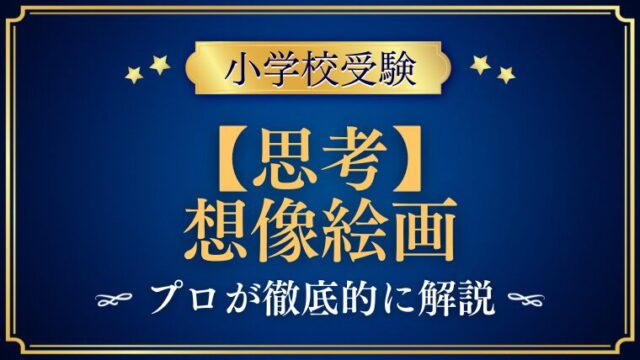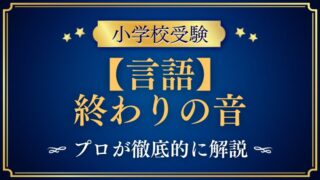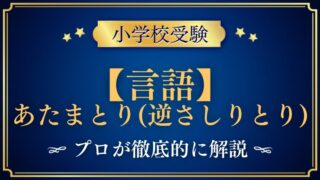【小学校受験】しりとりの出題意図は?
「しりとり」の問題が出される理由として、主に次のことが挙げられます。
ご家庭の教育力があるか
しりとり遊びは、お子さまにとって身近な遊びです。特に、幼児期のしりとり遊びは知育的な効果が期待できるので、ご家庭でしりとり遊びをしているご家庭も多いことでしょう。このような一般的な遊びをご家庭でも取り入れているかどうか、ご家庭の教育力が問われています。
言語力があるか
しりとり遊びをする上では、「語彙力」「音韻の認識」「はじめの言葉・終わりの言葉の理解」などが必要になります。例えば、「りんごの最後の音は『ご』だから、『ご』ではじまる言葉は・・・」と考える中で、これらの力が育っていきます。言語力を鍛えることで、「しりとり」の問題が簡単に解けるようになっていきます。
柔軟な思考力があるか
「しりとり」の問題では、絵や写真を見て何を表しているのかを判断しなくてはなりません。例えば、さんまのイラストがあった時に、「さかな」と考えるのか「さんま」と考えるのか、前後の言葉の関係を踏まえて柔軟に判断する必要があります。また、通常のしりとりとは異なるルールのしりとりを扱う問題もありますので、柔軟にルールを理解する理解力も必要です。
コミュニケーション力があるか
「しりとり」の問題は、個別テスト・口頭試問で出されることもあります。この場合、言語力や思考力に加えて、コミュニケーション力も必要になります。きちんと相手の言葉を聞き取り、相手に聞こえる声ではっきりと言葉を伝えられるようにしましょう。
【小学校受験】しりとりの出題方法は?
「しりとり」の出題方法には、大きく2つの方法があります。
個別テスト・口頭試問
個別テスト・口頭試問による出題では、学校の先生と実際にしりとりをする課題を出されるのが定番です。しりとりをしている様子を通して、「語彙力があるか」「課題に集中できるか」「発語に課題はないか」「コミュニケーション力があるか」などを総合的に見られています。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、様々なタイプの出題方法が考えられますが、多くの問題は絵を線で繋ぐか、当てはまる絵に丸をつける問題です。例えば、「しりとりの順になるように絵を線でつなぎましょう。」「しりとりが完成するように、四角に当てはまる絵に丸をつけましょう。」などの問題が定番です。
【小学校受験】しりとりの出題内容は?
「しりとり」の出題内容には、通常のしりとりの他にも様々なパターンがあります。
通常のしりとり
いわゆる普通のしりとりです。例えば、「えんぴつ→積み木→きつね」のようにしりとりがつながります。「しりとり」の問題の中では最も基本的な問題ですので、確実に解けるようにしましょう。
あたまとり(逆さしりとり)
あたまとり(逆さしりとり)は、ある言葉の1文字目の音で終わる言葉をつなげていくタイプのしりとりです。例えば、「かまきり→いか→サイ」のようにつながります。「逆さしりとり」とも言われるように、反対から考えると「サイ→いか→かまきり」のように、普通のしりとりになります。
◯つ目の音・◯つの音でつなげるしりとり
2つ目の音や3つ目の音、真ん中の音などで繋げるしりとりです。例えば、「2文字目の音をつなげてしりとりをしましょう。」と言われたら、「たいやき→いのしし→のこぎり」のようにつながります。また、「終わりの2つの音でつなげる」と言われたら、「カーテン→テントウムシ→虫とり網」のように言葉がつながります。
音の数を指定されたしりとり
「3つの音でできている言葉でしりとりをします。」のように条件を指定される問題です。例えば、「とけい→いちご→ごりら」のように言葉がつながります。ある程度は感覚的に理解できると思いますが、「音の数」について理解しているとこのタイプの問題が解きやすくなります。
【小学校受験】しりとりの解き方は?
「しりとり」の問題が得意になるためには、豊かな言葉感覚を持っていることが大切です。「感覚」というと「センスがあるかないか」と考えてしまう方がいますが、小学校受験における「感覚」のほとんどは知識と経験です。そのため、「しりとり」の問題が得意になるためには、しりとりの経験をすること、語彙を増やすこと、言葉遊びをすることなどが有効です。実際に問題を解く上では、通常のしりとりから徐々にステップアップして、幅広い「しりとり」の問題に慣れていくようにしましょう。
「しりとり」の問題では、問題を解きながら語彙力を向上させていくことも大切です。例えば、缶ジュースの絵は、「缶」「飲み物」「空き缶」「ジュース」など、様々な読み方ができます。単に問題を解くだけではなく、「この絵は他にもどんな読み方ができるかな?」とお子さまに問いかけながら、語彙力を増やしていきましょう。
また、小学校受験の問題では、ストーブ・ぼんぼり・急須・こたつ・こけし・じょうろ・そろばんなど、最近ではあまり見かけない物や、人によっては全く馴染みがない物が出てくることがあります。もし知らない物の絵が出てきたら、消去法を活用しながら類推して問題を解かなくてはいけません。その意味でも語彙が豊富な方が有利ですので、語彙を増やすことが大切です。
本オリジナル教材は、しりとりの基礎から応用まで幅広い問題に対応できるように3つの教材をご用意しました。『しりとり基礎編』『あたまとり(逆さしりとり)』『しりとり応用編』の順で問題を解くことで、「しりとり」の問題に慣れながら徐々にレベルアップしていけるように配慮しています。この3冊を解けるようになれば、小学校受験における「しりとり」の問題が十分に解けるようになることでしょう。
【言語】しりとり(教材サンプル)
【言語】6 しりとり応用編サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
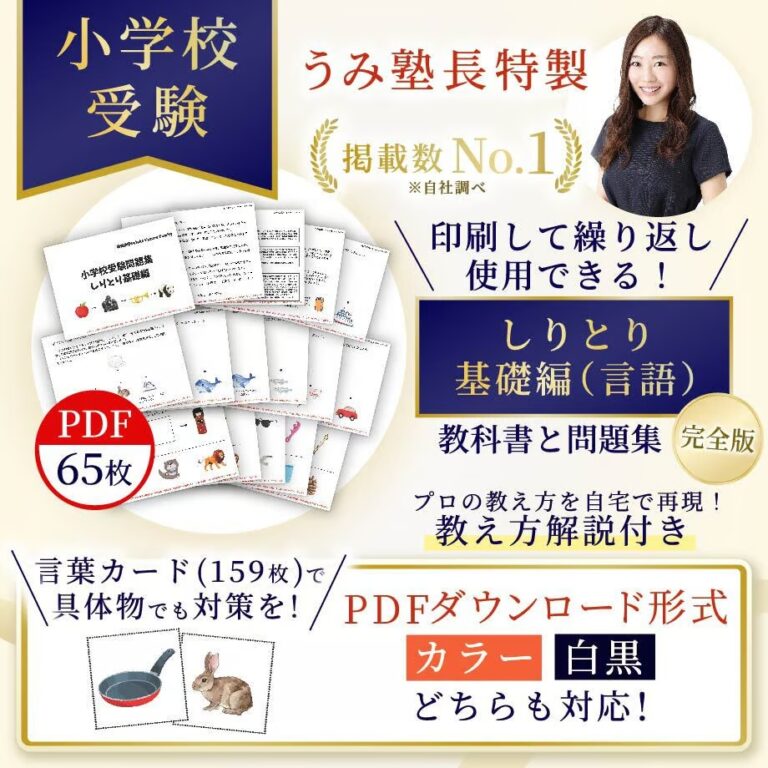

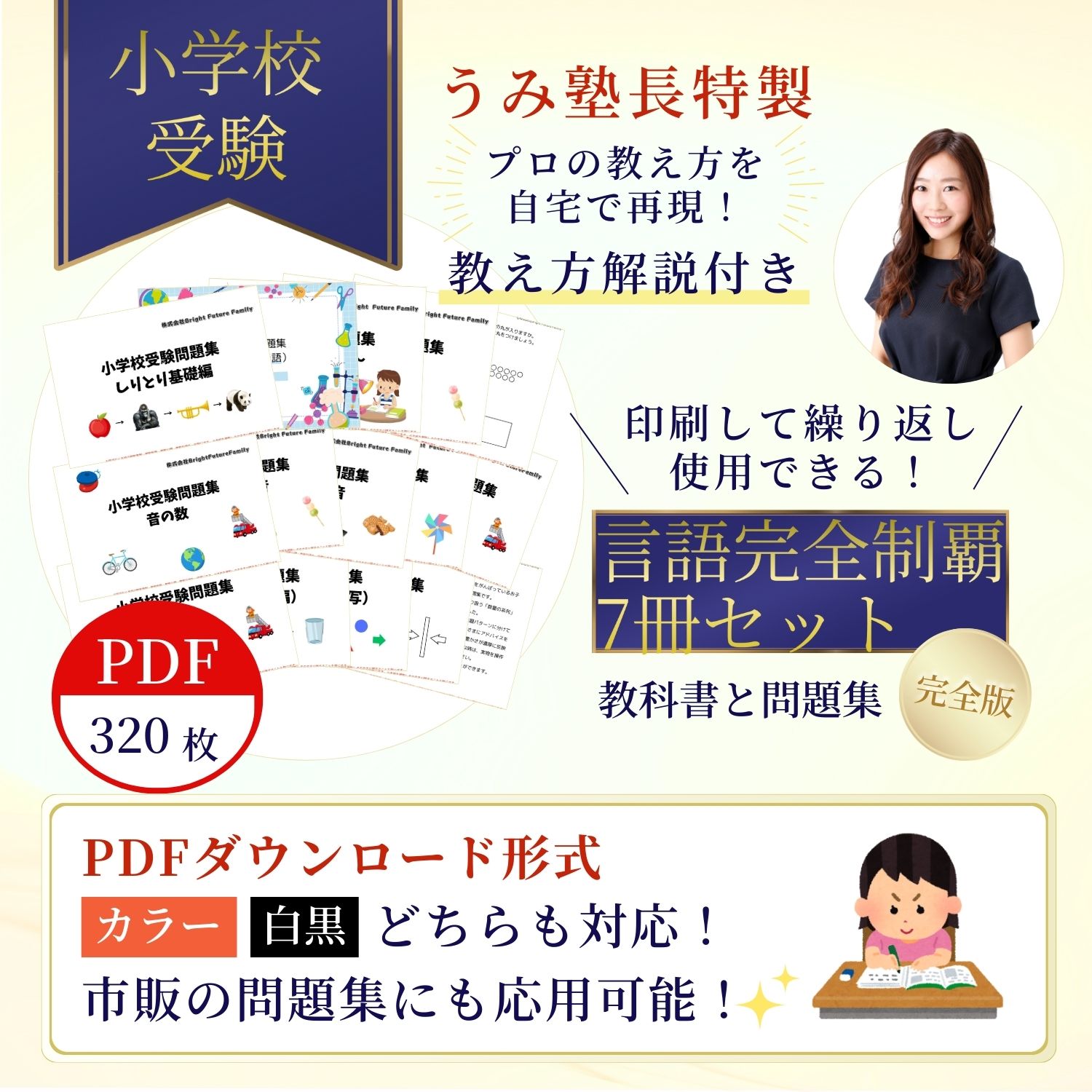
【小学校受験】しりとり|まとめ
小学校受験で頻出のしりとりを題材にした問題は、通常のしりとりはもちろん、ルールを工夫した問題もよく出されます。そのため、どのような問題が出されても対応できるように、幅広い対策をしておきましょう。また、しりとりは知育にも効果的な遊びです。ぜひ本記事でご紹介した教材をご活用いただき、言語力や思考力の向上に役立てていただけたらと思います。
1.jpg)