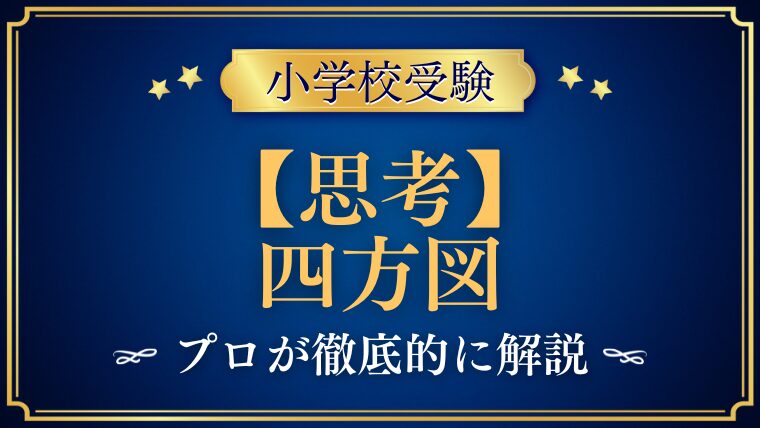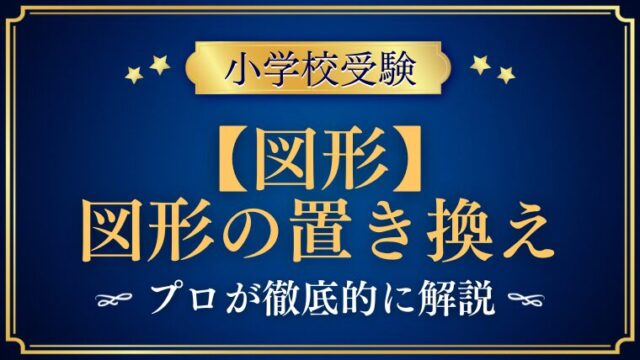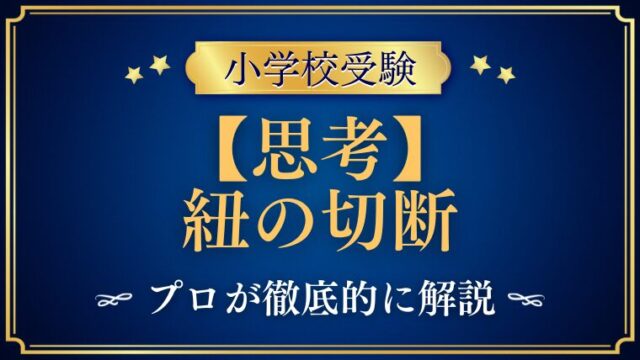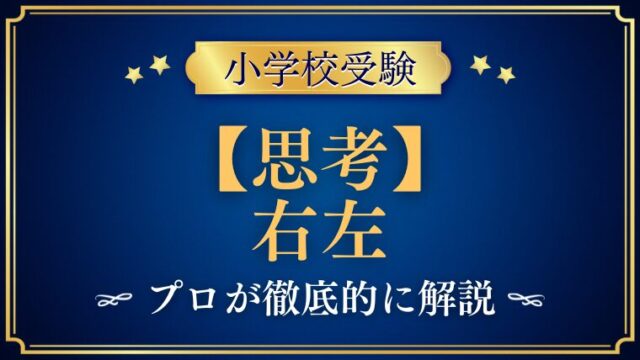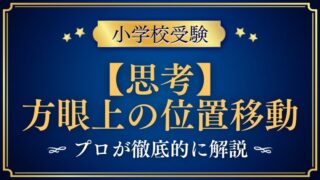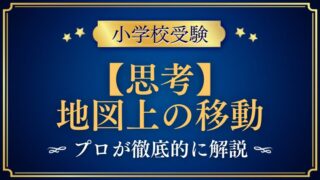【小学校受験】四方図の出題意図は?
「四方図」は空間認識力や位置関係を把握する力などが必要で、これらの力がきちんと発達しているかを評価されています。
空間認識力があるか
「空間認識力」とは、ものの位置関係や形、向きなどを認知する力のことです。「四方図」の問題を解くためには、頭の中で立体や物体を回転させて、別の角度から見た時にどのように見えるかをイメージする力が必要になります。
位置関係を把握することができるか
空間認識力と同じくらい、前後左右の位置関係を把握する力も重要になります。例えば、積み木が積まれている位置を把握し、それが別の角度から見た時にどの位置に配置されるのかを考えなければいけません。「四方図」は立体の位置関係を把握する必要があるため、平面上の位置関係を把握するよりも高い思考力が求められます。
論理的思考力があるか
「四方図」では、別の角度から見た時の形を論理的に考える力も必要になります。例えば、「私から見てコップの持ち手が右にあるから、左にいる人からはコップの持ち手が見えなくなるはず」のように、論理的に思考することができると、正解の形を考えやすくなります。
推理力があるか
「四方図」では、見えないところの形を推理する力が必要になることもあります。ただ、論理的に考えれば十分に推理することができますので、論理的に考えて推理するようにしましょう。
【小学校受験】四方図の出題方法は?
「四方図」の出題方法は、ペーパーテストによる方法が一般的です。
ペーパーテスト
ペーパーテストによる出題では、ある絵が描かれていて、それを指定された方から見た時に見える正しい絵を選ぶという出題が定番です。描かれている絵は、積み木・ブロック・道具・動物など様々です。また、前後左右の4方向の他にも、上から見下ろした時にどのように見えるかを問う「俯瞰図」が出題されることもあります。
【小学校受験】四方図の出題内容は?
「四方図」の出題内容には、「四方図(前後左右の4方向)」と「俯瞰図(上から見下ろしたように見た図)」の2種類があります。
四方図
ある絵を正面から見た時に、他の方向から見るとどのように見えるかを問う問題です。立体を横から見たり後から見たりした時の、前後や左右の関係を考えなければいけません。正しい位置関係を論理的に考える思考力が必要です。
俯瞰図
ある絵を上から見下ろした時に、どのように見えるかを問う問題です。1つの立体の俯瞰図を考える問題なら、四方図と同じようにイメージすれば問題なく解けると思います。2つ以上の立体が配置されているなら、ものの位置関係を把握することも必要になります。
【小学校受験】四方図の解き方は?
「四方図」を解くためには、空間認識力が重要になりますが、空間認識力が完成するのは10歳前後と言われています。そのため、幼児期においては遊びを通して空間認識力を鍛えることが有効です。例えば、キャッチボールやジャングルジムは、遠近感や上下左右の感覚を鍛えるのに効果的です。
ただ、受験期には空間認識力をじっくり育てる時間がないことも多く、ある程度解き方のテクニックを教えてあげることも必要でしょう。例えば、円柱の側面は真横から見ると長方形に見えることや、上面や底面は合同な円になっていることなど、どの部分に着目して形を捉えたらよいのかを適切にアドバイスしてあげることが大切です。その他の解き方のテクニックについては、こちらの問題集で解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
【思考】四方図(教材サンプル)
【思考】6 四方図サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
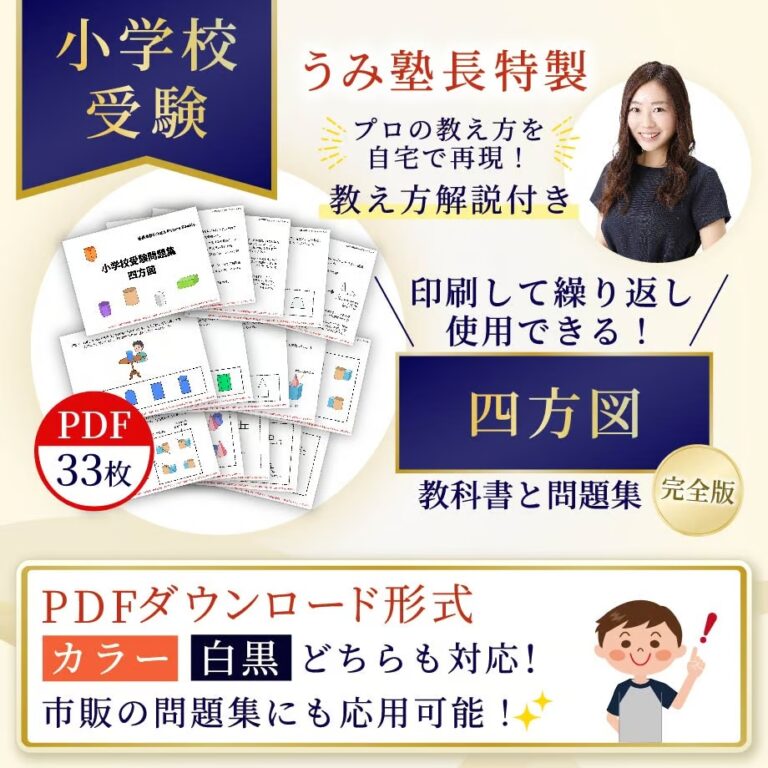
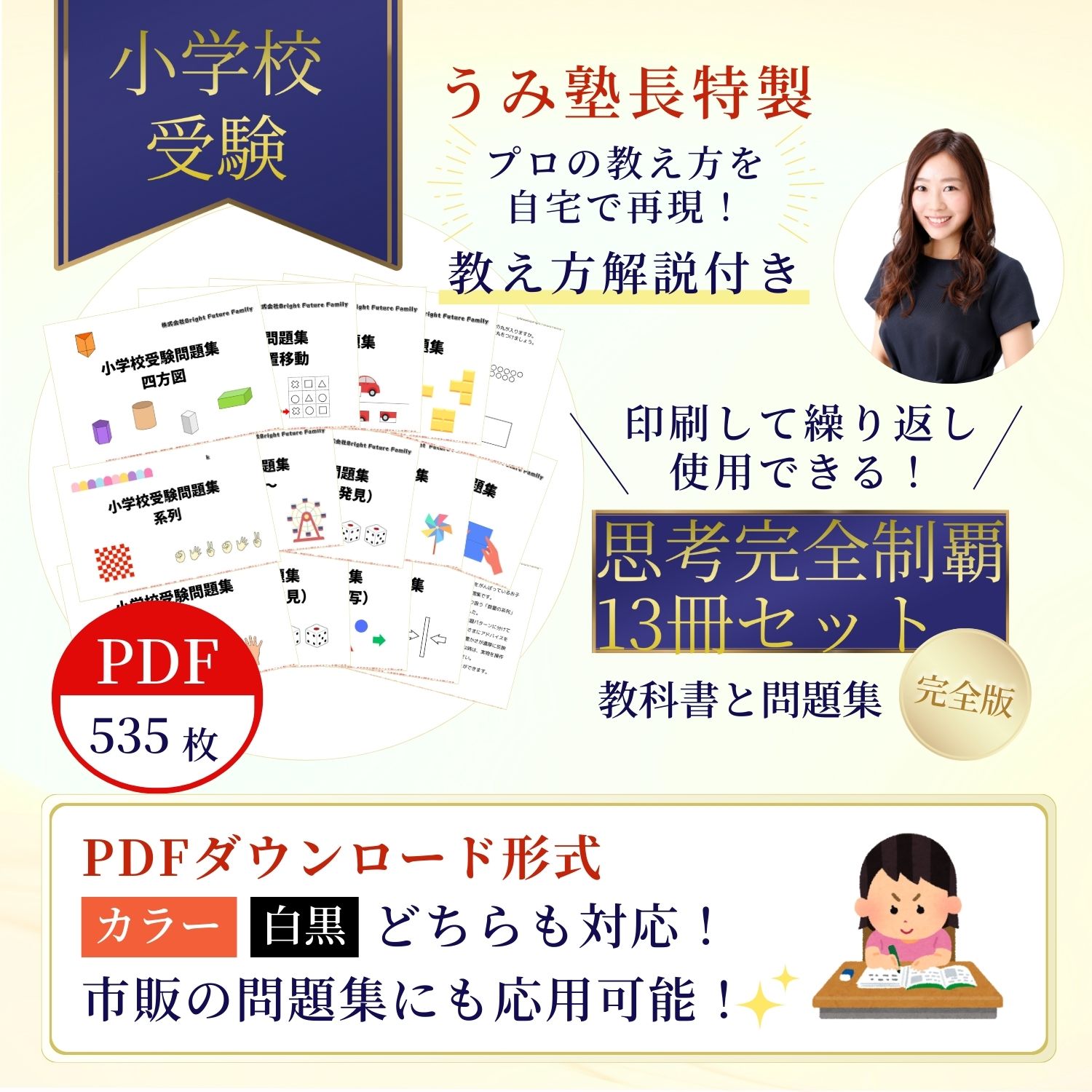
【小学校受験】四方図|まとめ
「四方図」は、空間認識力の高さに大きく左右されるため、得意と不得意が分かれやすい問題です。苦手なお子さまは解法のテクニックを身につけて少しでも問題を解けるように、得意なお子さまは確実に得点できるように問題練習に励んでいただけたらと思います。ぜひ本記事でご紹介した教材をご活用いただき、効率よく学習をしてください。
1.jpg)