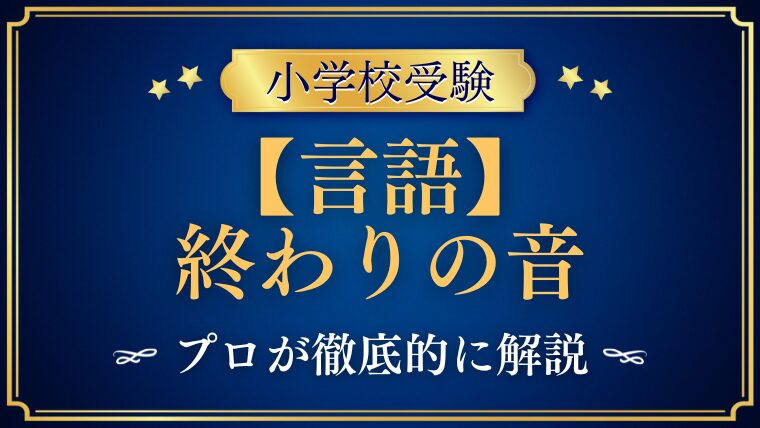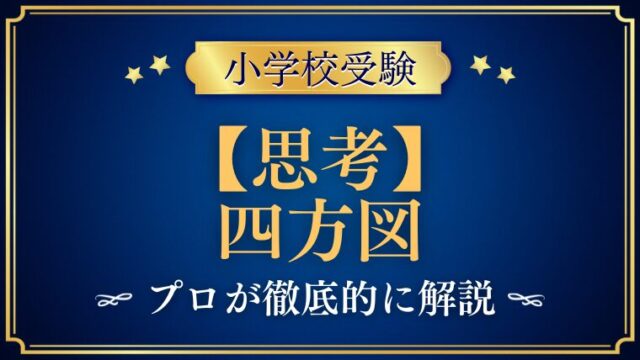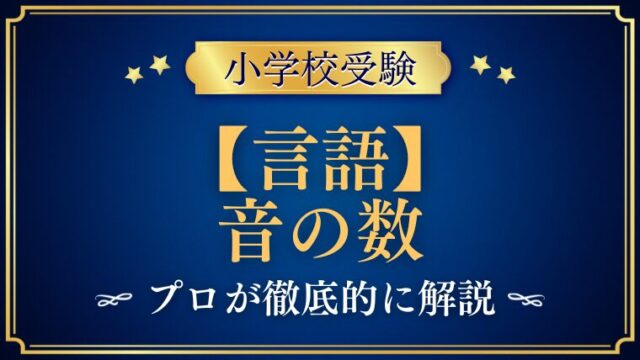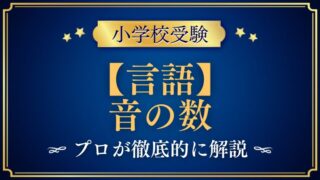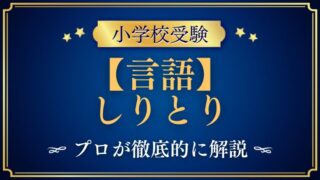【小学校受験】終わりの音の出題意図は?
「終わりの音」の問題では、音声認識や言葉の理解など、言語に関する基礎的な能力が備わっているかが見られています。
音声認識力があるか
日本語の音声を正しく認識できるかが評価されています。例えば、「き」と「ち」、「ら」と「だ」、「れ」と「で」など、特定のひらがなを聞き分けるのが難しいお子さまがいらっしゃいます。聴力に問題がないのに特定の音が聞き分けにくいという症状があれば、専門的なサポートが必要になる場合もあります。
言語力があるか
特に、言葉を音声に分けて理解することができるかを見られています。例えば、「団子」という言葉を「だ・ん・ご」の3つの音に区別して理解できることが重要になります。撥音(はねる音「ん」)、促音(つまる音「っ」)などを区別するのが難しいことがあります。
聞く力があるか
「終わりの音」の問題では、聞き取りによる出題もあります。この場合、正しく聞く力があるかも問われています。また、音声の認識ができるだけではなく、先生の話を1回で聞き取る集中力も必要です。
【小学校受験】終わりの音の出題方法は?
「終わりの音」は、主にペーパーテストにおいて出題されます。ペーパーテストによる出題では、筆記による出題方法と口頭による出題方法があります。
ペーパーテスト(筆記)
お手本で示されたイラストや写真を見て、同じ音で始まるものを答えるタイプの問題です。筆記による出題では、イラストや写真を見てそのものの名前がわかる語彙力が必要です。その上で、音を正しく判断し、選択できるようにしましょう。
ペーパーテスト(口頭)
先生が読み上げた言葉と同じ音で始まるイラスト・写真を答えるのが一般的な出題方法です。例えば、「『きりん』と同じ音で始まる絵に丸をつけましょう」という出題方法や、「『き』で始まる言葉に丸をつけましょう」などの出題方法があります。口頭による出題方法では、言葉を正しく聞き取ることが大切です。先生が言った音声を1回で聞き取れるようにしましょう。
【小学校受験】終わりの音の出題内容は?
「終わりの音」の出題内容はいくつかの種類がありますが、いずれも終わりの音を正しく判断することが大切な問題になっています。
同尾音・異尾音を答えるもの
同尾音(終わりの音が同じ)を答えたり、異尾音(終わりの音が異なる)を答えたりする問題です。「同じ音で終わる絵に丸をつけましょう」などの指示による問題が、同尾音を答える問題になります。例えば、「ねこ」がお手本で示されて、「らっこ」を選ぶような問題がこれに当たります。
同様に、「違う音で終わる絵にバツをつけましょう」などの指示による問題は、異頭音を答える問題になります。
特定の音を探すもの
複数のイラスト・写真の中から、特定の音のイラスト・写真を探す問題です。「『た』で終わる絵を全て選んで、丸をつけましょう。」などのように出題されます。
終わりの音を組み合わせるもの
いくつか示された言葉の終わりの音を組み合わせると、どのような言葉ができるかを答える問題です。例えば、「たい」「まないた」「たこ」の終わり音を組み合わせると、「たいこ」を作ることができます。
【小学校受験】終わりの音の解き方は?
終わりの音の問題を解けるようにするためには、「はじめの音」と同様に語彙力や言語力を高めることが重要になります。図鑑や絵本の読み聞かせをしたり、親子の会話を増やしたり、言葉遊びをしたりして、語彙力や言語力の向上を図ましょう。
その上で、終わりの音が解けるようにするために、いくつかのポイントを意識することが大切です。まず、終わりの音を意識するのが難しい場合は、アクセントを強めて発声する練習をしてみましょう。お子さまが問題を解いている様子を見ていると、「はじめの音」と「終わりの音」を混同してしまうお子さま多くいらっしゃいます。このような基本的な間違いをなくすためには、言葉の読み方を意識することが必要です。例えば、「うさぎ」の「ぎ」を強く発音することで、終わりの音を意識しやすくなります。初めのうちは声に出して練習して、次第に心の中で発声できるように練習していきましょう。
その他にも、終わりの音を確実に解けるようにするための方法をこちらの教材で解説しています。基礎的な問題を落とすようでは難関校への合格は難しいでしょう。ぜひこちらの問題集を活用して、終わりの音に関する問題を確実に解けるようにしてください。
【言語】終わりの音(教材サンプル)
【言語】3 終わりの音サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
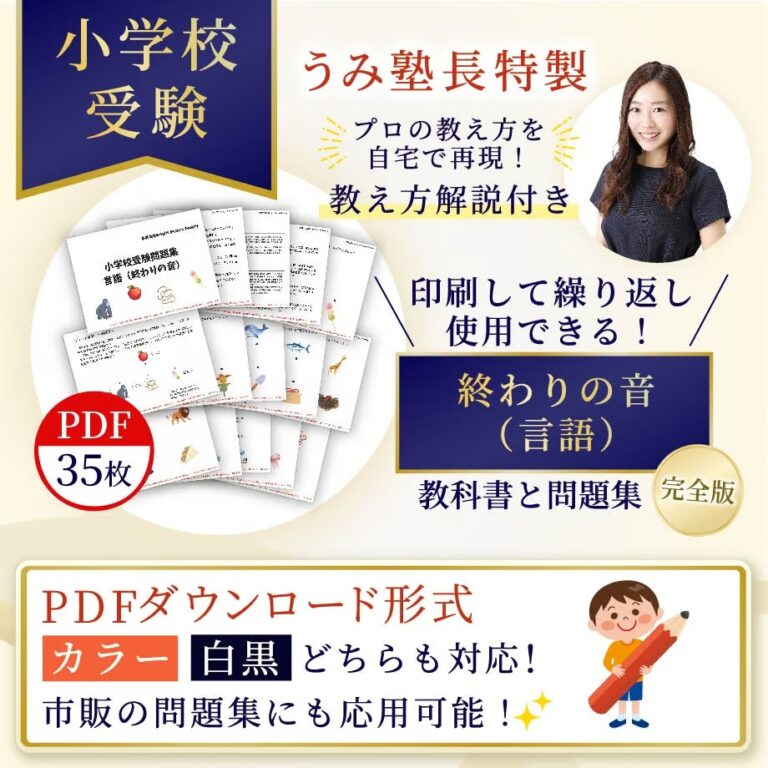
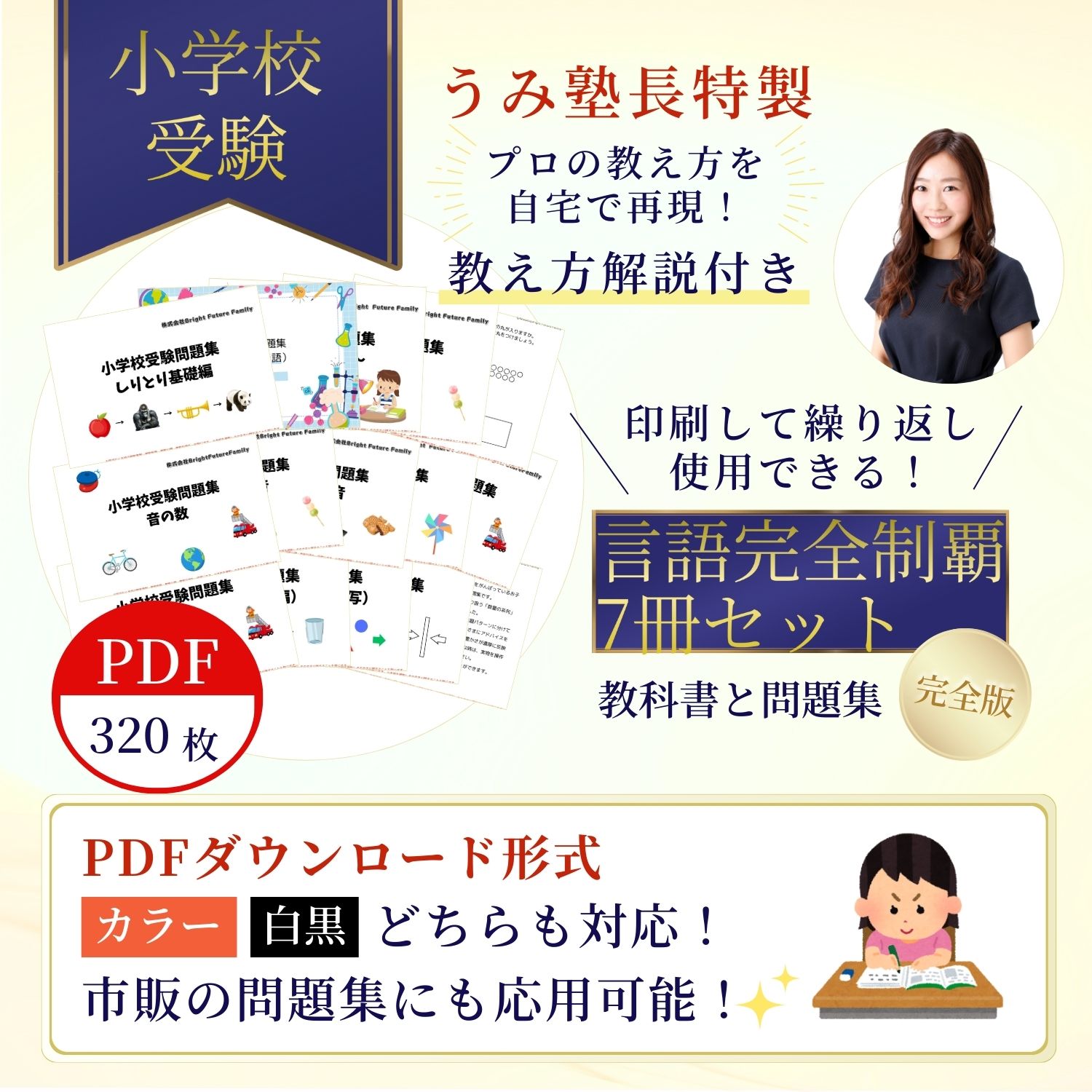
【小学校受験】終わりの音|まとめ
終わりの音の問題を解くためには、語彙力や言語力を向上させること、正しい解き方を身につけていることが大切です。解き方を身につけるためには、いろいろな問題を解くことも必要になります。ぜひ本記事でご紹介した教材をご活用いただき、語彙力や言語力を向上させつつ、効果的な解き方を学んでください。
1.jpg)