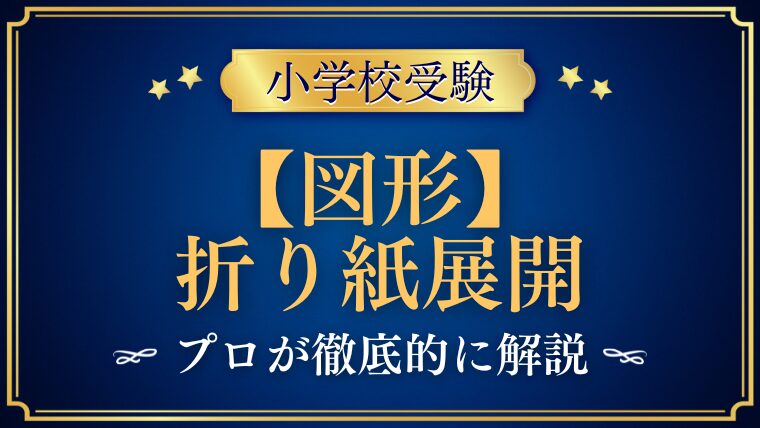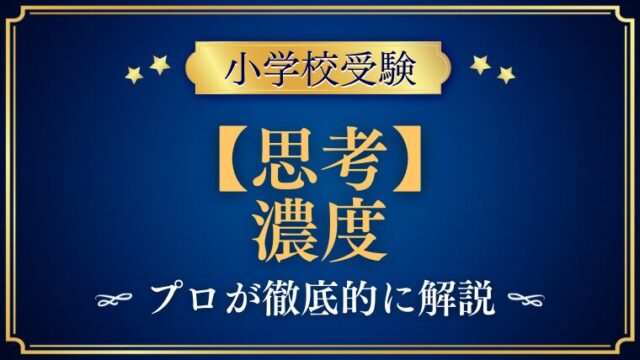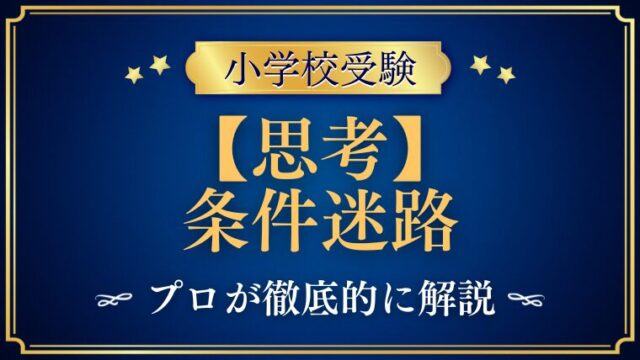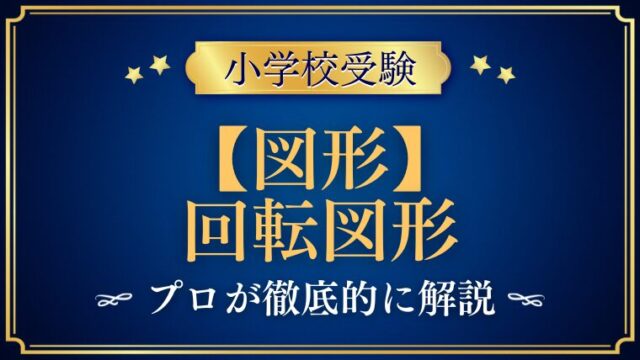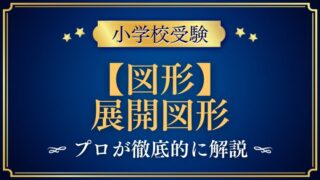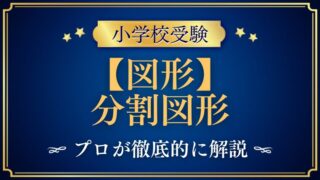【小学校受験】折り紙展開の出題意図は?
「折り紙展開」は、経験の豊かさ、空間認識力、思考力などが評価されています。
経験の豊かさがあるか
小学校受験で折り紙を扱った問題が多いのは、生活経験に即した課題だからです。実際に折り紙を折って切って開く活動を保育園・幼稚園やご家庭でしたことがあるお子さまなら、「折り紙展開」の問題も解きやすいでしょう。折り紙での制作活動は指先を使うので、脳の発達にもよいと言われています。普段の生活の中でも、実際に折り紙を使って様々な制作を行うのがおすすめです。
空間認識力があるか
「空間認識力」とは、ものの位置関係や形、向きなどを認知する力のことです。折り紙を展開した様子を頭の中でイメージするには、高い空間認識力と思考力が必要になります。空間認識力は、折り紙展開だけでなく、図形や推理、運動考査などの様々な場面で必要な力です。空間認識力を高めることは受験を有利に進める上で重要ですので、地道に鍛えるようにしましょう。
思考力があるか
「折り紙展開」の問題では、論理的に推理する力も大切です。例えば、「左側に丸が2つあるから、折り紙を広げた時に右側にも丸が2つあるはず」のように、論理的に推理しなければいけません。感覚的な理解も大切ですが、論理的に考える習慣をつけるようにしましょう。
【小学校受験】折り紙展開の出題方法は?
「折り紙展開」の問題は、基本的にペーパーテストで出題されます。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、折り紙を切ったイラストが示されて、開いたらどのような形になるかを答えさせる問題がほとんどです。解答方法は、択一問題になっていて、3つから5つの選択肢の中から選ぶことが多くなっています。
【小学校受験】折り紙展開の出題内容は?
「折り紙展開」の出題内容にはいくつかの種類がありますが、降り方で分類すると次のようになります。
四角折り
折り紙を長方形になるように半分に折ってから切る問題です。「四角折り」の問題では、左右に開くパターンで出題されることが多くなっています。左右に反転した形をイメージできるようにトレーニングをしましょう。
三角折り
折り紙を三角形になるように半分に折ってから切る問題です。「三角折り」の問題では、上下の向きや左右の向き、斜めの向きで出題されることがあります。「三角折り」の問題は、「四角折り」よりも難易度が高くなっています。
二度折り
「四角折り」または「三角折り」を2回してから切るパターンの問題です。1回折って切るよりも展開した所をイメージしにくいので、折り紙を実際に使ってイメージできるようにしましょう。解き方を身につけたり、繰り返し問題を解いたりして、しっかりと対策しておくことが望まれます。
【小学校受験】折り紙展開の解き方は?
「折り紙展開」の問題は、頭の中で折り紙を切ったり展開したりした形をイメージしないといけないため、空間認知力の高さが重要です。折り紙を展開した形がイメージできるように、折り紙を切って開く経験をたくさんさせてあげましょう。
また、空間認識力を鍛えるためには、「四方図」「鏡図形」「地図上の移動」など、他の空間認識力が必要な教材も並行してトレーニングするのがおすすめです。1つの問題に固執せず、お子さまの能力を総合的に伸ばしてあげる視点を持つようにしてください。
高い空間認識力や論理的な思考力が求められる「折り紙展開」ですが、たった1つのポイントを押さえておくだけでほとんどの問題を簡単に解くことができるようになります。この方法を使えば、展開した形をイメージしなくても解ける問題も多いため、「折り紙展開」が苦手なお子さまにはおすすめです。この問題の解き方については、こちらの教材で詳しく解説していますので、お子さまの学習にお役立てください。
【図形】折り紙展開(教材サンプル)
【図形】9 折り紙展開サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
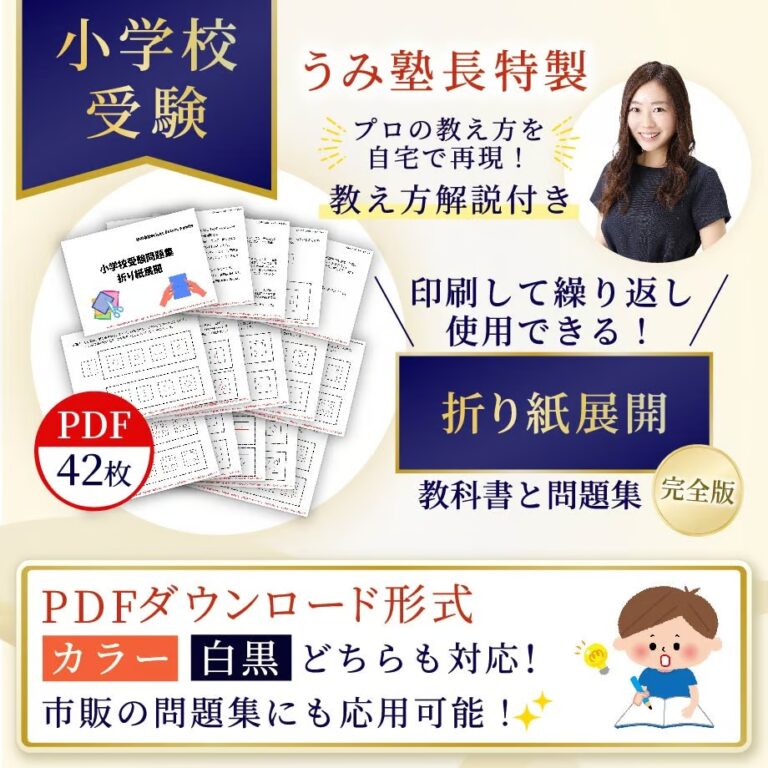
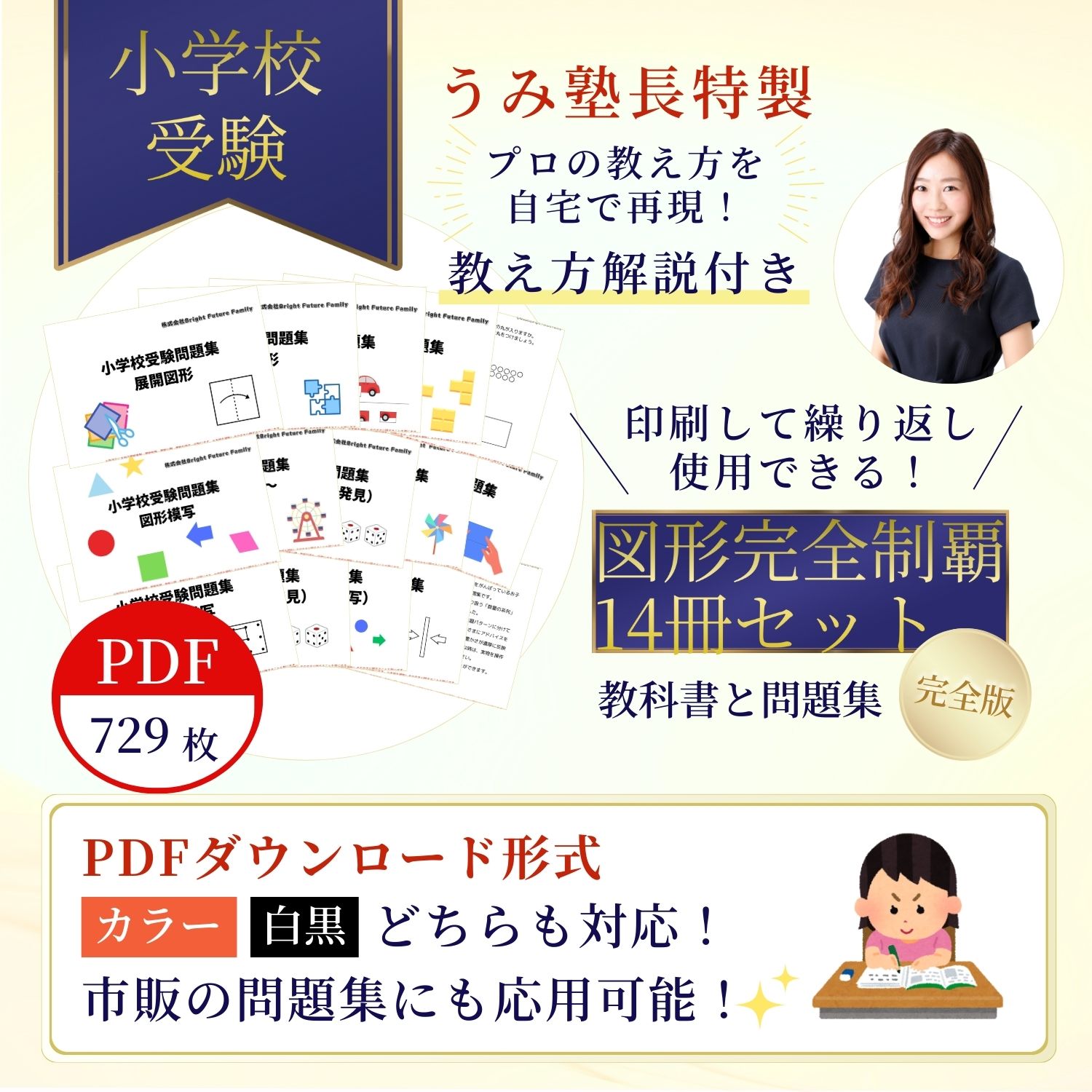
【小学校受験】折り紙展開|まとめ
「折り紙展開」は、高い空間認識力や論理的な思考力が必要な問題です。しかし、解き方のコツを押さえることで一気に解きやすくなる問題でもあります。ぜひ本記事でご紹介した教材をご活用いただき、効果的な学習をしていただけたらと思います。
1.jpg)