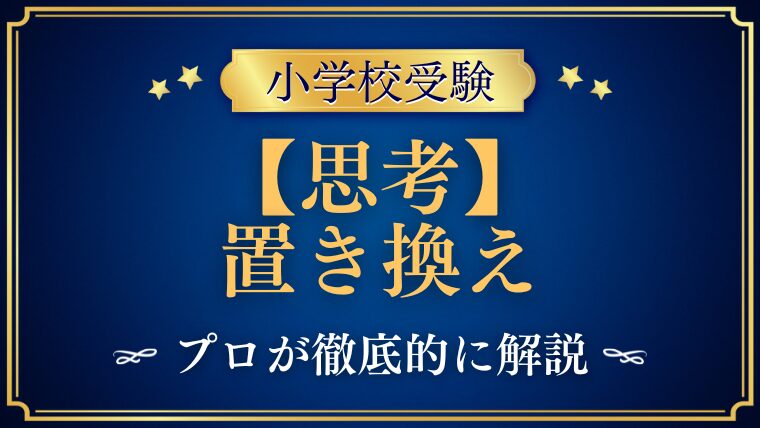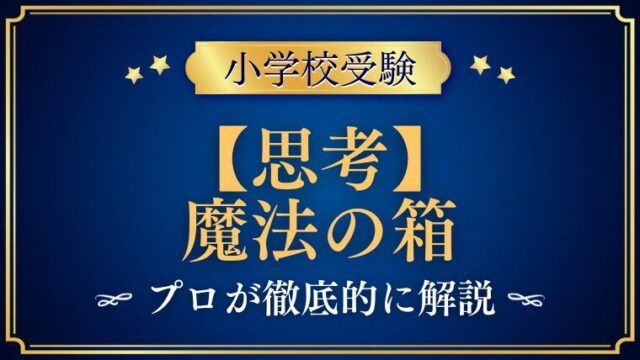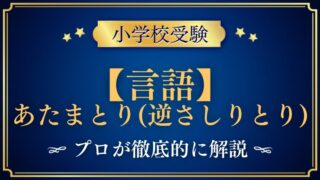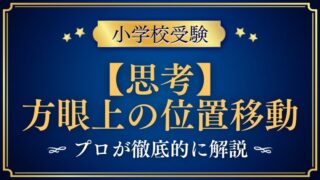【小学校受験】置き換えの出題意図は?
「置き換え」の問題は、思考領域の中でも基礎的な問題です。そのため、ルールの理解力、情報処理能力、集中力などの基本的な力が身についているかを評価されます。
ルールの理解力があるか
「置き換え」の問題の仕組みは、決して難しくありません。しかし、「りんご1つでみかん2つに、みかん1つでさくらんぼ3つに交換できます」のように、指示が複雑になると混乱してしまうお子さまもいらっしゃいます。ある程度問題に慣れていないと、問題が複雑になった時に置き換えのルールを理解できないという事態に陥ってしまうかもしれません。
情報処理能力があるか
「置き換え」の問題は単純に置き換えれば解ける問題ですが、その分作業スピードや正確性が問われます。情報処理能力が高いお子さまは、速く正確に問題を解くことができます。情報処理能力はワーキングメモリ(情報を一時的に保ちながら処理するための脳の働き)に左右されるので、ワーキングメモリを鍛えることも有効です。
集中力があるか
ワーキングメモリを働かせながら解答するためには、集中して問題を解く必要があります。集中力は、小学校受験ではもちろん、小学校入学後にも重要な力ですので、集中力を身につけるトレーニングも同時に行えるとよいです。
【小学校受験】置き換えの出題方法は?
「置き換え」の問題は、ペーパーテストで出題されるのが一般的です。
ペーパーテスト(筆記)
問題用紙の一部に置き換えの条件が示されていて、それを読み取って答えるタイプの問題です。置き換えの条件が1つだけのこともありますが、2つや3つ示されていることもあり、どの条件を使って問題を解くのかを判断する力も必要になります。
ペーパーテスト(口頭)
先生が置き換えの条件を読み上げて、その条件に従って置き換えるタイプの問題です。こちらの出題方法では、先生が言った条件を正しく記憶しなければいけないので、お話を集中して聞き、情報処理を適切に行えるようにしましょう。
【小学校受験】置き換えの出題内容は?
「置き換え」の問題の出題内容には、主に次の3つの種類があります。
1対1の置き換え
例えば、方眼上に記号や色付きの丸が描かれていて、「⚪︎→△」「赤丸→青丸」のように、1つの記号や色を別の記号や色に置き換える問題です。出題内容自体は簡単ですので、作業スピードや正確性が重要になります。記号を描く問題では記号を正しく速く描けること、色を塗る問題では色を丁寧に素早くぬれることが大切です。
1対複数の置き換え
例えば、「スイカ1個とメロン2個を交換できる」という条件で、スイカが2個の時にメロン何個と交換できるかを求めるような問題です。記号で出題されるときは、「⚪︎→△△」のような条件が描かれていて、丸や三角の記号を描くこともあります。1対複数の置き換えでは、「⚪︎→△△|⚪︎→◻︎◻︎◻︎」のような条件の時、△を◻︎に置き換えるような複雑な条件の問題も出題されます。
複数対複数の置き換え
例えば、「スイカ2個とメロン3個を交換できる」という条件で、スイカが4個の時にメロン何個と交換できるかを求めるような問題です。記号で出題されるときは、「⚪︎⚪︎→△△△」のような条件が描かれていて、丸や三角の記号を描くこともあります。
複数対複数の置き換えでは、「⚪︎⚪︎→△△△|⚪︎⚪︎→◻︎」のような条件の時、△を◻︎に置き換えるような複雑な条件の問題も出題されます。また「⚪︎=△△=◻︎◻︎◻︎」のように、3つの条件が組み合わさった問題もあります。
【小学校受験】置き換えの解き方は?
「置き換え」の問題では、条件に示された数を置き換えていくことで、答えにたどり着くことができます。地道に作業していけば、必ず答えにたどり着けるのですが、「置き換え」が苦手なお子さまはいきなり答えを求めようとして躓いてしまうことがあります。また、問題の難易度が上がると、何をどのように置き換えればいいかがわからなくなってしまうお子さまもいます。
「置き換え」を解く時は、条件に合わせて置き換えていくことが大切です。例えば、りんごとみかんを置き換えるような問題では、頭の中で(慣れないうちは声に出して)「りんご1個でみかん2個」と唱えながら、りんごを斜線で消してみかんと置き換えていきましょう。
「置き換え」の問題は、比(わり算)の考え方を使うような問題も出てきます。このような問題が解けるようになれば、「置き換え」の問題はほとんど解けるようになります。
複雑な条件の時の具体的な解き方はこちらの問題集で解説しています。繰り返し練習すれば必ず解き方が身につけられますので、しっかりと解き方を身につけて確実に答えを求められるようにしましょう。
【思考】置き換え(教材サンプル)
【思考】1 置き換えサンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
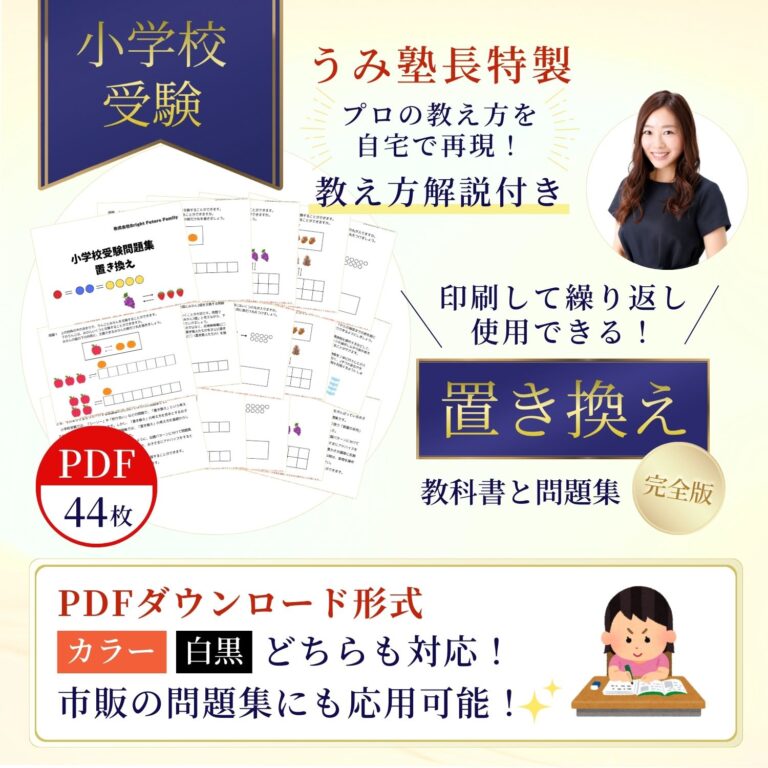
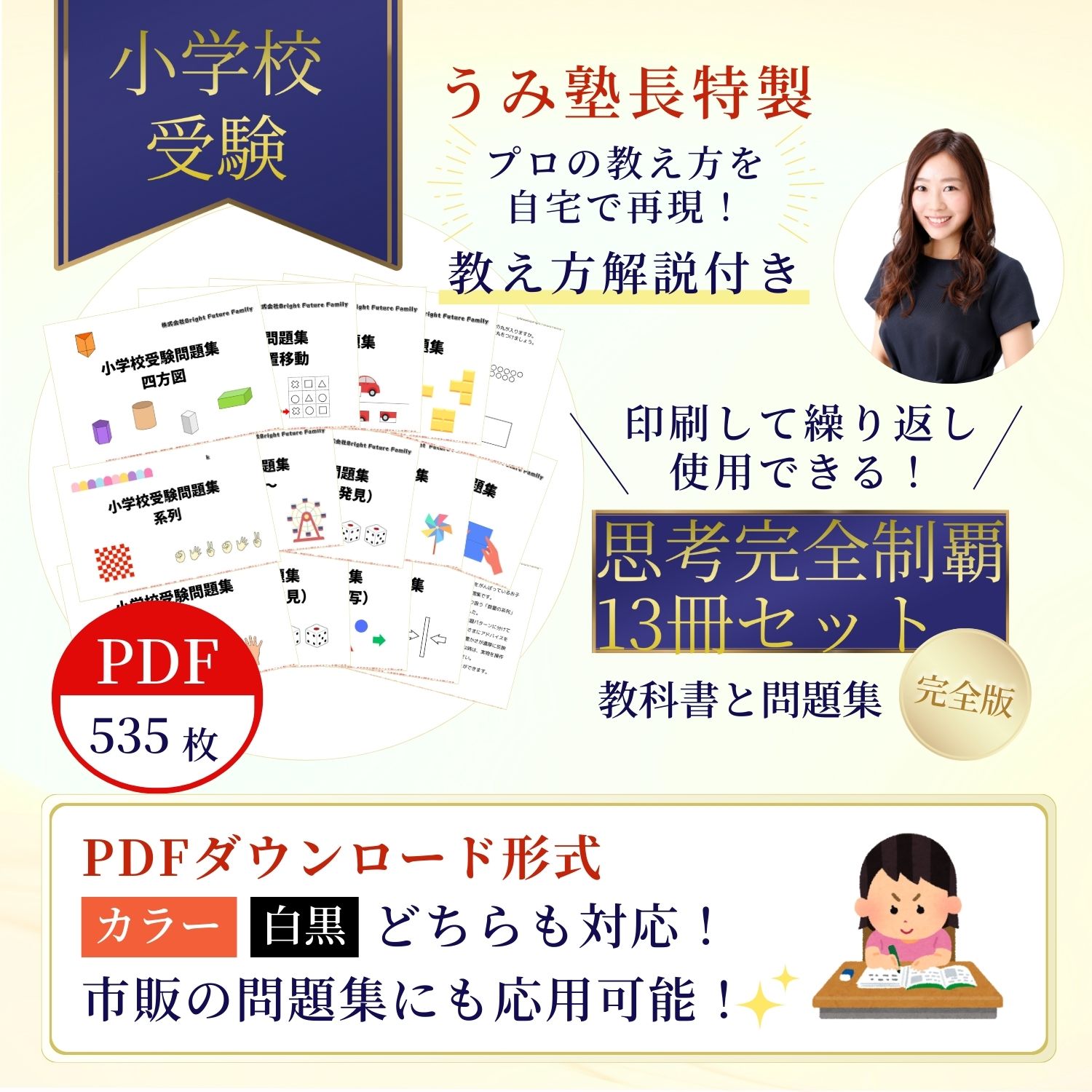
【小学校受験】置き換え|まとめ
「置き換え」の問題は、小学校受験の基礎的な問題でありながら、条件が複雑になると解けなくなってしまうお子さまも多くいらっしゃいます。また、「置き換え」は、「シーソー」や「釣り合い」の問題にも応用できる大切な考え方です。「置き換え」の考え方が苦手なお子さまは、しっかりと「置き換え」の考え方を身につけられるように基礎から丁寧に学習しましょう。また、得意なお子さまは難易度の高い問題も確実に得点できるようにしてください。ぜひ本記事でご紹介した教材をご活用いただき、「置き換え」の対策をしていただけたらと思います。
1.jpg)