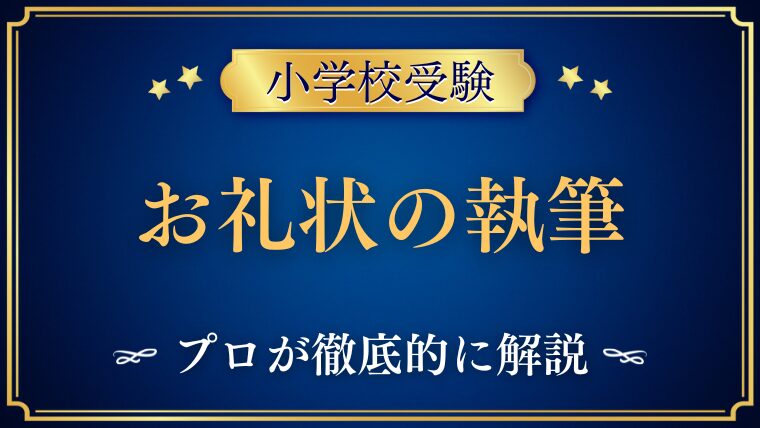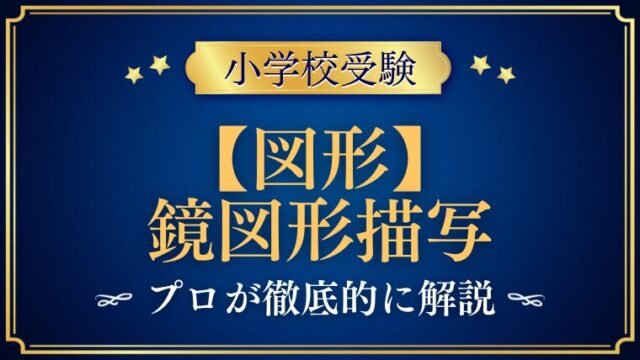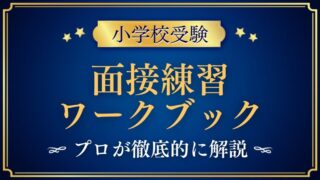【小学校受験】お礼状は必要?出すメリットは?
お礼状は基本的に出しても問題ありません。また、余程のことがない限り出してマイナスとなることはありえませんのでご安心ください。そのため、お礼状は受験の絶対条件ではありませんが、出すに越したことはありません。
メリット① 考査本番前にご家庭の意志を伝えることができる
お礼状は感謝の気持ちを伝えるものですが、受験や入学への意志を伝えるツールとしての役割もあります。例えば、「校長先生のお話に感動した」という親御様の多くは、そのご家庭の教育方針やお子さまの成長を思い浮かべて感動するのだと思います。つまり、学校の教育方針(校長先生のお話)とご家庭の教育方針(親御様の感動)が一致しているというわけです。もしお礼状を上手に活用すれば、出願前に入学への意志を示すことができます。
メリット② 学校側に好印象を残せる
正しい書き方で書かれたお礼状は、学校の先生に好印象を残すことができます。もし先生が好印象を持っている状態で面接をスタートすることができたらどんなに有利でしょうか。お礼状を受け取る機会が少ない学校であれば、なおのことその印象は強まります。
メリット③ 面接時の話題に繋がる
お礼状が面接の話題に上がることもあります。もし面接でお礼状について話題になれば、学校も好印象を抱いているということですし、親御様のお気持ちが学校に伝わっているということでもあります。その上で面接で上手に受け応えができれば、面接の評価はよいものとなります。
【小学校受験】お礼状を書く前にやるべきこと
学校に好印象なお礼状を書く上では、事前の準備が大切です。お礼状を書く前にやるべきことはいくつかありますが、本記事ではその中の2つをご紹介します。
学校研究
志望校の校風や方針をきちんと理解していなければ、学校の先生の心に残るようなお礼状は書けません。そのために必要なのが学校研究(志望校について深く知ること)です。学校HP、パンフレット、説明会、イベント、見学会など、学校研究ができる機会はたくさんあります。
また、よいお礼状が書けることは、よい願書を書くことにも繋がります。そのためにも、しっかりと学校研究をしなければなりません。
印象に残ったシーンやエピソードの整理
学校説明会や見学会では、学校の先生からお話を伺う機会があります。お話を聞くことで、学校の教育で大切にしていることなどを具体的に知ることができます。また、在校生のリアルな現状から、「こんなご家庭やお子さまに入学してほしい」 という学校側の思いを受け取れることもあります。このような貴重な機会では、どの先生がどのようなお話をしていたかをメモして、心に残ったことを整理しておくようにしてください。
【小学校受験】お礼状の書き方
お礼状を書く場合、常識の範囲内の文章量が推奨されます。具体的に言うと便せん2〜3枚が基本とお考えください。文字の大きさなどにもよりますが、意外と書ける文量は少ないです。そのため、次の構成に従って、簡潔に記入しましょう。
構成① 時候の挨拶
謹啓(拝啓)から始まる季節を取り入れたご挨拶です。季節を表す言葉が入りますので、その時期に合う表現を使うように気をつけましょう。挨拶状やお礼状には欠かせない要素だからこそ、間違った表現を使うことは避けなければなりません。
構成② 主催者、および開催へのお礼の言葉
まずは、お礼の言葉を記載します。 「先日の学校説明会では、先生方と直接お話させていただける貴重な機会をご用意いただき誠にありがとうございました。 」という内容で十分です。忙しい合間を縫って学校説明会やイベント見学を開催してくださる先生に、感謝の気持ちが素直に伝わるようにしましょう。
構成③〜
構成③以降は、「これ1冊でスラスラ書けるようになる! 学校説明会、イベント見学 お礼状執筆マニュアル」にて解説しています。また、こちらのマニュアルではお礼状の記入例を掲載していますので、内容を少しアレンジするだけできちんとしたお礼状を書くことができるようになっています。さらに、お礼状を書くデメリットやお礼状を書く時に絶対にしてはいけないことなども解説していますので、安心してお礼状を書いていただけます。
【これ1冊でスラスラ書けるようになる! 学校説明会、イベント見学 お礼状執筆マニュアル】(サンプル)
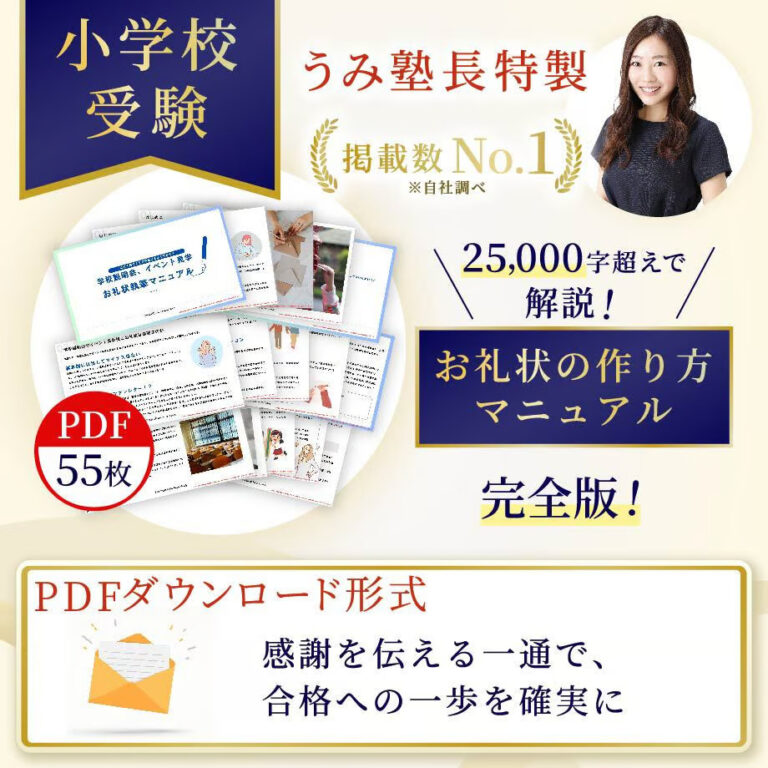
【小学校受験】お礼状の執筆|まとめ
「これ1冊でスラスラ書けるようになる! 学校説明会、イベント見学 お礼状執筆マニュアル」を活用することで、学校に好印象を持っていただけるお礼状を書くことができます。「お礼状ってどうやって書いたらいいの?」「お礼状を出すべきかわからない。」という方は、ぜひこのマニュアルをご一読いただき、きちんとしたマナーを守ってお礼状を書いていただけたらと思います。
1.jpg)