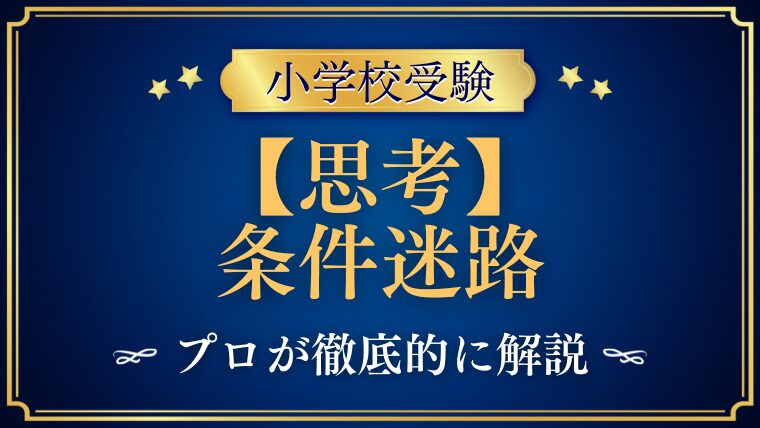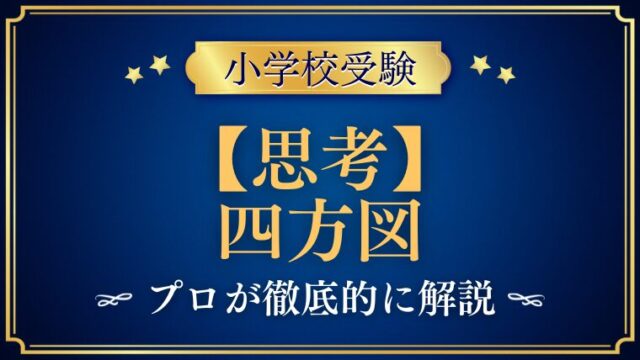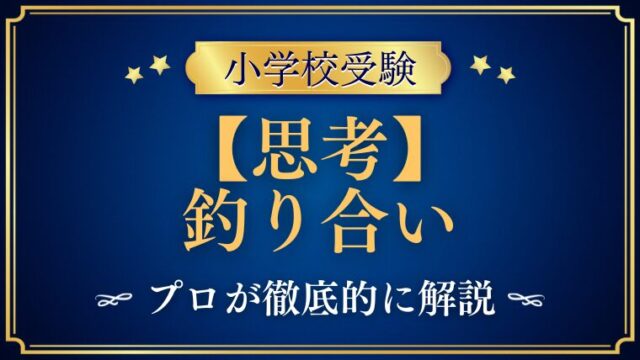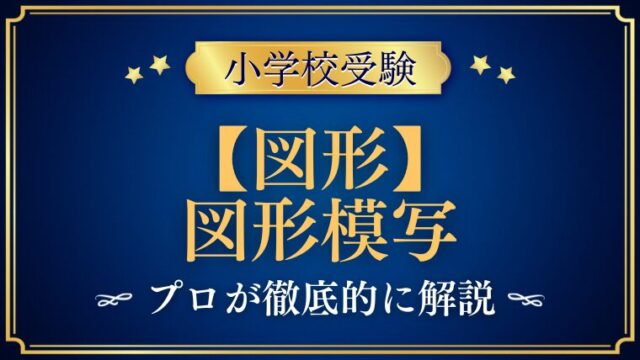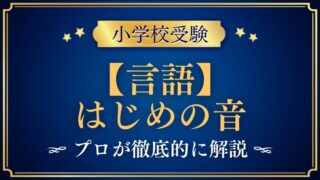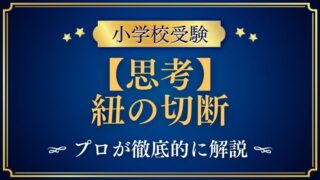【小学校受験】条件迷路の出題意図は?
「条件迷路」は、他の領域の問題と関連して出題されることも多く、幅広い思考力が求められます。
情報処理能力があるか
迷路を進む際に、「条件に合っているか」を考えながらゴールを目指さなくてはいけません。どの道を進めば条件から外れずに進めるのか、適切に情報を処理して判断する能力が必要です。
論理的思考力があるか
例えば、一筆書き迷路では、「この道を通ったら同じ道を通ってしまうからダメ」、しりとり迷路では、「この道の言葉は『ん』がつくからダメ」というように、論理的に考えることが必要です。論理的に思考することで、素早く正解の道を見つけてゴールにたどり着くことができます。
忍耐力があるか
「迷路」の問題は、間違った道に進んでも諦めず、試行錯誤しながら問題を解く必要があります。「条件迷路」の問題も同様に、試行錯誤しながら迷路を進む忍耐力が求められます。迷路自体は簡単なことが多いので、地道に迷路を進んでいきましょう。
集中力があるか
「条件迷路」では、試行錯誤を必要とする迷路があったり、間違いに誘導するような迷路があったりします。集中して問題を解かないと、間違いに気づいて進む道を修正したり、先を見通して道を選択したりすることができません。
学習の基礎が身についているか
「条件迷路」の問題は、他の領域と関連させて出題されることがあります。それぞれの難易度は低いものの、数・常識・言語・右左などの学習の基礎が身についていないと問題を解くことができません。そのため、幅広い対策をしておくことが求められます。
【小学校受験】条件迷路の出題方法は?
「条件迷路」は、基本的にペーパーテストで出題されます。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、先生が迷路を進む条件を説明してくれますので、しっかりとお話を聞いて言われた条件の通りに迷路を進みましょう。学校によっては、「例題」として先生と一緒に問題を解いてから自力で問題を解くこともあります。
【小学校受験】条件迷路の出題内容は?
「条件迷路」には、様々な出題パターンがあります。いろいろなパターンを知っておくことで問題に対応しやすくなりますので、ここに挙げた代表的な「条件迷路」はしっかりと解けるようにしておきましょう。
一筆書き
「同じ道は通らない」という条件がある迷路です。初めて一筆書きの問題を解くお子さまだと、「同じ道を通らない」という条件が理解しにくいことがあります。また、遠回りをしないとゴールにたどり着けないような迷路になっていることも多いので、ある程度問題に慣れておくことが大切です。
数
例えば、「りんごを10個拾う」など、数に関係する条件がある迷路です。数の合計を求める迷路では、基本的に「たし算(数え足し)」で迷路を進めることになります。ただ、「10個のりんごを持っていて、クマに会うたびりんごを1個あげる(ひき算)」や「一番りんごが多く拾えるように進む(数の比較)」などのパターンが出題されることもあります。いずれにしても、数は多くないため、数え足し、数え引き、数の比較などの基礎的な数の操作ができるようにしておく必要があります。
常識
例えば、「春の花をすべて通って」や「じゃんけんで勝つように」など、「常識」に関連した内容の迷路です。出題内容が多岐に渡るので、総合力が問われる問題です。ただ、「常識」に関する難易度はそれほど高くない傾向にあります。そのため、他の問題集を活用して総合力を上げ、確実に正解できるようにしたいところです。
言語
例えば、「しりとりの順になるように迷路を進みましょう」や「『た』で始まる物をすべて通ってゴールまで行きましょう」など、「言語」に関連した迷路です。「言語」に関する迷路も、迷路としての難易度は高くありませんので、確実に得点できるようにしましょう。
右左
例えば、「どんぐりを拾ったら右に曲がり、キノコを拾ったら左に曲がりましょう」など、曲がる条件が示された迷路です。この迷路は、別の教材「地図上の移動」で扱っていますので、ぜひそちらの問題集にもチャレンジしてみてください。
【小学校受験】条件迷路の解き方は?
「条件迷路」でポイントになるのは、見通しを持って取り組む力と遡って考える力です。
初めのうちは行き当たりばったりで迷路をしているお子さまがほとんどです。しかし、迷路に慣れてくると、分かれ道で「どちらが行き止まりか」を判断して正しい道を通れるようになってきます。この力は迷路に限らず、様々な分野で大切になる力です。
また、迷路で行き止まりになった時の思考法も重要です。行き止まりになった時は、「スタートから再開する」「分岐点まで遡る」という2つの方法が考えられます。基本的には、分岐点に遡った方が早くゴールすることができます。ただ、条件迷路で遡って考えると間違えやすくなることもあるので、問題に応じて解きやすい方法を選択できるのが理想と言えます。
その他にも、各問題の種類に応じて適切な解き方をする必要があります。こちらの教材では、「一筆書き迷路」「順番迷路」「計算迷路」「常識迷路」「言葉迷路」の問題を扱っており、それぞれの解き方も解説しています。条件迷路は高い思考力と総合力を身につけるのに適した教材ですので、ライバルと差をつけたい方はぜひ取り組んでみてください。
【思考】条件迷路(教材サンプル)
【思考】9 条件迷路サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
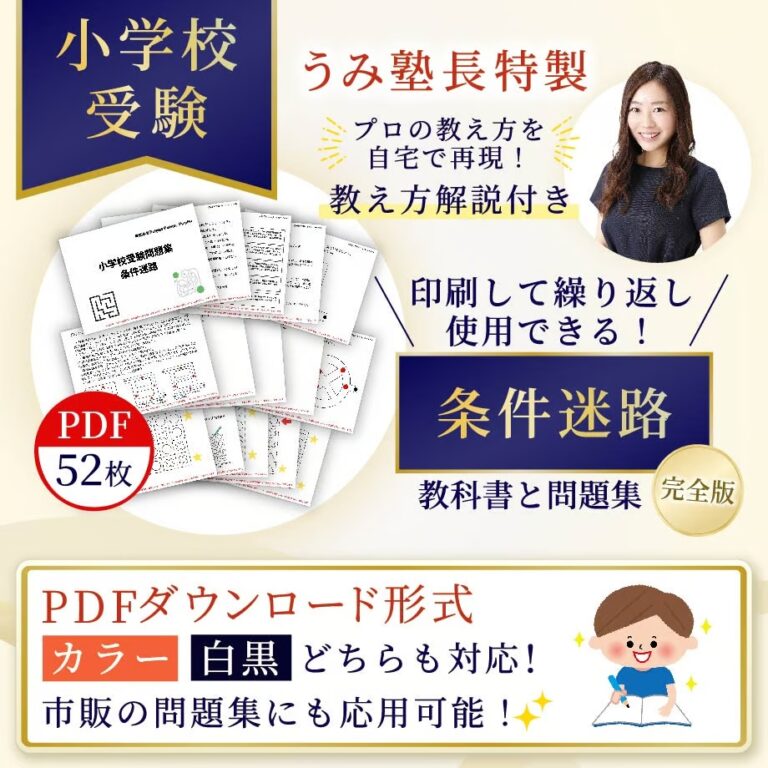
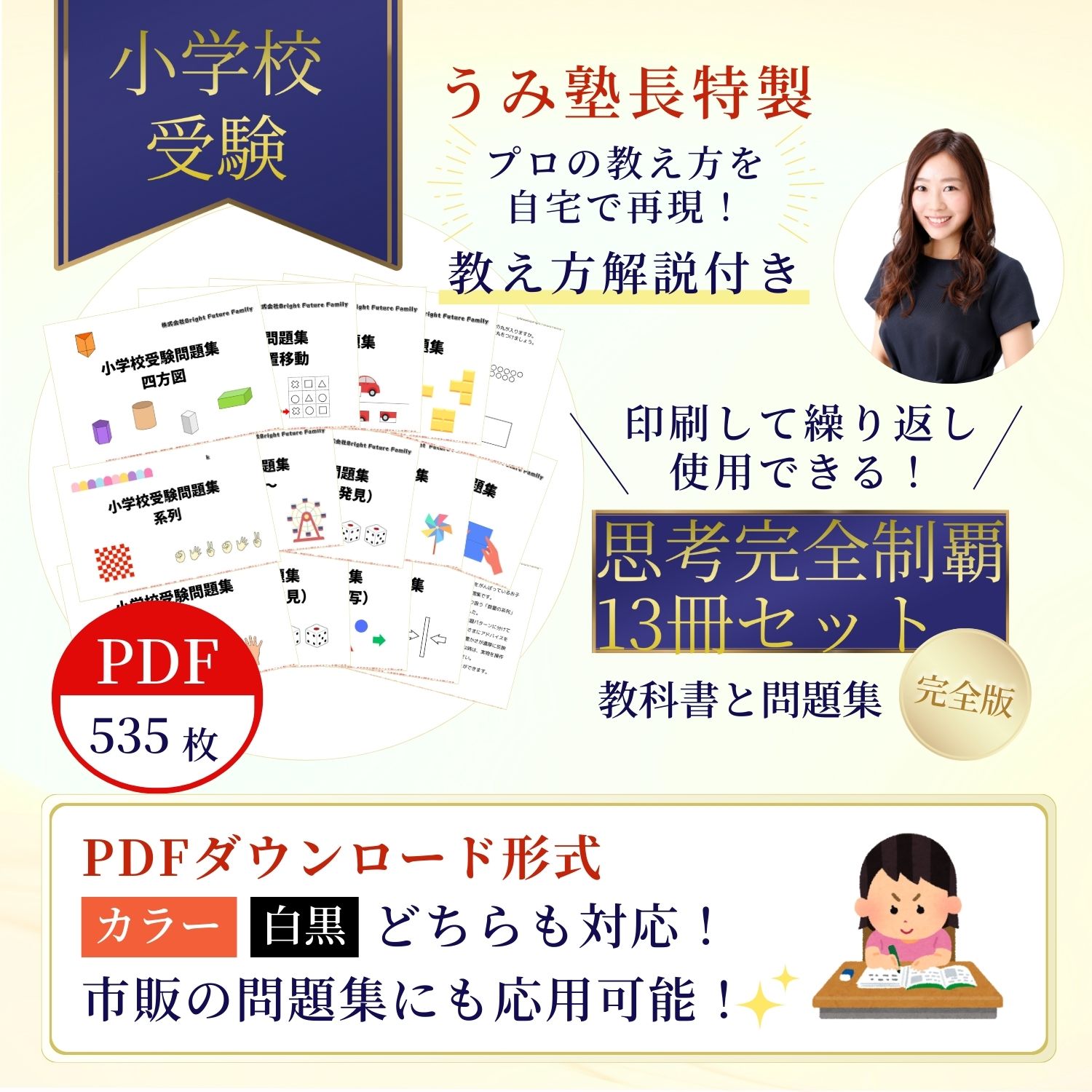
【小学校受験】条件迷路|まとめ
「条件迷路」は、高い思考力と総合力が試される問題です。初見では問題を理解するのが難しいお子さまもいらっしゃる問題ですので、事前にしっかりと対策しておきましょう。ぜひ本記事でご紹介した教材をご活用いただき、「条件迷路」を解くために必要な幅広い力を強化していただけたらと思います。
1.jpg)