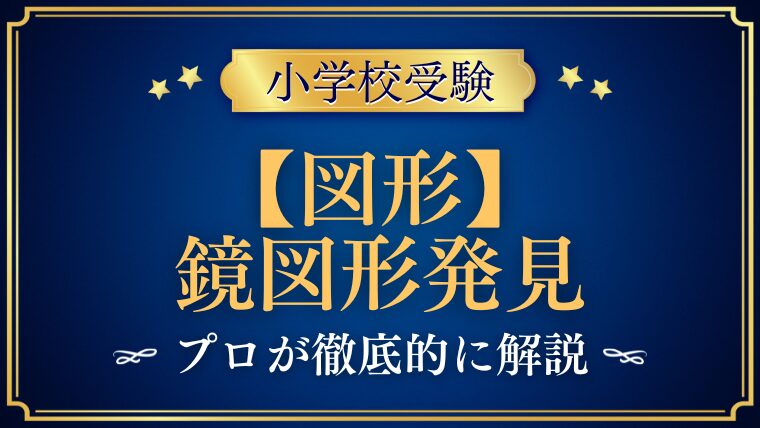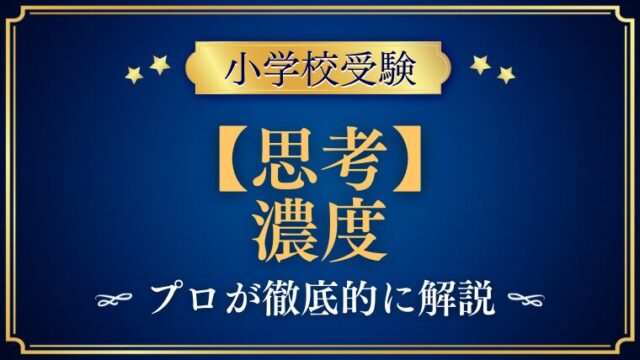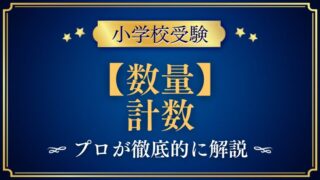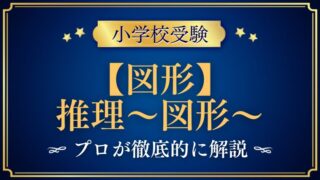【小学校受験】鏡図形発見の出題意図は?
「鏡図形発見」の出題意図では、空間認識力があるか、観察力があるか、論理的思考力があるかなどが評価されています。
空間認識力があるか
鏡に映った形の上下・左右を正しくイメージするためには、空間認識力が必要です。特に、「鏡図形発見」の問題では、鏡を見る位置により正解の形が変わるため、高度な空間認識力が必要になります。
観察力があるか
「鏡図形発見」では、形をよく観察して正解かどうかを判断しなければいけません。一見同じように見える形でも、よく見ると間違った選択肢になっていることがあります。選択肢を見比べて、どこがどう違うのかを見極めるようにしましょう。
論理的思考力・推理力があるか
「鏡図形発見」の問題を解くためには、鏡に形がどのように映るかを理解している必要があります。その上で、鏡に映った形の対称性や規則性などについて論理的に正誤を判断できる思考力や推理力が大切になります。
集中力があるか
「鏡図形発見」の問題では、「同図形発見」や「異図形発見」と複合的に出題されることがあります。このような出題の場合、細かい違いを見つけて正解の形を見分ける集中力も大切です。似ている形がたくさんあっても、忍耐強く取り組むようにしましょう。
【小学校受験】鏡図形発見の出題方法は?
「鏡図形発見」の出題方法では、ペーパーテストが一般的です。ただ、ペーパーテストのない小学校では、個別テスト・口頭試問で鏡図形の問題が出されることもあります。
個別テスト・口頭試問
個別テスト・口頭試問による出題では、「この形を鏡に映すとどのように映りますか。」「この形を鏡に映した時に見える形の絵を選んでください。」などと問われることがあります。このパターンの出題方法はあまり多くありませんが、ペーパーテストの対策をしていれば口頭試問にも十分対応することができます。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、お手本の絵と鏡が描かれていて、「この形を鏡に映すと、鏡の中の形はどのように見えますか。」のように質問されるのが一般的です。3つから5つ程度の選択肢の中から選ぶ問題がほとんどですが、「同図形発見」や「異図形発見」と複合的に出題される場合は、複数の絵がランダムに配置されていることもあります。
【小学校受験】鏡図形発見の出題内容は?
「鏡図形発見」の出題内容は、大きく分けて3パターンあります。
左右反転
ある形を鏡の横に置いた時に、鏡の中の形がどのように見えるかを問う問題で、「鏡図形発見」の基本的な問題です。左右が反転する問題では、上下は反転しないことに気をつけ ましょう。
上下反転
「鏡図形発見」の中には、鏡以外にも水(池・水たまり・湖など)に映った形を考えさせる問題もあります。上下反転の問題はこのパターンでの出題が多く、水面に映った形がどのように見えるかを問う問題が定番です。上下が反転する問題では、左右は反転しないことに気をつけましょう。
前後反転
鏡と正対した(向かい合った)時に映る形を答えるタイプの問題です。鏡と正対した時は、鏡の中の形は前後が反転します。前後反転の問題は、左右反転や上下反転に比べて出題頻度は低くなっています。
【小学校受験】鏡図形発見の解き方は?
「鏡図形発見」の問題が得意になるためには、感覚的な理解と論理的な理解の両面からアプローチしましょう。
感覚的な理解を促す上では、やはり鏡に色々なものを映してみることが大切です。この時、鏡を置く位置によって映り方が異なることを確認しましょう。文字や数字を映すといわゆる「鏡文字」になることや、反転する方向と反転しない方向があることなどを言語化しながら体験するのが効果的です。「鏡に映す」という体験を通して、反転する感覚を身につけられるようにしましょう。
論理的に考える場合は、「遠くは遠く、近くは近く」というポイントを意識しながら問題を解くのがポイントです。これは、「展開図形」の考え方とも共通しているので、「展開図形」と併せて対策するのが効率的でしょう。また、全体を見ても答えが分かりにくい時は、間違い探しのように部分的にパーツを見て正誤を判断するのがよいでしょう。「鏡図形発見」の具体的な解き方についてはこちらの教材で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
【図形】鏡図形発見(教材サンプル)
【図形】11 鏡図形発見サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
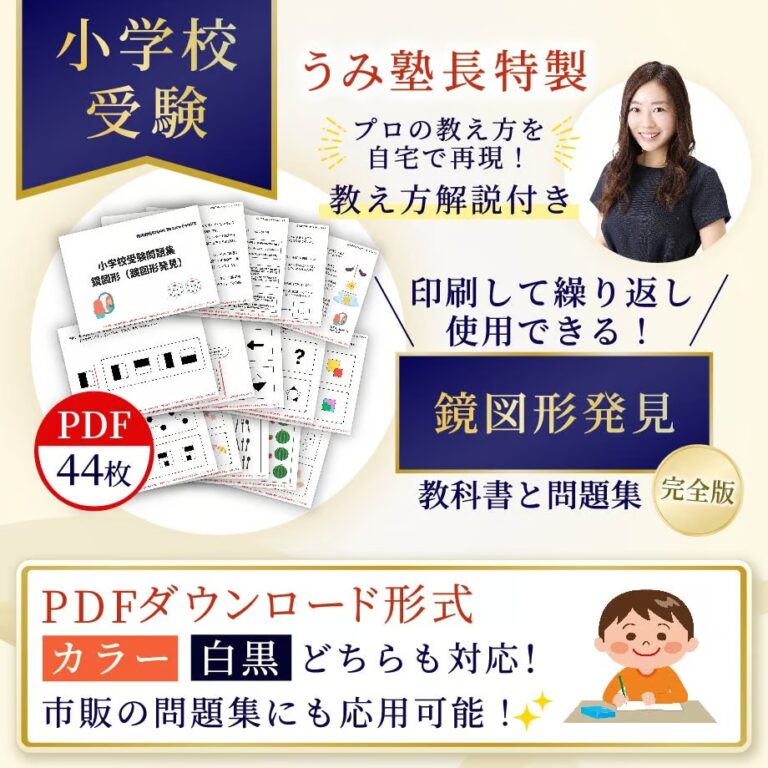
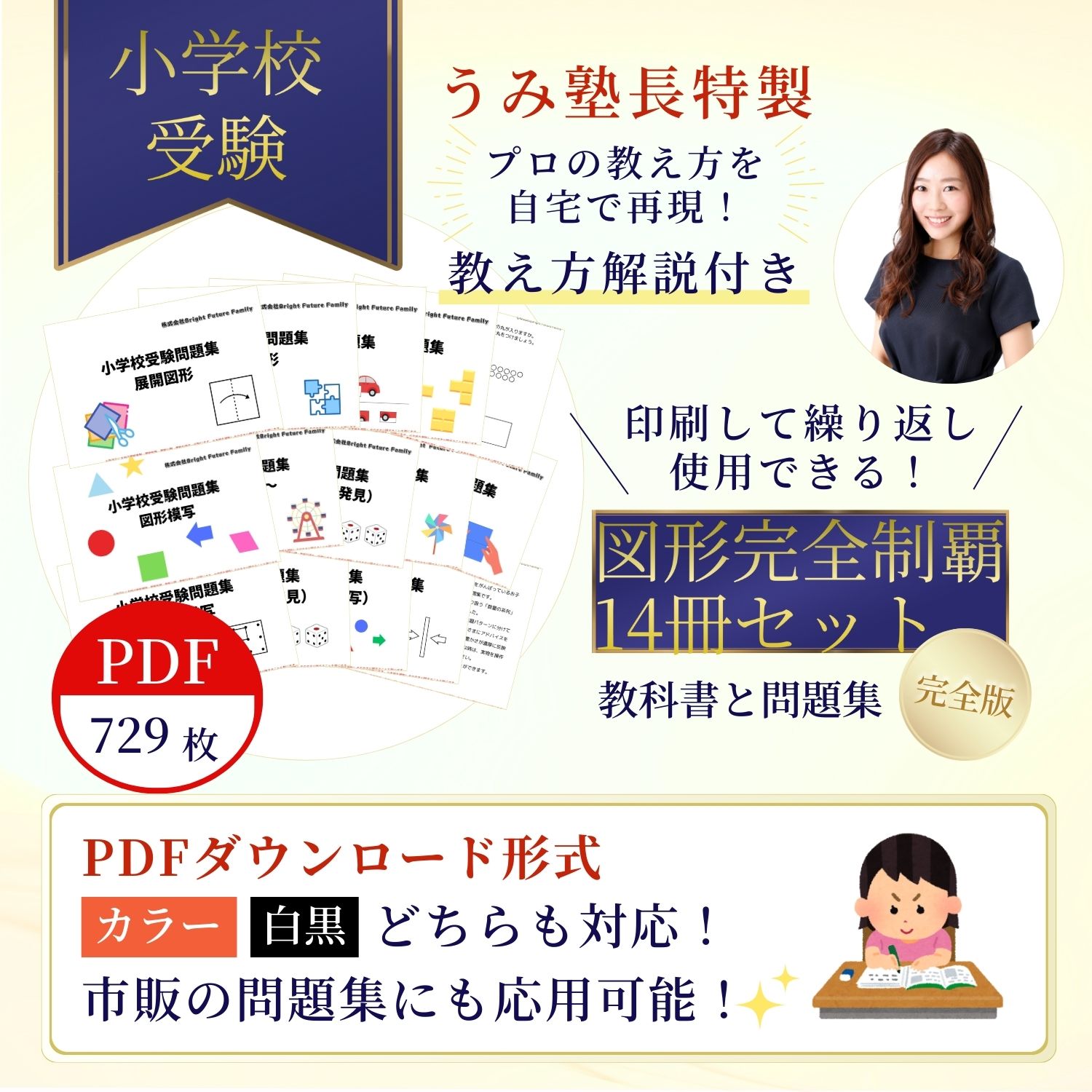
【小学校受験】鏡図形発見|まとめ
「鏡図形発見」は、鏡図形に関連する問題を解くための基礎となる問題です。出題内容には3つのパターンがあるため、それぞれしっかりと対策しておきましょう。また、他の問題と関連させながら論理的に解くことで、効率よく学習することができます。ぜひ本記事でご紹介した教材をご活用いただき、効率的に学習を進めてください。
1.jpg)