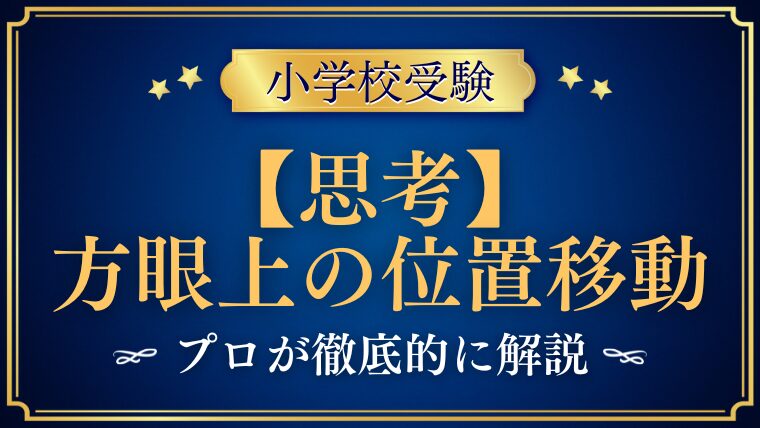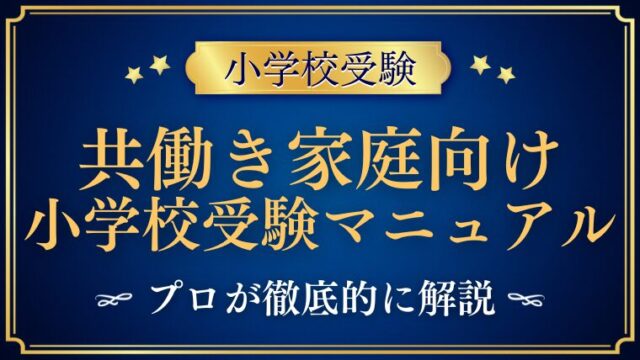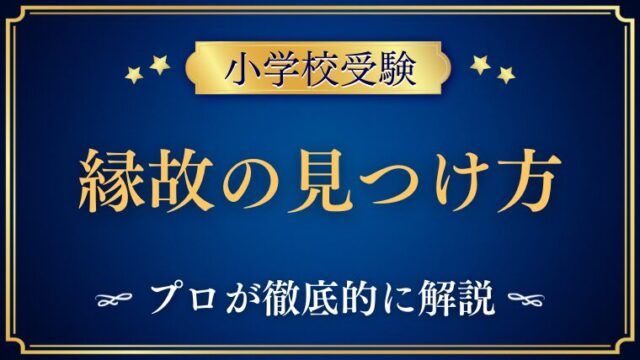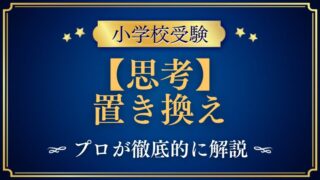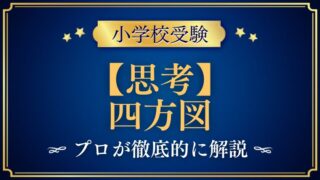【小学校受験】方眼上の位置移動の出題意図は?
「方眼上の位置移動」では、集中して聞く力や上下左右の方向感覚があるかどうかが評価されています。
集中して聞く力があるか
方眼上の位置移動では、聞き取りによる出題があります。先生の話を正しく聞き取り、適切に情報を処理していかないと正答を導くことができません。集中して話を聞くことは、保育園・幼稚園生活や家庭生活で育つ力です。そのため、集中して聞けるようになるためには、日頃の生活を見直すことも大切です。
方向感覚があるか
上下左右の方向感覚が身についていないと問題を解くことができません。例えば、聞き取りによる問題であれば左右を迷っているうちに指示を聞き漏らしてしまいますし、条件を読み取りながら移動するタイプの問題では回答スピードが遅くなって制限時間内に解けないこともあります。左右の判断が苦手なお子さまは、左右を即座に判断できるようになっておくことが重要です。
【小学校受験】方眼上の位置移動の出題方法は?
「方眼上の位置移動」は、主にペーパーテストで出題されます。ペーパーテストによる出題には、聞き取りによる出題と条件を読み取る問題の2種類があります。
ペーパーテスト(口頭)
先生の指示を聞いて移動した位置を答えるタイプの問題です。先生が出した指示のスピードについていけるように、上下左右をすぐに判断することが要求されます。
ペーパーテスト(筆記)
ペーパー上に示された条件に従って位置を移動するタイプの問題です。毎回条件を確認するのでは時
【小学校受験】方眼上の位置移動の出題内容は?
「方眼上の位置移動」は、「聞き取り」と「条件移動」の2つの出題内容に大別できます。
聞き取り
聞き取りの問題では、「右に2ます」「上に3ます」などの指示がある場合と、「カスタネットを叩いた回数だけ右に、タンバリンを叩いた回数だけ上に進んでください」のような指示がある場合があります。いずれの場合も、先生の話をしっかり聞くことが重要です。
条件移動
「◯では右に1ます」のように記号で条件が示されている場合と、「りんごでは上に2ます」のように物で条件が示されている場合があります。指定された条件に従って、上下左右を正しく判断しながら方眼上を移動しましょう。
【小学校受験】方眼上の位置移動の解き方は?
「方眼上の位置移動」の問題が解けるようになるためには、上下左右を正しく判断できること、指示を正しく聞き取ることが大切です。左右の判断が即座にできないお子さまは、「右左」の問題集から解いてみるのがおすすめです。また、聞き取りが苦手なお子さまは、「聞き取り」の問題集を活用して、聞き取りトレーニングをしてみてください。
「方眼上の位置移動」が正しくできるようになるためには、関数的(座標的)な見方を身につけることも効果的です。関数的(座標的)な見方を身につけるためには、「記号模写」に取り組んでみるのがよいでしょう。「記号模写」の問題では、自然と座標の考え方を身につけていくことができます。また、いろいろなパターンの出題方法に慣れておくことも大切ですので、本教材を活用して「方眼上の位置移動」の解き方を身につけましょう。
【思考】方眼上の位置移動(教材サンプル)
【思考】7 方眼上の位置移動サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
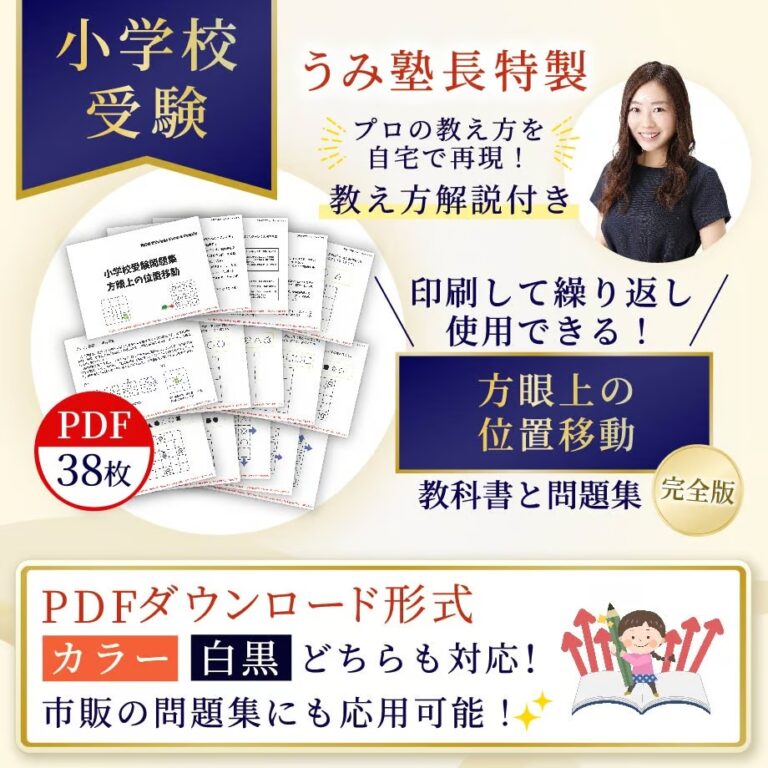
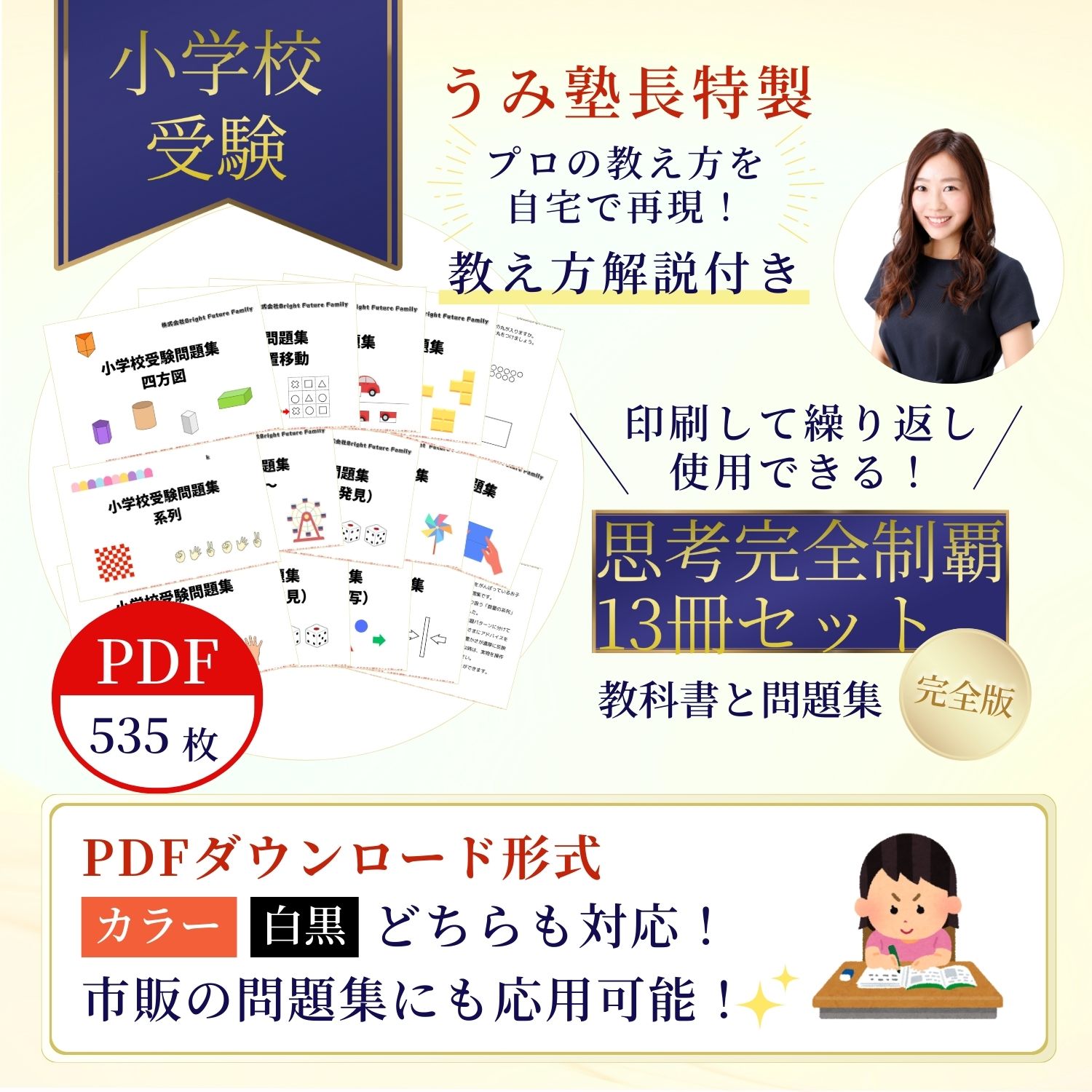
【小学校受験】方眼上の位置移動|まとめ
「方眼上の位置移動」を解くためには、集中して聞く力や上下左右の方向感覚が身についていることが大切です。また、関数的(座標的)な見方ができるようになると、問題が解きやすくなります。ぜひ本記事でご紹介した教材をご活用いただき、効果的な対策をしていただけたらと思います。
1.jpg)