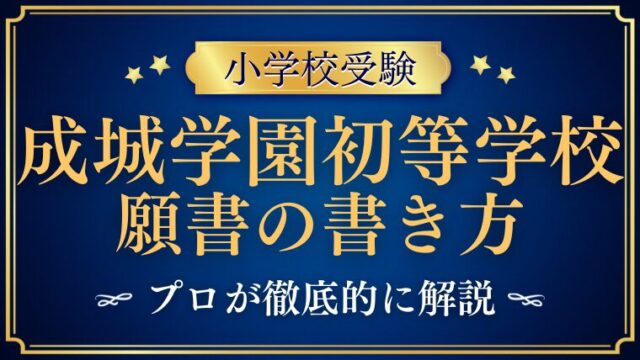慶應義塾幼稚舎は、福澤諭吉が創設した慶應義塾の精神をそのまま受け継ぐ初等教育機関です。
「独立自尊」という教育理念のもと、知識だけでなく豊かな感性や表現力、自主性を育てることに重きを置き、お子様たちの個性と向き合う丁寧な教育が行われています。そのため、学問的な評価のみならず、日々の生活に根ざした力や、心の成長も大切にされています。
そんな幼稚舎の入試では、いわゆるペーパーテストは実施されません。代わりに、「行動観察」「運動」「絵画・制作」といった実技を中心とした試験によって、その子がどのような思考や感性を持ち、どう行動するかが評価されます。
その中で例年話題に上がるのが「絵画・工作テスト」です。この試験では、表面的な技術ではなく、お子様の心の動きや、内面からあふれ出る発想力・表現力が問われる非常にユニークな試験です。本記事では、その特徴や家庭での対策までを詳しくご紹介していきます。
【慶應義塾幼稚舎】絵画・工作試験とは
慶應義塾幼稚舎の絵画・工作テストは、入学試験とは思えない程、その作り出される作品のレベルが大変高いことでも有名です。その一方、ただ完成された芸術作品を作れば良いというわけではないという点が、本試験の難しさを象徴しているとも言えます。
慶應義塾幼稚舎の絵画・工作テストでは、お子様たち一人ひとりがテーマに対してどう向き合い、どのように自分の世界を広げていくかという「心の動き」、「想像力」、「創造力」、そして、その作品や作品を紹介する際に見え隠れする「お子様の成育環境」を知るために行われます。
評価されるのは、絵の上手さや色使いだけでなく、取り組みの姿勢、発想の豊かさ、制作過程に見られる工夫や粘り強さ、そして発言力です。
テーマを理解し、自分の中でイメージを膨らませ、それを形にしようとする一連のプロセスこそが試されます。
たとえ手先が器用でなくても、工夫して取り組もうとする姿勢があれば、それはしっかりと評価に繋がります。つまり、絵画・工作テストは、その子らしさが最もよく表れる場でもあるのです。

【慶應義塾幼稚舎】絵画・工作試験が出題される理由
慶應義塾幼稚舎がこのような形式の試験を行うのは、表面的な能力だけではなく、本質的な“人間力”を見たいという意図があるからです。
お子様がテーマに向き合うとき、そこには観察、理解、思考、判断、表現、そして自信といったさまざまな力が必要となります。それを短時間で引き出し、判断するには、実際に行動や制作を通じて見るしかありません。
特に、自由なテーマに対して自分の言葉や形で表現できるか、自分だけの視点を持てているかという点は非常に重要です。また、最後まで集中して取り組む力や、困ったときにどう対応するかといった、非認知能力も同時に測られています。
【慶應義塾幼稚舎】絵画・工作試験例年の流れ
慶應義塾幼稚舎の絵画・工作テストは、男女別に複数日に分けて実施されるのが通例です。試験当日、受験生は運動や行動観察などの試験を終えたのち、絵画・工作テスト専用の教室へと案内されます。教室内には一人ひとりに割り当てられた席があり、すでに用意されている用紙や道具が整然と並んでいます。
代表的な導入形式
まず始まるのが「導入」と呼ばれる説明タイムです。
・映像を見せる(アニメ、写真、イラストなど)
・ストーリーテリング(語り手が物語を読み聞かせる)
・実演・実物提示(道具や素材を見せてからテーマ提示)
・クイズや選択肢方式で発想を誘導する
上記一例とはなりますが、このように、多彩な方法でその日の制作テーマについて説明が行われます。
試験官は、お子様たちが話を集中して聞いているか、ルールを理解できているか、表情や態度、リアクションまで細かく観察しています。つまり、制作以前に「聞く姿勢」「理解しようとする意欲」などがすでに評価されているのです。
導入の後、テーマに関する発問が行われます。たとえば「バッグの中に入っていたものを自由に描いてみましょう」や「博士が拾った道具を想像して制作しましょう」といった、具体と抽象を行き来するような出題が特徴的です。お子様にとっては、答えが決まっていないからこそ、自分らしい発想を発揮するチャンスでもあります。
【慶應義塾幼稚舎】製作時間の流れと具体的な試験内容
テーマが発表されたあとは、いよいよ制作の時間がスタートします。お子様たちはそれぞれの机に用意された道具を前に、自分のアイデアを形にするための作業に取り組みます。
使われる画材や工作材料
使用される画材は実に多彩で、画用紙、クレヨン、色鉛筆、のり、はさみ、折り紙、シールなどに加え、年によっては紙コップや割りばし、粘土、モール、布素材といった立体制作向けの材料も登場することがあります。これらの素材はあらかじめ決められた数が用意されており、その中から必要なものを自分で選び取る判断力も求められます。
製作に与えられる時間
制作時間は、おおよそ20〜30分ほどが目安となっており、その限られた時間のなかで、テーマを解釈し、構想を立て、制作し、仕上げるという一連の流れをすべて完結させなければなりません。
試験官は、完成した作品だけでなく、その過程においてお子様がどんな姿勢で取り組んでいたか、どのように困難を乗り越えたかといった行動面もしっかりと観察しています。
近年の出題傾向
ここ数年の傾向としては、「ミックス型」の課題が主流となっています。これは、平面表現と立体表現を組み合わせた課題で、たとえば「海の中にある不思議な生き物を立体で作り、その様子を背景とともに描きなさい」といったようなものです。工作で想像した世界を絵に落とし込む、あるいは絵で描いたイメージを粘土などで立体化するといった形式により、構成力や創造的な連動性、物語の展開力までが問われるようになっています。
また、課題の中には“あえて曖昧な指示”が含まれていることもあります。たとえば「とても大切なものを入れる箱を作りなさい」といったテーマでは、その「大切なもの」とは何かという問いそのものが自由に設定されており、お子様の価値観や生活経験までもがにじみ出てくるようになっています。
技術的な完成度よりも、お子様なりに最後までやり遂げようとする姿勢や、ひとつのアイデアにこだわりをもって試行錯誤していく粘り強さこそが、高く評価されるポイントとなるのです。
【慶應義塾幼稚舎】最も大切なのは、絵画・工作試験中の身の振るまい
慶應義塾幼稚舎の絵画工作テストで、作品の完成度と同じくらい、いやそれ以上に重視されるのが、試験中の態度です。試験官は、お子様たちがどのように座り、話を聞き、道具を扱い、トラブルに対処するかといった行動の一つひとつに目を光らせています。
指示をきちんと聞けるか、隣の子の邪魔をせずに自分の世界に集中できるか。何かに悩んだとき、感情的にならずに自分で解決しようとする姿勢があるか。そうした“ふるまい”こそが、その子の育ちを物語る最大の材料となるのです。
【慶應義塾幼稚舎】ご家庭でできる絵画・工作試験対策
慶應義塾幼稚舎の絵画・工作テストの準備として特別な画材やテクニックを用意する必要はありません。むしろ、お子様が日常の中で「見たもの」「感じたこと」「心が動いた瞬間」を、自分の言葉や表現でアウトプットする経験を積むことこそが、最良の対策になります。
ここからは、ご家庭でできる絵画・工作テスト対策をいくつかご紹介します。すべて、日々の生活の中に自然と取り組めるものばかりです。ぜひご家族で楽しみながらトライしてみてください。
絵本の読み聞かせから会話を発展させる
たとえば、絵本を読み終えたあとに「どの場面が心に残った?」と問いかけてみましょう。お気に入りのキャラクターを真似して描いてみたり、ストーリーの続きを自分で想像して形にすることで、自然と想像力と表現力が結びついていきます。
お出かけした後の感想を絵に落とし込む
また、お出かけしたあとも絶好のチャンスです。動物園や水族館、公園などの非日常的な体験の中で、印象的だった景色や出来事を一緒に思い出しながら、画用紙に描いてもらうのも効果的です。
その際、親は「どんな動きだった?」「その時、どう思ったの?」と優しく問いかけ、お子様の記憶や感情を丁寧に引き出すことが大切です。
日常生活で質問の繰り返しを習慣にする
日々の会話の中でも、「この色はどんな気持ちの時に使いたい?」「どうしてこの形にしたの?」といった質問を繰り返していくと、お子様は自分の思考に自信を持ち、自分らしい表現を言葉にしやすくなっていきます。
絵を描く・作るという行為が、単なる「作業」ではなく、自分の感性と対話する時間であることに気づいていくでしょう。
ポイントを絞って具体的に褒める
加えて、制作中のお子様に対して「上手だね」と褒めるのではなく、「よく考えて描いたね」「ここにこんなアイデアを入れたんだね」といった“過程”に着目した声かけを意識することで、お子様の表現意欲をより深く育むことができます。
このように、絵画・工作テストの準備とは、何かを「教え込む」ことではなく、親子の関わりの中でお子様の想像力を自然と引き出すような時間を積み重ねていくことが、本質的な力につながっていくのです。
【慶應義塾幼稚舎】絵画・工作試験内容がすごい!内容や対策方法についてプロが徹底
慶應義塾幼稚舎の絵画・制作テストで高く評価されるお子様たちは、決して“技術的に優れた作品”を作る子ではありません。与えられたテーマを自分なりに受け取り、考え、楽しみながら形にできる子です。
だからこそ、大人が「こうすれば良い」と方向づけをするのではなく、「あなたのその表現、面白いね!」と感性そのものに寄り添う姿勢が何より大切です。
慶應義塾幼稚舎の絵画・工作テストテストは、まさに“その子自身の世界”を試される場です。答えのない問いに、答えを探すのではなく「自分の答えを創り出す力」が問われるこの試験において、必要なのは「発想する習慣」と「表現する勇気」。それを育てるのは、日々のご家庭の中にこそあるのです。
1.jpg)