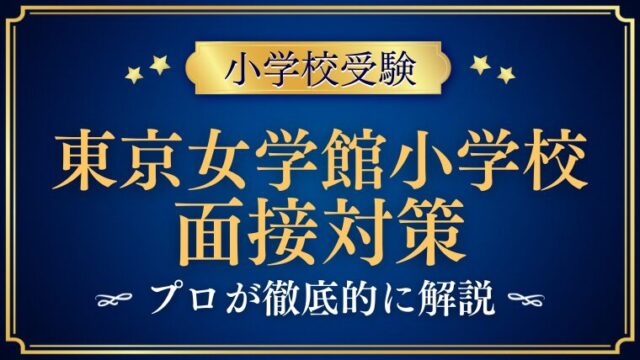慶應義塾幼稚舎は、福澤諭吉の思想を受け継ぐ、慶應義塾の初等教育機関として知られています。「独立自尊」の理念のもと、単なる学力の習得にとどまらず、お子様たち一人ひとりの感性や表現力、自主性といった“人としての根っこ”を大切に育む教育が行われている点が大きな特徴です。
そのため、幼稚舎の入試でも、知識量や処理能力といった評価軸では測れない、“人間としての成熟度”が求められます。中でも、とりわけ受験生間の差が見えにくく、かつ合否に大きく影響する試験が「行動観察」です。
この試験では、一般的に良しとされる協調的な行動や礼儀正しさだけでは、評価に直結しません。むしろ、どれだけその子自身の本質や思考力が、集団の中で自然に表れるかが問われる、極めて本質的な選考です。
本記事では、その慶應義塾幼稚舎ならではの行動観察テストの特徴や、家庭での具体的な対策方法について、丁寧に解説していきます。
【慶應義塾幼稚舎】行動観察試験とは
慶應義塾幼稚舎の入試では、いわゆるペーパーテストは一切実施されません。それは、数値化された点数でお子様を測ることよりも、「行動観察テスト」などを通して直接“お子様自身”に向き合うことで、その子が持つ本質的な知性や、物事への理解力、柔軟な思考力が手に取るように分かると考えられているからです。
この行動観察テストでは、グループ活動や共同制作、ルールのある遊びなどを通じて、お子様たちがどのように他者と関わり、自分らしく考え、行動するかを丁寧に見極めていきます。
一見すると“遊び”のようにも見える課題ですが、その中にこそ真の人物像が現れるため、慶應では最も重視される試験のひとつとされています。
【慶應義塾幼稚舎】単なる「協調性」だけでは通用しない、慶應らしい観点とは?
慶應義塾幼稚舎の行動観察は、他の私立小学校で重視されがちな「協調性」や「空気を読む力」だけでは合格につながりません。もちろん、それらの力があることは前提条件ですが、それだけでは“印象に残る子”にはなり得ないのです。
むしろ重要なのは、協調性を持ちつつも、「自分らしい考え」をしっかりと持ち、それを自然体で表現できるかどうか。仲間と協力しながらも、ふとした瞬間に見える“キラリと光るオーラ”や、“この子にしかない発想や感性”が、選考の決め手となります。
つまり、慶應義塾幼稚舎が求めるのは「調和の中で個性を発揮できる子」。一歩引くでもなく、一方的に前に出るでもなく、場に応じた自分の役割を見つけ、そこに自発的に向き合える姿勢が、高く評価されるのです。
h2 【慶應義塾幼稚舎】行動観察テスト例年の流れ
慶應義塾幼稚舎の行動観察テストは、男女別に複数日に分けて実施されるのが通例です。試験当日、受験生は運動テストを終えたのち、行動観察テスト専用の会場(体育館、教室など)へと案内されます。
試験官は、体操テストや絵画工作テストと同様に、お子様たちが話を集中して聞いているか、ルールを理解できているか、表情や態度、リアクションまで細かく観察しています。つまり、振る舞い以前に「聞く姿勢」「理解しようとする意欲」などがすでに評価されているのです。

【慶應義塾幼稚舎】近年の行動観察の試験内容
近年の出題傾向を見ても、慶應が「お子様らしさと知性の共存」をどう評価しているかがよく分かります。
以下は、2020年度以降に実施された行動観察課題の一例です。
慶應義塾幼稚舎の行動観察テストは、実施日、実施グループに酔って出題内容が異なりますのであくまで一例とご理解ください。
2020年度:フルーツバスケット風の椅子取りゲーム
お題の言葉に対して素早く判断し、自分の席を見つける課題。ルールを理解する力と同時に、周囲の動きを見る広い視野、そして勝敗を切り替える感情のコントロールが問われました。
2021年度:紙コップと輪ゴムを使ったタワーづくり
数人のグループで、輪ゴムを器用に使いながら紙コップを積み上げる課題。コミュニケーション力だけでなく、構造を捉える空間把握能力や、チームでアイデアをすり合わせる粘り強さが必要とされました。
2022年度:条件付きのぬいぐるみ並べゲーム
「赤い帽子をかぶった動物は左端」など、細かい条件を守ってぬいぐるみを並べる活動が出題。単なる作業ではなく、状況の変化に対する柔軟な対応力と、メンバー間での確認・相談といった社会性も評価の対象でした。
h3 2023年度:自由創作とプレゼンテーション要素を含んだ制作課題
「好きな乗り物を作って、紹介する」というテーマで、限られた時間の中で制作から発表までを行う複合型課題。個性と想像力だけでなく、“人前で伝える力”も求められる構成でした。
これらの課題には共通して、「一つの正解がない」ことが特徴です。その場の状況判断、他者との関係性、そして自らの創意工夫をいかに自然に出せるか――こうした力こそ、ペーパーでは測れない“本物の知性”として慶應が重視しているポイントです。
【慶應義塾幼稚舎】最も大切なのは、試験中の身の振るまい
慶應義塾幼稚舎の行動観察テストでは、課題への取り組み方と同じくらい、いやそれ以上に重視されるのが、試験中の“ふるまい”です。
試験官は、子どもたちがどのように場に入り、仲間と関わり、問題に直面したときにどう行動するか、その一つひとつを丁寧に観察しています。
友だちの意見に耳を傾けられるか、自分の考えを伝えるときに相手の気持ちを尊重できるか。衝突や行き違いが起きたときに、大人の指示を待たずに自ら修正しようとする姿勢があるか。そうした瞬間の積み重ねこそが、その子の育ちと内面を語る、何よりも雄弁な証拠となるのです。
【慶應義塾幼稚舎】ご家庭でできる行動観察試験対策
このような本質的な力を短期間で習得するのは難しく、日々の生活の中で育んでいくことが何よりの対策となります。
たとえば、家族でルールのある遊びやボードゲームを楽しむこと、普段の会話で「どうしてそう思ったの?」とお子様の思考を引き出すこと。さらには、トラブルや意見の違いを乗り越える体験をポジティブに受け止め、「自分で考えて動く」習慣を支える姿勢が大切です。
また、保護者が「うまくやらせる」ことに固執するのではなく、「自分らしく取り組めたこと」を評価し、安心感を与える関わり方をすることで、お子様は自信を持って本番に臨むことができます。
ここからは、ご家庭の日常生活で簡単に取り組める「慶應義塾幼稚舎行動観察テストの対策」を具体的な方法でご紹介します。ぜひ気軽に取り組んでみてくださいね。
毎週末の夕方は家族でボードゲームの時間にする
行動観察テストで問われるのは、話し合いの力や順番を守る態度、勝敗への折り合い、そして何より「他者とのやり取りを楽しむ姿勢」です。
これらを無理なく日常に取り入れるには、週末に家族でボードゲームをする時間を設けるのが効果的。ゲームの選び方としては、ルールが明確で順番を守るもの(オセロやUNO、すごろくなど)が特におすすめです。
お子様が悔しがったり、反則したりする場面も含めて、感情の整理や話し合いの練習につながります。勝ったときの振る舞いや、負けた相手への声かけなどもさりげなく教えていくと、自然と“社会性”が育っていきます。
「どうしてそう思ったの?」と聞く習慣をつける
家庭での会話は、お子様の思考力を育てる最高のフィールドです。特に慶應幼稚舎の行動観察では、ただ行動するだけでなく「考えて行動する力」が重視されるため、日頃から「なぜそうしたの?」「どうしてそう思ったの?」と問いかけることが非常に効果的です。
これは詰問ではなく、あくまでお子様の考えを引き出すきっかけ。正解を求めず、「へぇ、そういう考え方もあるんだね」と肯定的に受け止めることで、お子様は自分の意見を伝えることに自信を持てるようになります。
行動の背景にある“理由”を言葉にする経験が、観察テスト本番でも生きてくるのです。
異年齢の子と遊ぶ機会を意識的につくる
幼稚舎の行動観察では、自分と異なるタイプの子とどう関われるかも見られています。そのため、同年齢だけでなく異年齢のお子様たちと接する機会を意識的につくることも大切です。
年下の子と遊ぶときには、ルールを教えたり助けたりするリーダーシップが、年上の子と接するときには、素直に話を聞く態度や協調性が育ちます。
兄弟姉妹がいない家庭であれば、公園での声かけや、親子参加型の地域イベント、友人家族との合同遊びなどが有効です。家庭の中だけでは得られない“違いを受け入れる力”が、ここで自然に磨かれていきます。
【慶應義塾幼稚舎】行動観察の試験内容をプロが徹底解説!
慶應義塾幼稚舎の行動観察テストは、決して単なる集団遊びや「いい子」を演じる場ではありません。そこにあるのは、「この子と6年間、共に学び、共に成長していきたい」と心から思わせる“人間力”があるかどうかを見極める選抜です。
福澤諭吉の「独立自尊」の精神を継承し、時代を切り拓く人材を輩出し続けてきた日本屈指の名門校として、慶應義塾幼稚舎が求めるのは、単に“協調的なふるまい”をできる子ではありません。
自らの考えを持ちながらも他者を思いやる力、個性と共に長く良好な人間関係を築いていける土台のある子どもこそが、真に評価されるのです。
これは、6年間クラス替えを行わないという幼稚舎独自の体制にも通じます。固定された環境で多様な仲間と向き合い続けるからこそ、表面的な良さではなく「深い人間性と信頼関係を育める資質」が求められるのです。
日々の暮らしの中で育まれた優しさ、知的なまなざし、そして自分を信じて一歩踏み出す力。それらすべてが、試験当日の“自然な一瞬”に集約されていきます。
正解のない世界の中で、誰かに流されず、でも誰かを大切にしながら、自分の光を放てる―。そんなお子様が、慶應義塾幼稚舎における「未来をつくる存在」として、伝統を守り、進化を続けるこの学び舎にふさわしいといえるのです。
1.jpg)