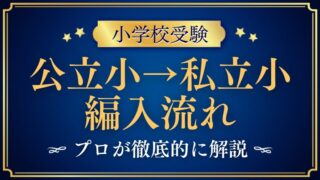公立小学校から私立小学校へ編入を検討するご家族の中には、お子様がいじめの被害にあっていたり、学校への行き渋りがあったりと、登校に関して何かしらの問題を抱えている場合もあります。
しかし、現状を打破するために選んだ私立小学校に、またいじめの問題があったら…そう悩み不安になられる方もいらっしゃることでしょう。
私立小学校にもいじめはあるのでしょうか?
もしいじめがある場合、編入前に確認すべきポイントはあるのでしょうか?プロが徹底解説します。
私立小学校編入後にいじめはある?現状を知る
結論から申し上げると、歴史ある伝統私立小学校や何万倍もの倍率を突破しないと入学できない国立小学校であっても、いじめが起きる可能性はあります。
いじめのない学校とは、まだいじめが起こっていないだけの学校です。
どんな学校であってもいじめのリスクは平等に抱えているのです。
私立小学校でもいじめが起こり得る理由
当たり前のことですが、私立小学校でもいじめが起こり得ます。
どれだけ厳しい選考を経ていたとしても、そこに集うのはまだ6~12歳の幼いお子様たちです。
精神的な未熟さや、性格や価値観の違いから自然と摩擦が生じることは日常的なことです。
公立小学校と比べると、私立小学校の方がご家庭の教育観や環境が近いご家庭が集まりやすい傾向はあるものの、個々の背景も多様であり、その違いが人間関係の摩擦につながることもあります。
どの学校でもいじめの可能性はゼロにはならないため、学校や保護者がお子様の心に寄り添い、早期に問題を発見し対応する姿勢が大切です。
公立小学校と私立小学校のいじめの違い
私立小学校のいじめへの対応には、公立小学校と異なる特徴がいくつかあります。
まず、私立小学校は1学年あたり1~3クラス程度の規模であることが多く、1学年に対するクラス数が少なめです。
そのため、教職員が児童一人ひとりの状況を把握しやすい環境にあります。
教職員の芽が行き届きやすい分、小さな問題がいじめのレベルにまで発展する前に気づき、早期対応が可能です。
さらに、私立小学校の教職員は任期や転勤がなく、長年勤務するケースが多いです。
これにより、学校全体で過去の事例を共有し、いじめに関する対応のノウハウが蓄積されています。
これらの経験を活かし、いじめの発生時には迅速かつ的確に問題解決に導く体制が整っています。
また、私立小学校では防犯カメラやICT機器など、設備が充実していることが多い点も特筆すべきです。
教室や廊下などに防犯カメラが設置されている場合、いじめの事実確認が容易に行え、関係者全員が納得できる形で解決を進めることが可能です。
このように、設備面でもいじめを防ぐための環境が整っていると言えます。
このように、私立小学校では少人数制の特性や教職員の経験の蓄積、充実した設備を活用し、いじめを未然に防ぎ、発生時にも迅速に対応する仕組みが整っています。
これらの取り組みは、お子様たちが安心して学べる環境づくりに大きく寄与しています。
私立小学校編入前に確認するべきポイント
もちろん、私立小学校の全てが上記のような状況・対応をしてくれるとは限りません。公立小学校と同様に、学校によって対応力やその方法は異なります。
そのため、保護者としては編入試験を通して各校の対応方法を確認しておく必要があります。
では、具体的にどのようなポイントを確認すれば良いのでしょうか?プロが詳しく解説します。
保護者間の直接連絡について学校側がどう考えているか
私立小学校では、保護者同士が直接連絡を取り合うことを推奨しない学校も多いです。
学校がこのような立場を取る理由は、問題を適切に解決するために教職員が介入し、状況を把握した上で対応することが重要だと考えているからです。
このような学校では、いじめ問題に関しても、学校が主導して問題解決にあたるため、効果的な対策を講じるノウハウや実績を持っている可能性が高いです。
保護者間で感情的な衝突を避け、冷静に問題解決を図る姿勢が、いじめの早期発見と解決につながります。
学校が保護者同士の関わり方をどう考えているのかを理解しておくことで、家庭内での不安や疑問を解消し、安心して通わせることができます。
志望校の教育理念や教育方針
いじめに対するアプローチは、学校の教育方針や教育理念に大きく影響されます。
例えば、カトリック教育を軸とする学校では、いじめをした児童に厳罰を与えるのではなく、反省と赦し、共に成長することを重視する指導が行われることが多いです。(*決していじめを許容しているという意味ではありません。)
このような学校では、対話を通じて問題を解決する方針が取られます。
しかし、この考え方に否定的なご家庭では、学校の方針とご家庭でのスタンスが合わず、問題が生じた際に困難を感じることもあるかもしれません。
いじめへのアプローチが家庭の価値観と合わないと、後々の教育環境で不安を感じる可能性があります。
そのため、学校選びの際には、教育理念やいじめへの対策をしっかり比較し、納得できる学校を選ぶことが必要です。
人間関係のトラブル発生時の対応
いじめやトラブルが発生した際、学校がどのように対応するのかを知ることも重要です。
学校によっては、専任のカウンセラーが相談窓口として設けられている場合があります。
また、教職員や担任が問題解決にどう関わるのか、関係者間で情報共有をどのように行うのかも重要なポイントです。
迅速かつ効果的な対応ができる体制が整っているか確認しておくと安心です。
いじめが気になる場合にできる具体的な質問例
「私立小学校編入前に確認するべきポイント」を理解できたとは言え、学校側にストレートに聞くことは難易度が高いことでしょう。
「あなたの学校に入れてください!」とお願いする立場にあるのに「お宅の学校にいじめがありますか?」なんて聞けるような親御様は少数派ですし、学校によってはその質問を口にしただけで相性が悪いと判断されかねません。
そんな危機に陥らないため、いじめ問題について間接的に質問するための質問例をいくつかご紹介します。
これらの質問は、学校への関心や信頼を示す形になるため、ポジティブな印象を与えつつ、重要な情報を得るのに役立ちます。ぜひ参考にしてください。
「御校ではお子様たちが安心して学校生活を送れるよう、どのような取り組みをされていますか?」
この質問は、学校がどのように児童の安全や心のケアを実践しているかを理解するためのものです。
例えば、学校が行っている「心の教育」や「児童同士の関係づくり」などの取り組みを知ることができます。
また、少人数制や担任の先生の目が行き届きやすい環境で、個別のニーズにどれだけ対応しているかも分かります。
学校がお子様の心の成長を重視し、トラブルやいじめが起こる前に予防策を講じているかを確認できます。
「児童間でトラブルが発生した場合、どのような対応を取られているか教えていただけますか?」
この質問は、学校が実際にトラブルやいじめが発生した場合にどのように対応するかを知るためのものですが、”いじめ”というセンシティブワードを使わずに質問することができます。
迅速で適切な対応が取られるのか。
また、事実確認や関係者への配慮がどのように行われるかを確認できます。
この質問を通して、志望校が問題解決の姿勢や透明性が感じられる学校であると判断できれば、安心してお子様を任せることができます。
「もしお子様が学校に行きたくないと言った場合、保護者としてどのように寄り添うべきか教えていただけますか?」
この質問は、学校がいじめや心理的な問題に対してどのようにサポートをしているかを知るためのものです。
保護者が学校に教えを請い、具体的なアドバイスをした場合、その内容がそのまま学校側の価値観に直結します。
例えば「ご家庭でお話を聞いてあげてください。その上で、学校側にご報告いただけますか。」や「まだ幼いうちは状況を客観的に説明できない場合もあります。気になることがあればいつでも学校に連絡してください。」といったアドバイスをしてくれるならば、児童間の問題に学校側が積極的に介入し、解決に向かうよう努力してくれる学校と言えるでしょう。
私立小学校に編入後にいじめを受けないために親ができること
最後に、私立小学校に編入後お子様がいじめを受けないために、親御様ができることを解説します。
親御様ができることは限られるかもしれません。しかし、できる限りの努力をすることで、いじめのリスクを下げることにつながります。
お子様が何でも話せるような関係作り
お子様が新しい環境での不安や悩みを安心して話せるように、親子の信頼関係を日頃から築いておきましょう。
お子様の話を聞く時は、叱責ではなく共感や理解を示し、お子様に「お父さん/お母さんにはどんなことでも話していい。」と感じさせる環境を整えます。
また、親御様自身の過去の体験を共有し、お子様が同じような悩みを抱えても自然に相談できる雰囲気を作ることも効果的です。
大切なのは、親御様が味方であることを常に伝えることです。
学校側と定期的なコミュニケーションを取る
親御様のできる対策のひとつとして、新しい学校での生活が順調に進むよう学校との連携を密に保つことも大切です。
担任の先生のご負担にならない程度に定期的な面談やメールでのやり取りを通じて、お子様の学校での様子や友人関係を把握しましょう。
また、編入前のタイミングで担任の先生をはじめとする教職員の方々にお子様の個性や状況を共有することで、適切なサポートを得られる可能性が高まり、万が一問題が発生した際には迅速に対応できる体制を築くことができます。
積極的な関与を通じて、学校側と親御様の良好な関係を育んでおきましょう。
お子様の様子をよく観察する
編入後の半年間は特に注意深くお子様の様子を観察しましょう。
普段と異なる行動や感情の変化が見られる場合、それは新しい環境への適応に苦労しているサインかもしれません。
年頃のお子様はマイナスな話をストレートに話すことを嫌がる傾向にあります。
直接的な質問だけでなく、普段の会話や行動の中から情報を探るようにするのがおすすめです。
また、必要であれば学校の先生やカウンセラーにも相談し、早期に問題を解決することを心がけましょう。
私立小学校にいじめはある?編入前に確認すべきポイントまとめ
私立小学校にいじめはあるか?
そして、編入する前にどのように確認すればよいのかそのポイントをプロが徹底的にまとめました。
大切なのは、いじめが起きない学校を探すことではありません。
いじめやいじめにつながりそうな問題が起きた場合、保護者と一体となって解決しようとしてくれる学校か。
また、その対処法がご家庭の価値観と揃っているかを事前に知ることが大切です。ぜひ事前にチェックし、後悔のない学校選びをしてくださいね。

1.jpg)