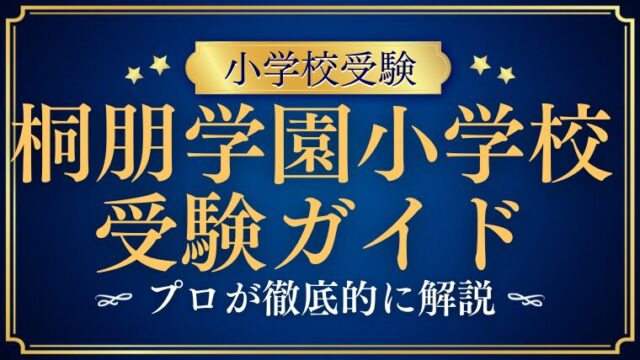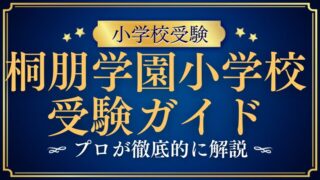【立教女学院小学校】過去問は入手できる?
立教女学院小学校の過去問は、さまざまなお教室や出版社から年度別に発行されています。ここでは、代表的なものをご紹介します。
【立教女学院小学校】過去問からわかる出題傾向
ここからは、立教女学院小学校の入学考査で実際に出題された課題内容を年度ごとに具体的に解説します。
ペーパーテスト
【出題傾向の概要】
立教女学院小学校のペーパーテストは、数量・記憶・推理・言語・常識といった複数の分野にわたり出題され、いずれの年度も「思考の過程」や「聞く力」「状況理解力」を重視している点が共通しています。単なる知識量やスピードよりも、話を正確に聞いて理解する力や、場面の意図を汲み取って行動につなげる力が試されます。
・2025年度の出題
数量、話の記憶、観察力、話の理解、常識、推理・思考(重ね図形)、進み方、模写、言語など、非常に多岐にわたる設問構成となっています。特にストーリー性のある問題が多く、動物やお菓子を用いた「日常的で親しみやすい場面設定」の中で、数の合成・分解や条件整理、順序推理といった力が問われています。また、模写や言語(語頭・語尾)といった感覚的な問題も含まれ、ペーパーテスト全体のバランスの良さが特徴です。
・2024年度の出題
この年度は「数量」「推理・思考(対称図形)」「言語」「語」「位置・記憶」「進み方」といったテーマが軸になっています。数量分野では、動物が料理を作る際の材料や作業工程を通じて、計算力と論理的思考を問う設問が出されました。図形や言語に関する問題では、「視覚と聴覚」両面の認知力をバランスよく評価する構成となっており、過去問全体における難易度は中程度からやや高めと考えられます。
・2023年度の出題
前年と比較して、ストーリー性や操作性がより強調されているのが2023年度の特徴です。数量問題では、アトムシを捕まえる場面や卵と料理の関係、動物の交換ゲームなど、物語に沿って数量を把握する形式が中心となっており、シンプルながらも「前提条件の整理力」が求められます。また、話の記憶や言語、推理(立体図形)では、視覚情報を聞き取りながら記憶・推測・選択するといった一連の思考プロセスが求められていました。
個別テスト
【出題傾向の概要】
個別テストでは、受験生が先生と1対1で取り組む形式で、巧緻性や制作課題を中心に、その子の集中力・指示理解・作業の丁寧さが評価されます。各年度で課題の形式やテーマは異なりますが、共通して「話を正確に聞き、自分の手を使って何かを完成させる力」が問われています。
・2025年度の出題
この年の制作課題は、色の指示理解と手先の操作を組み合わせた構成でした。まず、子どもたちは自分の机の上に貼られた色テープと同じ色の画用紙を、教室内の決められた場所まで取りに行きます。その後、その画用紙をハサミで切ったり、シールを貼ったりしながら「カード」を完成させる制作課題が出題されました。このカードは、後の集団活動(カード遊び)で使用されるもので、単なる手先の巧緻性にとどまらず、「聞いた指示を理解し、段取りよく作業し、最後に自分の作ったもので人と関わる」という一連の流れを含む高度な評価設計になっていました。
・2024年度の出題
この年は、制作課題として「ライオンのお面作り」が出題されました。使用された材料は、B4サイズの画用紙と、クレヨン・ホッチキス・はさみ・のりなどの一般的な道具です。配布された画用紙に顔の輪郭が印刷されており、子どもたちはそれにたてがみや顔のパーツを描いたり貼ったりして完成させます。2025年度と比べると創作の自由度が高く、完成品の見た目にも個性が表れやすい課題となっていました。一方で、道具の使い方や片付け、作業中の丁寧さといった基本姿勢も重要視されています。
・2023年度の出題
この年度は、ビーズ通しや紙皿・ストロー・ペン・セロテープ・輪ゴム・はさみなどを使用した複合的な制作課題が出題されました。決められた材料を使って構造物を作る形式で、工程の順序、手先の器用さ、空間把握力などがバランスよく求められました。制作テーマ自体は記載されていないものの、材料構成から見て「見本を見ながらの再現型」または「簡単な工作物を完成させる課題」であったと推測されます。創意工夫よりも、道具を安全に・正しく扱いながら、落ち着いて作業を進める姿勢が評価の中心と考えられます。
生活習慣(個別テスト内)
【出題傾向の概要】
立教女学院小学校の生活習慣テストは、3年連続で「お箸の使い方」をテーマとした出題がなされており、他校と比べても際立った特徴となっています。いずれの年度も、単に正しい持ち方ができるかどうかを確認するのではなく、実際にお箸を使って何かをつまむ・移す・扱うという実演課題が設定されています。
「家庭でお箸をどのように扱っているか」「道具に対する丁寧さや姿勢」「食事の所作として自然に身についているか」など、普段の生活ぶりがそのまま表れる領域として、立教らしい温かくも本質的な視点で子どもたちが見られています。
・2025年度の出題
2025年度は、“お寿司ゲーム”のような形式でお箸の使い方を観察する課題が出されました。
4人ずつが前に呼ばれ、テーブルの上には、
・お寿司型の消しゴム
・おわん
・割り箸
が用意されています。試験官の「美味しいものをおわんに入れましょう」という声かけに従い、子どもたちはお箸でお寿司消しゴムを1つずつ取り、おわんに移していきます。「やめ」と言われるまで繰り返し、その後は「お片づけしましょう」という指示で片づけの所作も観察されました。
この課題では、楽しげな雰囲気の中で自然な所作としてお箸を扱えるかどうか、また緊張の中でも落ち着いて手先を動かせるかが見られていたと考えられます。
・2024年度の出題
この年は、よりバリエーションに富んだ素材を用いた実演型のお箸課題が出題されました。
子どもたちの前には、
・ビー玉
・ビーズ
・スーパーボール
・ひも
・大豆
など、異なる大きさ・重さ・形状の素材が混在する容器が置かれており、それらをお箸で別の容器に移すという作業に取り組みます。
素材によって扱いにくさが異なるため、ただ持てるかどうかだけでなく、力加減・集中力・道具に対する丁寧さなど、多角的に見られていたことがうかがえます。子どもたちの技術だけでなく、「楽しんで取り組む姿勢」や「諦めずに続ける粘り強さ」も含めて観察されていたと思われます。
・2023年度の出題
2023年度も、お箸に関する実技課題が実施されています。
この年は、もっともシンプルに、
・正しい箸の持ち方ができているか
・モノをつまむ動作ができるか
を実際に受験生たちにやってみせてもらう形式でした。
教材の詳細は不明ですが、他年度と同様に「つまむ対象物」が用意されており、それを正しい手の動きで扱う様子が評価されています。
ここでは、お箸を持つ所作が自然かどうかや、普段の生活の中で使い慣れているかどうかが観察ポイントであり、机上の知識ではなく「家庭での習慣」がそのまま出る構成でした。
集団テスト
【出題傾向の概要】
立教女学院小学校の集団テストでは、受験生たちの協調性・自発性・ルール理解・社会性を見極める活動が行われます。年によって実施される内容は異なりますが、特に近年は個別テストで制作したアイテムを活用する「制作連動型アクティビティ」が導入されており、「自分で作ったものを使って遊びに参加する力」や「創作物を媒介としたコミュニケーション力」も評価対象になっていることが特徴的です。
・2025年度の出題
この年度の集団テストは、個別テストで作成したオリジナルカードを用いた「カード遊び」でした。3人1組の小グループで、各自が持ち寄ったカードを使ってルールに沿ってゲームを行う形式で、ルール理解・順番を守る態度・相手への気配りなどが見られました。特に注目すべきは、自分が作ったものを「道具」として共有する体験の中で、遊びに取り組む姿勢・言動・関係の築き方が自然に観察されるよう構成されている点です。また、ゲームが終わった後にカードを片づける場面なども評価対象になっていたと見られます。
・2024年度の出題
2024年度は、従来の「風船ゲーム」や「指示行動」に代わり、個別テストで制作したライオンのお面を装着しながら参加する「冒険ゲーム(オリジナルの集団活動)」が行われました。お面をつけた状態で、集団で動き回る/役割を演じる/簡単な指示に従うといった要素が盛り込まれた活動で、子どもたちが創作物を媒介に一体感を持って取り組むことを意図した設計となっていました。この活動を通して、集団内での振る舞いや反応、周囲との関わり方、即時の判断力や柔軟性などが観察されたと考えられます。
・2023年度の出題
この年は、より伝統的な集団テスト形式で、「仲間探しゲーム」と「指示行動」が行われました。仲間探しでは、特定の共通点(色、アイテム、持ち物など)を持つ他の子どもたちとグループを作る活動で、観察力や他者への声かけ、協調的態度などが見られました。また、指示行動では、試験官の動きや指示を模倣して実行する形式で、「話をよく聞き、タイミングよく正確に動けるか」が評価されました。これらの活動は、他者との自然な関わりの中での振る舞いを浮き彫りにするという意味で、非常に効果的な観察手法となっています。
運動テスト
【出題傾向の概要】
運動テストでは、身体の使い方やリズム感、指示を聞いてその通りに動けるかどうかといった「体と心の連動性」が重視されます。いずれの年度も運動能力の高さ自体よりも、「姿勢・集中力・やり遂げる力」「初めての動きに対する適応力」などが評価の軸となっています。
・2025年度の出題
この年度は「連続運動」の構成で、マット上でのアザラシ歩き、フープを通過するケンケン、スキップなどを順に行うコースが用意されました。道中にはボールをキャッチする課題や、特定の動作を繰り返すエリアもあり、全身を使いながらテンポよく進行する「リズムと集中力」が求められました。運動が得意かどうかよりも、指示を正確に再現し、最後までやりきる力が試されていた印象です。
・2024年度の出題
この年は、体育館に設定されたコース内で「スキップ・ケンケン・ジャンプ・方向転換」などの基本動作を繋げて行う形式でした。動きの中には「赤いフラッグを拾って青のマークの位置に置く」などの簡単なタスクも含まれ、単なる体の動きだけでなく「聞いたことを覚えて実行する力」「タイミングの感覚」などが見られていました。
・2023年度の出題
2023年度は、縄跳びと連続運動の2本立て構成でした。縄跳びは、1人ずつ順番に呼ばれて前方に進み、決められた場所で一定回数跳ぶという内容で、リズム感や持久力の確認が意図されています。連続運動では、スキップ、ケンケン、フープをまたぐ、両足跳び、アザラシ歩きなど複数の運動を1つのコース内で行う“サーキット形式”で、身体のコントロール、集中力、バランス感覚を総合的に試されました。年少児にとってはやや負荷の高い構成ですが、そのぶん「がんばる姿勢」や「途中であきらめない粘り強さ」が重視されたと見られます。

【立教女学院小学校】過去問に対応した家庭学習のコツ
立教女学院小学校の入試では、思考力や生活習慣、協調性など、表に出にくい力が幅広く問われます。過去3年の傾向をふまえ、ご家庭で取り組みやすい学習ポイントをご紹介します。
「聞く力」と「情報整理力」を育てるペーパー対策
立教女学院小学校のペーパーテストは、聞き取った情報を頭の中で整理し、考えを導く力が必要です。たとえば「話の記憶」や「進み方」など、一度の説明を正しく理解する問題が多く出題されています。
家庭では、絵本の内容をあとから思い出す遊びや、「おつかいの内容、覚えてる?」といった日常の会話の中で、聞く力や整理力を伸ばせます。音だけの情報処理に強くなることが、合格の鍵となります。
「お箸の実技」を日常で自然に習慣化する
立教女学院小学校の生活習慣の課題では、3年連続で「お箸」が出題されており、立教らしさが表れています。ビー玉や消しゴムをつかむといった実技も見られました。
家庭では、日々の食事の中で正しい持ち方を自然に定着させることが重要です。「ごっこ遊び」などを通じて練習すれば、子どもも楽しんで取り組めます。丁寧な道具の扱いは、「立教にふさわしい子」という好印象にもつながります。
制作・集団活動で求められる「丁寧さ」と「責任感」
立教女学院小学校の個別テストでは毎年制作課題が出されています。お面やカードなど、指示をきちんと守りながら丁寧に作る力が求められます。
ご家庭では、基本的な道具の使い方を日頃から練習し、「先生に言われた通りに作ってみよう」といった活動も効果的です。また「どうやって使うの?」「友達と遊ぶなら?」といった会話を通して、作品への責任感や人との関わり方も育てられます。
プロのサポートを受ける方法も
立教女学院小学校の入学考査では、普段の暮らしの中で培われる力が試されます。特別な教材に頼るよりも、「丁寧な生活」「人への思いやり」を意識することこそが、最良の対策です。
ご家庭だけでの対策に不安がある場合は、幼児教室やプロの講師の力を借りるのも有効です。専門家による視点は、ご家庭では見落としがちな課題にも気づかせてくれます。
私は、立教女学院小学校に特化した願書作成や面接レッスン、家庭学習支援サービスを得意としており、いずれも高い合格実績を誇ります。もしお困りの場合は、一度相談LINEまでご連絡くださいね。ひとりで悩まず、プロの手を上手に活用して受験準備を進めていきましょう。
まとめ:立教女学院小学校の過去問対策は、家庭での取り組みが土台に
立教女学院小学校の入試に向けた準備において、もっとも大切なのはご家庭での関わり方です。日々の暮らしの中で、ご家族がお嬢さまとどれだけ丁寧に過ごしているか、どんな対話や経験を積み重ねてきたかが、そのまま試験に表れます。
遊びや生活の場面を通じて、自然なかたちで思考力や人との関わり方を育んでいくことが、立教らしい学びの第一歩です。必要に応じて外部のサポートも取り入れながら、お子さまと向き合い、一緒に成長していく姿勢が何よりも大切です。
そうした毎日の積み重ねが、お嬢様や親御さまの確かな自信となり、合格へとつながっていきます。焦らず、前を向いて、一歩ずつ準備を進めていきましょう。
1.jpg)