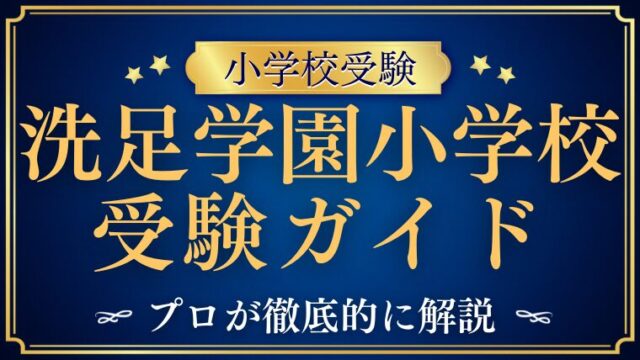2013年に神奈川県横浜市に開校した慶應義塾横浜初等部は、慶應義塾幼稚舎に次ぐ、大学までの一貫教育を担う慶應義塾の2校目の小学校です。
言語能力や論理的思考力を養う教育に重きを置き、「ことば」や「英語」の学習がカリキュラムの中核を成しています。将来の国際社会を見据えた実践的な教育方針が高く評価されており、全国から注目を集めています。
また、同校では学力のみならず、身体表現や芸術的感性、そして自主性を重視した教育が行われています。お子様が自らの意思で行動し、他者と協働しながら社会性を育む環境が整っているのが大きな魅力です。
本記事では、慶應義塾横浜初等部の入試に関する全体像を、「試験の流れ」「出題傾向」などに分けて、プロがわかりやすく徹底解説します。
【慶應義塾横浜初等部】入学試験の全容をご紹介
慶應義塾横浜初等部の教育理念である「独立自尊」は、入学試験の内容にも色濃く反映されています。単なる暗記や反復ではなく、考え抜く力、そしてその考えを言語化する力が求められます。
同校の入学試験は一次試験と二次試験に分かれており、それぞれに異なる力が問われます。一次試験はペーパーテスト(筆記試験)、二次試験は絵画・制作・行動観察・運動といった実技中心の内容となっています。
特筆すべきは、一般的な私立小学校入試で多く見られる「家族・保護者面接」が存在しない点です。その代わりとして、願書提出時に課される「課題図書の感想文」によって、家庭の教育観や親子の関わり方を評価するという、ユニークな仕組みが採用されています。
一次試験では、ただ正しい答えを導き出すだけでなく、「どう考えたか」「なぜその答えになったのか」といった思考のプロセスが問われます。こうした姿勢は二次試験でも同様で、絵画や行動観察などにおいても「なぜそのように表現したのか」「どんな意図があったのか」を語る力が必要とされます。

【慶應義塾横浜初等部】入学試験 実施日程
まずは、2025年度(2024年実施)の入学試験日程をご紹介します。
| 一次試験試験日 | 受験者 |
| 2024年11月11日(月) | 全員。女児→男児の順。年少者から順に実施。 |
| 二次試験試験日 | 受験者 |
| 2024年11月22日(金) | 男児(年少者から) |
| 2024年11月23日(土) | 男児 |
| 2024年11月24日(日) | 女児(年少者から) |
| 2024年11月25日(月) | 女児 |
一次試験では、志願者全員が同日に受験します。まず女児、その後男児と分けられ、さらに月齢の低い順に試験が実施されるのが特徴です。
二次試験に進めるのは、全体の約3割程度とされています。こちらも年齢順でグループ分けされ、4日間に分けて男女別に実施されます。二次試験では、制作・絵画課題、集団行動観察、そして運動テストが行われます。
慶應義塾横浜初等部の試験は11月中旬以降に実施されるため、他の多くの首都圏私立小学校の入試日程と重なることが少なく、併願しやすいスケジュールが特徴です。そのため、第一志望として受験する家庭はもちろん、他校でご縁を得られなかった家庭が「最後の勝負」として受験するケースも多く、受験者が殺到する傾向があります。
しかし、試験日程が11月下旬まで続くため、長丁場に及ぶ準備期間に加え、親子ともに精神面での持久力が求められるのも事実です。慶應義塾横浜初等部を本命とするご家庭は、早期に他校での合格を得るなど、気持ちに余裕を持てるよう併願校戦略をしっかりと立てることが肝要です。
【慶應義塾横浜初等部】一次試験 実施される試験内容
慶應義塾横浜初等部の入学試験で課される試験は具体的にどのような内容なのでしょうか。まずは1次試験についてプロが解説します。
ペーパーテスト
一次試験では、主にペーパーテスト(筆記試験)が課されます。出題内容は一見するとスタンダードな構成ですが、その実、お子様の基礎力と柔軟な思考力を丁寧に見極める意図が込められた良問が並びます。
お話の記憶、図形認識、数量感覚、生活常識といった分野が中心で、単なる正解の多さではなく、「どれだけ落ち着いて取り組めているか」「理解に基づいて問題を処理しているか」が重視されます。年度によっては、問題を解くための補助道具として積み木や円筒といった具体物が使われることもあります。
また特徴的なのは、設問によって筆記用具やその色を変えるように指示が出される点です。これは、指示を正確に聞き取り、その通りに実行する力、すなわち「聞く力」と「注意力」を評価するための工夫です。たとえば、「赤いクレヨンで○をつけましょう」などの音声指示があるため、しっかりと耳を傾けながら問題に取り組む姿勢が求められます。
これらの出題形式からもわかる通り、慶應義塾横浜初等部では、単なる知識の多寡よりも、考える力・聞く力・集中力といった基礎的な能力を重視して評価しているのです。

【慶應義塾横浜初等部】二次試験 実施される試験内容
実施される試験内容 一次試験を通過した受験生のみが臨むことができる二次試験では、主に3つの領域で実技的な力が試されます。それが、絵画・制作テスト、行動観察テスト、そして運動テストです。詳しく見ていきましょう。
絵画・制作・行動観察テスト
慶應義塾横浜初等部の二次試験で出題される絵画・制作課題は、年によって内容が変わるものの、「自分の思いを表現する力」と「それを言葉にして伝える力」の両方が求められます。
2021年度以降は感染症対策の影響で絵画のみの出題が続いていましたが、2024年度には画用紙や箱など身近な素材を使った立体制作と、それを用いた自由な遊びが行動観察の中で再び導入されました。
この試験では、作品を作る際の発想や工夫、その過程における主体性が大きな評価ポイントとなります。「何を表現したいのか」「どのように工夫したか」といった制作の意図を、審査員にしっかり伝えられるような準備が重要です。
一方で、行動観察テストでは、集団でのルール理解や協力姿勢、周囲との調和を保ちながら課題に取り組めるかが見られます。遊びを通じた自然な交流のなかで、協調性やリーダーシップ、適応力などが丁寧に観察されるのです。


運動テスト
慶應義塾横浜初等部の運動テストでは、模倣体操やリズム運動、ボール運びや段ボールを使ったリレーなど、多様な身体表現が課題として出題されます。
ここでは、純粋な運動能力というよりも、「状況を把握して的確に動けるか」「体をコントロールできるか」「仲間との動きに配慮して行動できるか」といった、心と体のバランスが重視されます。
慶應義塾の教育理念には、福澤諭吉の『まず獣身をなして後に人心を養う』という言葉があり、身体を通して人間形成を図るという価値観が根底にあります。運動テストはその思想を体現した試験でもあり、心身の成熟度が評価対象となります。
とくに注視されるのは、課題に取り組む態度です。緊張のなかで過度に萎縮したり、逆にふざけてしまったりすることなく、適度な緊張感と前向きな姿勢で参加できるかどうか。審査員は、お子様たちの姿勢や感情の安定度まで含めて総合的に評価していきます。

【慶應義塾横浜初等部】ご家庭でできる試験対策
慶應義塾横浜初等部の入学試験は、短期間の詰め込み型の学習では対応が難しい、深い理解や思考、表現力が問われる内容となっています。だからこそ、日々の家庭生活のなかで自然と力を養っていく姿勢が大切です。ここからは、ご家庭でできる試験対策をご紹介します。
一次試験対策
一次試験のペーパーテストでは、基礎的な知識をベースにした問題が中心ですが、正確さとスピード、そして集中力が求められます。難解な問題に挑むよりも、「基本的な問題を確実に、テンポよく解ける力」を身につけることが重要です。
また、聞き取り力と注意力が必要な指示形式の問題が含まれるため、普段から「人の話をよく聞く」「指示を正しく理解する」練習を取り入れましょう。例えば、「赤い鉛筆で丸をつけてね」といった指示にすぐ反応できるよう、遊びの中で色や道具を使い分ける経験を重ねることが有効です。
二次試験対策
絵画・制作においては、自由に描いたり作ったりするだけでなく、「なぜそれを描いたのか」「どんな工夫をしたか」といった自己表現の力を磨くことが求められます。日頃からお子様の作品について会話をし、「どんな気持ちで描いたの?」「ここはどうしてこうしたの?」と問いかけることで、自分の考えを言語化する習慣がつきます。
また、行動観察や運動テストにおいては、特別な訓練よりも、日常生活での生活態度や集団でのふるまいがそのまま表れます。家庭でも「順番を守る」「話を最後まで聞く」「人の話に割り込まない」といった基本的なマナーを意識させることが、試験本番においても大きな支えになります。
運動面では、遊びの延長として取り組める運動を日常に取り入れておくとよいでしょう。走る・跳ぶ・投げるといった基本動作を楽しみながら身につけられるよう、外遊びや親子でのリズム運動などもおすすめです。
【慶應義塾横浜初等部】【慶應義塾横浜初等部】入学試験の全容をプロが徹底解説!まとめ
應義塾横浜初等部の入学試験は、一次試験のペーパーテストを突破しないと始まりません。その背景から、慶應義塾横浜初等部の対策=ペーパーテストと判断されがちですが、それは大きな誤りです。
慶應義塾横浜初等部が求めているのは、表面的な学力だけではありません。お子様自身の内面や生活態度、考える力を丁寧に見極めようとするものです。
そのため、「入試対策=勉強」と考えるのではなく、家庭での関わり方や日常生活そのものが重要な準備期間になります。
一次試験のペーパーテストで基礎的な思考力・地頭の良さを判断されたのちに見られる点は、慶應義塾の精神を体現できるお子様・ご家庭であるか否かです。「この子と6年間を過ごしたいと思えるかどうか」。
お子様が持つ素直さ、伸びしろ、そして自分の意見をしっかり持ちながら他者と協力する姿勢が評価されます。
当日の試験で大切なのは、無理に良い子を演じることではなく、「普段通りの自分を堂々と出すこと」。
そのためには、ご家庭での信頼関係や日常の習慣づくりが欠かせません。
試験内容や出題傾向を事前に把握したうえで、親子で安心して試験に臨めるよう、心と準備を整えていきましょう。
1.jpg)