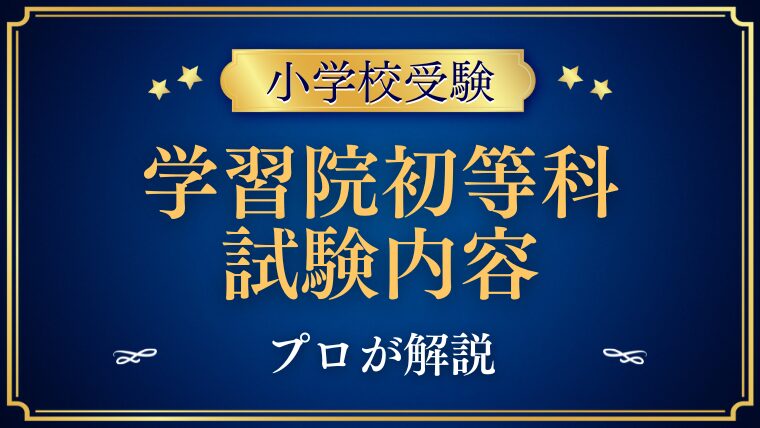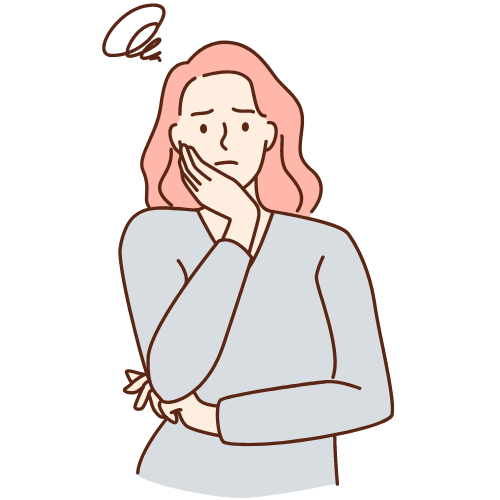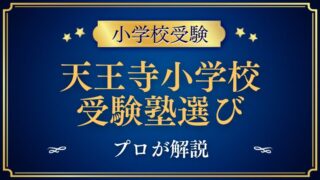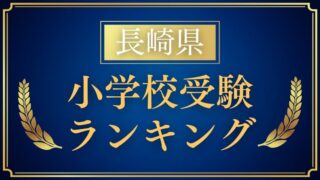学習院初等科を受験するんだけど、試験内容についてを知りたい!
皇族の為の初等教育機関として生まれ、長い歴史と伝統を守りながら優秀な卒業生を輩出する、都内私立小学校御三家の一角である学習院初等科。
多くの良家子女をお預かりする使命を持ちながらも、一般のご家庭にもフェアな考査を行い、毎年一定数の一般家庭のお子さまを入学させることでも有名です。
日本の文化や歴史を愛し、ひらがなの書き方をはじめ学びの基礎を徹底的に教育しながらも、夏期には体育を2時間連続にし遠泳の特訓を行ったり、ICT教育を積極的に採用する等、温故知新の精神を大切にしています。そんな伝統と変革を極める学習院初等科の考査は一体どのように進んでいくのでしょうか。
本記事では、学習院初等科の願書作成や面接対策で毎年合格者を輩出する筆者が解説をします。
【学習院初等科】の試験の流れ
学習院初等科の入学試験は、約4~5日間に分かれて行われます。月齢の低い順から振り分けられ、受験者(お子さま)は考査を、同じ時間に保護者は夫婦で面接を受けることになります。
入校すると、まず始めに受験者にクジをひくように指示があります。受験日当日は受験番号ではなく、このクジの順番で試験を受ける流れとなります。歴史ある名門校である学習院初等科には、卒業生や関係者も多く、事前に判明する受験番号順の考査となると何等かの忖度が行われるのではないか。そういった不透明さを排除し、公平に開かれた考査とするための学校側の正義と配慮により「当日クジの順番制」が採用されているとのことです。
その後、クジの番号順に振り分けられた待機室(1階の教室が多いようです)で受験者と保護者で待機します。試験官の先生が受験生を呼びにくると、そこで受験生と別れることになります。
少し遅れて、保護者も面接室の前に促され、順番に面接を受けていきます。終わるとまた元のお部屋に戻り、受験生が戻ってくるのを待ちます。
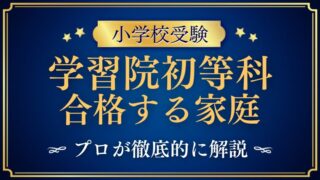
【学習院初等科】の試験の内容
それでは、ノンペーパーテストを中心に進む学習院初等科の試験内容を流れに沿って詳しく見ていきましょう。
学習院初等科では「真実を見分け、自分の考えを持つ子ども」を教育理念にあげ、自重互敬と豊かな人間関係を重視した教育を行っています。自分とは異なる考えを尊重することが自己肯定や成長に繋がるという考えの元、コミュニケーション姿勢や対話を重視した教育を行うことから、その考査も「対話」「協調」「学習院初等科にふさわしい振るまい」を大切にする内容になっています。
学習院初等科の試験内容について、分かりやすいように個別テスト①②、集団テスト①②と4つのカテゴリに分類して解説していますが、実際は個別テスト①と②は同時に行われます。また、集団テストに関しても①行動観察と②運動テストが一連の流れの中で行われます。ですので、実際は「個別テスト」と「集団テスト」の2つが行われ、お子様が試験を受けている間に「保護者面談」が同時進行で進んでいくとイメージしてください。
①個別テスト
学習院初等科の入学考査における個別テスト①では、受験者の思考力や記憶力が問われます。受験者は一人ずつ教室に入り、試験官(テスター)と1対1で対話をしながら問題に答える形式です。
出題内容
出題範囲は幅広く、以下のような内容が含まれます。
- 推理・思考
- 記憶(毎年出題される傾向)
- お話作り
- 説明力
- 生活習慣・常識
ペーパーテストのように答案に記入するのではなく、試験官の質問に対して自分の言葉で説明する力が求められます。また、学習院初等科の特徴として、具体物(実物の道具や模型など)を用いた出題が頻繁に行われる点が挙げられます。
試験の具体例
1. 記憶(ほぼ毎年出題)
絵や具体物を見て、それを記憶し、後で答える問題が出題されます。例えば、
- 絵の中に登場するものの形・色・並び順・方眼上の位置を記憶して答える。
- 位置関係に関する問題が高頻度で出題される。
2. お話の内容理解
短いお話(約1~2分)を聞き、その内容を理解した上で答える問題です。ただし、単に暗記するのではなく、
- 「どうしてそうしたのかな?」
- 「なんでそう思ったの?」
- 「あなたならどうしますか?」
といった気持ちの推測や自分の意見を求める質問が多く出されます。
3. 口頭質問(説明と作業)
具体物を用いた作業や説明を求められます。
- 積み木やパターンブロックを指示通りに並べる・同じ形を再現する。
- 穴のあいた積み木やひもを使い、見本通りの形を作る。
- 果物や野菜の模型を使った質問
- 「この果物(野菜)が育つ季節を知っていますか?」
- 「食べたことはありますか?」
- 「どんな味がしますか?」
- 「表面の手触りはどのような感じですか?」
- 「どんな料理に使いますか?」
試験官の質問に対し、単に答えるのではなく、敬語を交えながら、豊富な語彙を使って説明できることが重要視されます。
求められる力
学習院初等科の個別テストでは、ペーパーテストを解く知識を前提としながら、以下の能力が求められます。
- 自分の言葉で説明する力
- 豊富な語彙力と適切な敬語の使用
- 具体物を使った作業を正確にこなす力
試験官との対話形式のため、表現力や対話力が大きな評価ポイントとなります。普段から会話の中で、考えを整理して話す練習を積んでおくことが大切です。
②集団テスト
学習院初等科の集団テストでは、5~10人程度のグループに分かれ、ゲームや制作活動を行います。試験官は、子どもたちの周囲との関わり方、作業への取り組み姿勢、集中力などを観察し、評価します。
また、個別テスト②でも解説した通り、所作の丁寧さが重要なポイントとなります。
試験のポイント
1. 所作や丁寧さ
- 説明を一度で正しく聞き取ることが求められます。
- ゲームや制作で使用する道具を乱雑に扱わず、大切に使うことが重要です。
- 夢中になりすぎてはしゃぎすぎたり、乱暴な言動をとることは避けるべきです。
2. お友達との関わり方
- 相手を尊重し、協力して仲良く進めることができるか。
- 相手の話をしっかり聞く姿勢があるか。
- 時には自分が折れることができるか。
試験官は、子どもが相互尊重の精神を持っているかを確認しています。
3. ルールを守る力
- 試験官の指示をしっかり聞き、それを守った上で楽しんでいるか。
- 「聞く力」と「実行力」の両方が求められます。
具体的な試験内容
1. 行動観察
3~4人のグループに分かれ、協力が必要な遊びを行います。
過去に出題された例
- 風船運び:みんなで工夫して風船を運ぶ。
- ごっこ遊び:役割を決め、協力しながら遊ぶ。
- 風呂敷運び:大きな風呂敷の四隅を1人ずつ持ち、その上にボールや道具を乗せて運ぶ。
コロナ禍では1人でお手玉を運ぶような考査に変更されていましたが、2022年度以降は徐々に従来の内容に戻る傾向にあります。学習院初等科でも、今後は従来の協力型の課題が増えると予想されています。
2. 待ち時間の行動
テストの合間や待ち時間には、モニターにディズニー映画などが流され、「静かに見て待つように」と指示が出されます。
- つい笑ってしまったり、隣の子と話してしまう受験者が多いですが、これも試験の一部です。
- 試験官の指示を守り、静かに待つことが大切になります。
学習院初等科の集団テストでは、協調性やルールを守る力、丁寧な所作が重視されます。単にゲームが上手なだけではなく、周囲との関わり方や態度も評価されるため、日頃から丁寧な行動や協力の大切さを意識しておくことが重要です。
集団テスト②(運動)
集団テストの中で、ゲームや制作に合わせて運動関連のテストも出題されます。ボールを使った運動や屈伸運動、音楽に合わせたリズム体操など。小学校受験対策をしてきたお子様にとっては簡単なものが出題されます。しかし、この運動テストでも重要なのは集団テスト①(行動観察)と同様「丁寧な所作」、「お友達を尊重し協力する姿勢」、「指示を聞く力」、そして「実行力」です。勝敗にこだわり、上手に行うことに夢中になってしまい自分勝手な行動を取ったり乱暴なしぐさになってしまうと良い結果は得られません。学習院初等科の集団テストで重要となるのは、結果よりも「周りと強調して丁寧に進める意識」であることを決して忘れないでください。
④保護者面接
受験生が考査を受けている間に、保護者面接が行われます。男女2人の面接官による面接は約5~7分と大変短く、質問も2問程度となります。ご夫婦で参加される場合は、お父さまに1問、お母さまに1問程度。質問内容も、志望動機やお子さまのキャラクターに対するようなオーソドックスな内容になります。短い時間でしっかり志望理由や学習院初等科への想いを伝えられるよう準備することが大切です。
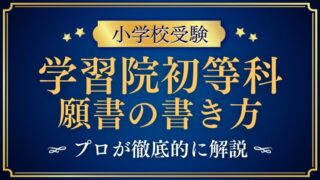

ご自宅で取り組める学習院初等科の受験対策
プロの解説によって、学習院初等科の試験内容は十分理解できたかと思います。ここから、ご家庭で明日から取り組める学習院初等科の受験対策をご紹介します。
「何事もゆっくりやってみる」に挑戦をする
小学校受験に取り組む如何に関わらず、子育て中というのは常に「急いで!早く!」の繰り返しです。けれど、学習院初等科を目指すご家庭であれば、お子様に丁寧な身のこなしを身に付けさせるのは必須です。なので、あえて真逆の「何事もゆっくりやってみる」に挑戦することが合格への第一歩となります。
お子様というのは「早く」と「丁寧に」を両立できません。急げば雑になるし、丁寧にやれば時間がかかるものです。しかし、先にスピードを身に付けても丁寧さにはつながりませんが、先に丁寧さを身に付ければその身のこなしをスピードアップさせることは十分に可能なのです。最初に丁寧を極めることは、じっくり時間をかけて取り組むことで「丁寧とはどういうことなのか」を学ぶことにつながります。それに付き合う親御様には負担の大きなものになりますが、例えば親御様の夏休み一週間だけでも十分ですので、あえてゆっくり時間をかけて日常生活を送ってみてください。たった一週間でも驚く程お子様の身のこなしが変わっていきますよ。
絵本の読み聞かせ
学習院初等科が求める「豊かな表現力」や「説明する力」を身に付けるには、言葉を増やすことが土台になります。それに直結するのが絵本の読み聞かせです。
小学校受験準備中であれば、毎日読み聞かせに取り組まれているとは思いますが、ぜひ日本で長く愛される昔ながらの絵本をラインナップに取り入れてみてください。
平成以降に出版された絵本はポップな作風で展開や台詞回しも面白いものが多く、お子様が「読書の楽しさ」を知ることに役立ちます。けれど、日本らしい美しい世界や表現に触れられるのは、やはり昔ながらの絵本です。そして、そういった美しい表現を知れば知る程、お子様の発する言葉も洗練されていくのです。
親御様がお子様が楽しめる作品の中に、いくつか昔ながらの絵本も取り入れてくださいね。
初めましてのお友達と遊ぶ機会を設ける
学習院初等科では、お互いを認め合い尊重し合う気持ちを大切にします。そのような姿勢を学ぶには、とにかく場数を踏むことが重要です。小学校受験準備中のご家庭であれば、お受験に強いと言われる幼稚園に通い、お教室で行動観察の授業に取り組まれていると思います。しかし、それだけの対策や経験では不十分なのです。
お受験に強い幼稚園というのは、躾に厳しく指導力も一流です。また、小学校受験を志すご家庭が集まっているので、そもそも同様の価値観の元育てられたお子様が揃いがちです。お教室も同様ですし、顔を合わせるお友達も固定化するでしょう。しかし、そもそも似た価値観で育てられたお子様が集まっている場所で期待通りの行動がとれるのは、ある種当たり前なのです。
考査本番でも幼稚園やお教室と同等の行動がとれるようにするためには、早い段階から「小学校受験に特化した訓練がなされていない初対面のお子様」と遊ぶ機会を積極的に設けることです。
小学校受験の準備をしていない=乱暴な振る舞いをしたり場を乱すような行動をする。なんてことは決してありません。(もしそのようなお考えをお持ちであれば、ご自身がいささか慢心されていると思わざるを得ません。)けれど、訓練されていないが故に、訓練されたお子様からすれば想像を超えるような言動を発することが度々あります。
「おもちゃの取り合いになったら”どうぞ”って言うのが当たり前なんじゃないの?」
「意見が分かれたら”あなたはどう思う?”って聞くんじゃないの?」
時にこのように戸惑うこともあるかもしれません。
しかし、たとえどんな相手と対峙しようとも「相手を尊重し理解しようとする」姿勢を貫くことはできます。そして、それを自分のものにできたと言えるのは、どんな相手や状況であってもそうできるようになった瞬間です。
様々なタイプの子どもたちに揉まれながらも一緒に楽しく遊ぶ経験を積むことが、お子様を一歩も二歩も成長させることになりますよ。
【学習院初等科】試験内容と対策をプロが解説まとめ
学習院初等科の入学試験は、例年10倍近い高倍率を誇る人気試験であり、その難易度の高さでも知られています。試験内容や対策について、ここまでご紹介してきましたが、どんな難関校を受験する場合でも、日常生活の延長線上で知識や振る舞いを身につけることが何より大切です。
親御様の工夫次第で、お子さまの能力は何倍にも向上します。ぜひプロの解説を参考にしながら、日常生活の中で無理なく取り入れてみてください。
学習院初等科は、「都内私立小学校の御三家」と称される名門校であり、長い歴史と伝統を大切にしています。その入試では、お子さまとじっくり向き合い、個性や人間性を深く理解しようとする姿勢が特徴です。
求められるのは、「自分の言葉で話し、意見を述べられる力」と「優しく、丁寧で、穏やかな心を持つこと」。
学習院初等科の考査内容をしっかりと研究し、日々の生活の中で自然に身につけながら、試験に臨んでください。お子さまが自分らしく輝けるよう、応援しています!
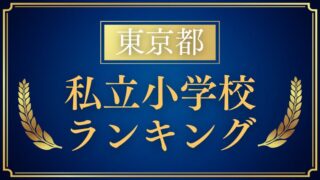
1.jpg)