青山学院初等部は、学校法人青山学院の理念に基づいた、キリスト教主義の精神を大切にする大学附属の私立小学校です。
東京都渋谷区という都心にありながら、恵比寿の緑豊かな環境に囲まれたキャンパスで、児童たちは心身ともにバランスよく育まれていきます。
体育・芸術・国際交流といった多様な分野の学びにも力を入れており、お子様の個性と可能性を丁寧に伸ばす教育が魅力のひとつ。その教育環境に魅了され、青山学院初等部への入学を希望するご家庭は年々増加しており、学校説明会や見学会には多くの保護者が関心を寄せています。
【青山学院初等部】学校説明会や見学イベントは実施されているのか
青山学院初等部では、例年、保護者向けに学校説明会やオープンスクールなどの見学イベントが実施されています。
それぞれのイベントには独自の目的と内容があり、青山学院初等部の魅力や教育理念を深く知るための貴重な機会となっています。
学校説明会
米山記念礼拝堂で年に2回ほど開催される学校説明会は、青山学院初等部の理念や教育の全体像を知る上で非常に貴重な機会です。
まず、静かな礼拝で心を落ち着けることからスタートし、青山学院らしい「心の教育」の一端に触れることができます。その後、校長先生や教職員の方々から、学校の歴史や教育方針、日常の授業内容に至るまで、幅広い説明が丁寧に行われます。
説明の内容は具体的かつ実践的で、「どのように子どもたちの心と学力を育てていくのか」がよく分かる構成となっています。
加えて、後半の校内見学では、実際の教室や図工室、音楽室、そしてICT機器が導入されている特別教室などを間近で見ることができ、青山学院初等部の教育環境の充実ぶりを実感することができます。
<2024年度 実施例>
第1部:青山学院初等部の教育方針・教育の実際についての説明
第2部:校内見学(1年生の生活、専科の学習、宿泊行事、給食、ICT活用など)
オープンスクール
青山学院初等部のオープンスクールは、保護者とお子様がともに校内を歩きながら、青山学院初等部の学びの姿を体感できるイベントです。
礼拝堂での全体礼拝から始まり、その後は校舎内の各所に設けられた体験ブースを自由に回るスタイルが基本。理科の実験や図工の作品制作、音楽のミニレッスンなど、教科ごとに工夫されたプログラムが用意されており、子どもたちも楽しみながら自然に学校の雰囲気に馴染むことができます。
このイベントでは、保護者も児童の様子を見守りながら、校内の掲示物や先生方の雰囲気を感じ取り、初等部の空気感をリアルに知ることができます。説明会ではわからない“肌感覚”を得られるのが、オープンスクールの最大の魅力と言えるでしょう。
例年、6月下旬〜7月初旬にかけて開催されており、午前・午後の2部制で実施。どちらも同じ内容で、都合の良い時間帯を選んで参加申込を行います。
イベントに参加する際の注意事項
青山学院初等部の説明会・オープンスクールに参加するにあたっては、学校側の決めたルールをしっかりと理解し、誠実な姿勢で臨むことが重要です。
人気校であるため、定員に限りがあり、事前申込制での運営が徹底されています。申し込んだ回にのみ参加できる仕組みで、無断参加や別時間帯への振替は認められていません。
また、セキュリティ強化の一環として、来校者には身分証明書(運転免許証や健康保険証など)の提示が求められます。撮影や録音は禁止されており、参加中のマナーにも注意が必要です。
お子様が同行する場合は、動きやすい服装・運動靴の着用が推奨され、校内の雰囲気に馴染みやすくなるよう配慮がなされています。施設内には駐車場がないため、自家用車での来校はできず、公共交通機関の利用が原則です。
水筒持参による水分補給の推奨、感染症予防のための体調管理など、学校全体が安全で円滑にイベントを運営できるよう工夫されています。これらのルールを守ることが、今後もこのような見学の機会が継続されるかどうかに関わってくるといっても過言ではありません。
入試説明会
青山学院初等部の入試説明会は、実際に出願したご家庭だけが参加できる重要な場であり、入学試験当日に向けた具体的な情報が得られます。試験当日の流れや注意事項、集合場所や持ち物など、受験に直結する詳細が一挙に説明されるため、参加者にとっては聞き逃せない内容ばかりです。
例年、対面形式またはオンライン形式で実施され、説明のトーンも非常に実務的かつ具体的です。事前に確認しておきたい点や、不安に思っていた内容について直接情報を得られる貴重な機会となります。
服装に関しても、試験当日の雰囲気を意識し、きちんとした印象を与えるスタイルでの参加が推奨されます。ご家庭としての雰囲気が表れる場でもあるため、お子様と同席する際は、話し方や立ち居振る舞い、表情にも細やかな配慮が必要です。
また、過去の参加者からは「入試説明会での内容をもとに、試験日当日の動線や段取りを予行演習できたことが大きかった」という声も多く、事前に把握しておくことで当日の緊張を軽減できるという意味でも、大きな意義を持つ説明会といえるでしょう。

【コラム】青山学院初等部の学校行事を見学することはできるのか?
青山学院初等部では、「運動会」「ファミリーフェア」「クリスマスツリー点火祭」など、数々の魅力的な行事が行われています。しかし、それらの多くは在校生・関係者向けであり、一般公開されることはほとんどありません。
学校のリアルな様子や子どもたちの生活を見学できる貴重な機会が限られているため、在校生や卒業生のご家族などから話を聞くなど、日頃からつながりを大切にして情報収集をしておくことが望まれます。
https://ukaruco.jp/syoujyu/%e3%80%80aoyamagakuin-undokai/
【青山学院初等部】学校説明会と学校見学会以外で学校を知る方法
青山学院初等部は、その人気の高さから見学機会が限られており、限られたイベントに参加するだけでは全貌をつかむことが難しいのが現状です。そのため、保護者が主体的に情報を取りにいく姿勢が何よりも重要です。
学校説明会やオープンスクール以外でも、学校の方針や児童の様子、日常の空気感を知る手段はいくつか存在します。ここでは、お受験準備の一環としてぜひ取り入れたい、実践的で信頼性の高い4つの方法をご紹介します。
合同説明会に参加する
青山学院初等部は、限られた合同説明会に資料参加という形で関わることがあります。たとえば「東京私立小学校展」や「キリスト教学校合同フェア」などが代表的で、学校のパンフレットや概要資料が配布されることが多いです。
直接先生に話を聞ける機会は少ないかもしれませんが、学校の教育理念や特色、年間行事の様子などが書かれた資料は、非常に有用な参考情報となります。実際に資料を手に取ってみると、学校ごとの雰囲気や価値観が細部に表れており、自宅でじっくり読み返すことで入試の志望理由づくりにも役立ちます。
また、他校と比較して見えてくる青山学院初等部の独自性にも気づくことができ、学校選びの視野を広げる機会にもなります。
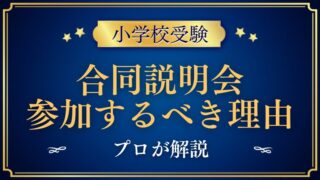
在校生のご家族とつながる
青山学院初等部の在校生ご家族とのつながりを持つことは、学校について最もリアルな情報を得られる手段のひとつです。
実際に通っているお子様やその保護者の方から直接お話を聞くことで、公式サイトやパンフレットでは伝わらない学校の実態や雰囲気、先生方の指導方針、児童の様子などを知ることができます。
また、受験準備の進め方や、面接や試験当日の体験談、日頃の学校生活に必要な物品や心構えなども、細かな部分まで聞くことができる貴重なチャンスです。ただし、いきなり踏み込んだ質問をするのではなく、まずは丁寧に関係を築き、信頼関係を深めてから話を伺うようにしましょう。
得た情報はあくまで一例であることを踏まえつつも、そのご家庭が感じている“リアルな青山学院初等部”は、非常に参考になるはずです。
青山学院と縁のある知人を頼る
青山学院大学・中等部・高等部など、青山学院系列の出身者やその家族、教職員経験者など、青山学院に縁のある知人を通じて情報を得るという方法も有効です。
青山学院初等部は、伝統校として幅広いネットワークを持つため、意外なつながりが見つかることもあります。
たとえば、勤務先の同僚、同窓会で再会した旧友、ママ友ネットワークなどに“青学関係者”が含まれていることもあるでしょう。そうした人から直接情報を得ることで、学校の文化や求められる子ども像、保護者としての心構えなど、受験の参考になる情報が得られます。
ただし、ここでも大切なのは、関係性を急がず、誠実なコミュニケーションを心がけることです。
習い事などを通じて交流を持つ
英語、ピアノ、水泳、体操などの習い事は、青山学院初等部の在校生やその兄弟と自然に接点を持てる場でもあります。
実際に多くの受験家庭が、志望校と親和性の高い教育スタイルの習い事に通わせる傾向にあるため、そうした場は貴重な情報収集のチャンスになります。
同じ教室で学ぶうちに、お子様同士が仲良くなり、そこから保護者同士の交流が生まれることも珍しくありません。無理に情報を得ようとするのではなく、あくまでも自然な流れの中で関係性を育てることが重要です。
信頼関係が築けた段階で学校の話題になった際には、さりげなく質問を投げかけてみると良いでしょう。その際は、話してもらえたことに感謝を伝える姿勢を忘れずに。
【青山学院初等部】学校説明会や見学イベントは行われるのか?プロが徹底解説!まとめ
青山学院初等部の学校説明会やオープンスクールは、限られた日程でしか開催されない貴重な機会です。参加には事前の準備とマナーが求められます。
とはいえ、それらのイベントに参加するだけでは、青山学院初等部のすべてを知ることはできません。
だからこそ、ネットワークや縁を大切にしながら、さまざまな視点から学校の姿を捉えることが大切です。入試に向けて努力を重ねるお子様に対し、保護者ができる最大限のサポートは、情報と理解に裏打ちされた“戦略的な準備”と言えるでしょう。
1.jpg)



























