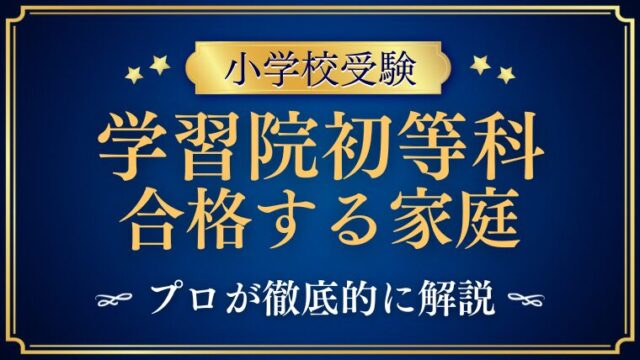塾長
Contents【青山学院初等部】ペーパーテスト試験とは
青山学院初等部の入試は2日間にわたって行われ、初日の適性検査Aにてペーパーテストが実施されます。問題はグループごとに教室で行われ、音声による指示に従って一斉に解く形式です。
出題は、「話の記憶」「数量」「常識」「言語」「図形」「推理・思考」など多岐にわたっており、単なる知識を問うのではなく、記憶力、集中力、思考の柔軟性、聞き取る力などを総合的に評価する内容です。
年を追うごとに設問はより工夫され、2025年度には一部問題に「仲間分け」や「推理力」などの応用的な思考を必要とする内容も含まれるようになりました。これにより、形式的な暗記や演習の繰り返しだけでは対応しきれない難しさが増しています。
 【完全保存版】青山学院初等部受験まとめ|入試・倍率・願書・学費・生活まで全網羅 \合格率97%/
青山学院初等部
オーダーメイド願書作成
詳しくはこちらをクリック ...
【完全保存版】青山学院初等部受験まとめ|入試・倍率・願書・学費・生活まで全網羅 \合格率97%/
青山学院初等部
オーダーメイド願書作成
詳しくはこちらをクリック ...
【青山学院初等部】ペーパーテスト試験が出題されるようになった理由
青山学院初等部においてペーパーテストが導入された背景には、時代の変化に伴う教育ニーズの多様化と、入学後の学びをより円滑にスタートさせるための“準備段階としての資質”を見極める必要性があったと考えられます。
従来、同校は「知識偏重ではない、人格重視の選考」を掲げ、行動観察や制作、集団活動といった多面的なアプローチでお子様の本質を評価してきました。しかし、社会全体の教育環境が大きく変化し、お子様たちの生活体験の質も家庭ごとにばらつきが生じる中で、「一定の基礎的な言語理解や数量感覚が備わっているか」を事前に把握する必要が高まったのです。
また、幼稚園・初等部からの一貫教育を担う青山学院においては、進学先となる附属中学校・高等学校との接続面も無視できません。近年、附属中高からは「基礎学力をしっかりと身につけた児童の育成」を求める声も上がっており、それに応える形で、初等部でも学力面での一定の土台づくりが意識され始めています。
ただし、これは「競争的な学習」への移行を意味するものではありません。青山学院初等部の教育はあくまでも“個を活かす”ことを大切にしており、一般的な公立小学校のように通信簿で評価を付けたり、テストで順位をつけたりといったことは一切行われていません。
そのような環境の中でも、お子様たちが学びに対して前向きに取り組み、自らの力で考えることに喜びを見出せるよう、教職員は日々さまざまな工夫と努力を重ねています。
ペーパーテストもまた、その教育方針を損なうものではなく、むしろ「お子様自身の学びのスタートラインを知る」ための温かく前向きな評価の一環として位置づけられているのです。形式的な受験対策では太刀打ちできない構成になっているのも、青山学院らしい“本質を問う入試姿勢”のあらわれです。
【青山学院初等部】ペーパーテストの試験内容
以下は青山学院初等部で過去に実施されたペーパーテストの代表的な課題例です。年によって構成や設問の形式は多少異なりますが、出題の意図や難易度は一貫しており、試験の本質を理解するための参考として非常に有効です。
※青山学院初等部の適性検査A(ペーパーテスト)は、実施日、実施グループによって内容が一部異なります。そのため、こちらに掲載した試験内容もあくまで参考としてご利用ください。
2025年度実施ペーパーテスト
■主な出題項目
お話の記憶(男女別)
数量・常識(ボールの数や並び順)
言語(語頭音、語後音/しりとり/文字数)
常識(生活習慣・仲間分け)
点図形(プロジェクターに写された絵を書く)
絵の記憶(イラストを15秒間見て回答)
構成・推理・思考(図形回転や位置判断、図形変化の想像など)
■特徴
語彙力や記憶力だけでなく、「図形の位置関係」や「仲間分けの根拠を考える力」「音声指示の理解力」といった、複数の力を同時に求める設問が多く見られました。
特に、数量や図形に関する問題では、情報を一度に把握して正確に処理しなければならず、思考の柔軟性や情報整理のスキルが問われています。
また、絵の記憶に関しては、一瞬で見せられたイラストの細部を捉える観察力や、見たものを正確に再現する力が重要となります。音声での出題が主となるため、設問の聞き取りミスを防ぐ集中力や、落ち着いて待機・対応できる態度も評価対象となっていることがうかがえます。
全体として、受験者の“学びへの姿勢”そのものが浮き彫りになるような、奥行きのある出題が特徴的です。
2024年度実施ペーパーテスト
■主な出題項目
お話の記憶(男女別)
数量(野菜の数)
常識(季節、生活習慣、仲間訳)
言語(しりとり・語彙力)
点図形・図形記憶
絵の記憶(映像提示後の記憶)
推理・思考(図形の回転・重ね図形・方向推理)
■特徴
この年度では、ストーリー性のある設問が多く見られ、「お話の記憶」や「絵の記憶」といった、集中力とイメージ力を総合的に問う問題が中心でした。
単なる記憶ではなく、「順番」「登場人物の特徴」「起きた出来事の関係性」など、内容の構造を理解して記憶する力が求められています。数量や図形の出題も、図形の回転や組み合わせなど、視点を変えて考える応用力を必要とする内容でした。
また、生活常識の設問では、家庭や園生活でどのような体験をしてきたかが問われるため、日常的な親子の会話や経験の積み重ねが得点につながるケースもあります。
出題内容からは、短期間の詰め込み対策では太刀打ちできず、「ことばに強く、生活力のあるお子様」が高く評価される傾向が読み取れます。
2023年度実施ペーパーテスト
■主な出題項目
お話の記憶(男女別)
言語(語彙/語尾/しりとり)
数量(仲間分け・足し算的な思考)
常識(生活・交通ルール・仲間探し・仲間訳)
点図形・絵の記憶(視覚記憶)
推理・構成(図形を使った法則性)
■特徴
この年は、「聞く→理解する→手を動かす」という一連のプロセスが滑らかに行えるかどうかが、大きな評価ポイントとなっていました。
特に、「聞いた話を頭の中でイメージ化し、それを再現・記述する」力や、「どの選択肢が適切かを論理的に選ぶ」推理力など、受験者自身の中で情報を処理する能力が重視されています。
図形や構成の問題は、視覚的に似たパーツの中から違いを見つけたり、完成図を想像して選ぶといった、空間認識や先を読む力も必要とされました。問題文に含まれる微妙な言葉の違いを聞き取れるかも重要で、聴覚の感度や言語理解力が合否を分けた可能性もあります。
また、どの設問においても、「落ち着いて最後までやり切ること」が重要視されており、普段からの姿勢が表れる設計になっていた印象です。
【青山学院初等部】家庭でできるペーパーテスト対策
青山学院初等部をはじめとする、私立小学校受験におけるペーパーテスト対策というのは、単に机に座って大量のプリントを解くだけでは十分とは言えません。
思考力、観察力、集中力など、幅広い力を問う出題が増えているため、日常生活の中に取り入れられる「体験型の学び」や「五感を使った学習」がより効果的とされています。ここでは、家庭で手軽にできる3つの取り組みを紹介します。
絵本の読み聞かせ+要約練習で「話の記憶力」を伸ばす
青山学院初等部のペーパーテストでは、毎年必ず「お話の記憶」に関する問題が出題されています。ここで問われているのは、ただ物語の内容を覚えることではなく、誰が・どこで・何をしたかを整理しながら聞き取る力や、細かい表現・語彙の記憶です。
日常でできるおすすめの対策は「絵本の読み聞かせ+要約練習」。読み聞かせのあとで「どんな話だった?」「どこが面白かった?」「何をしたお話だったかな?」と問いかけ、要点をまとめて話す練習を重ねることで、耳からのインプットと記憶の保持力が自然に鍛えられます。
慣れてきたら、聞いた内容を絵で描くなどアウトプットの工夫も取り入れると、さらに記憶が定着しやすくなります。
お買い物やお手伝いで「数量感覚」と「観察力」を育てる
数量に関する設問では、数の多少や順番、並び方を正しく認識する力が求められます。家庭内で自然に数量感覚を身につけるには、買い物体験や日常のお手伝いが非常に効果的です。
たとえば、スーパーでの「リンゴは全部で何個ある?」「赤い野菜はどれ?」といった声かけや、食事準備で「お皿を3つ出して」「スプーンは1人何本?」など具体的な数に触れるシーンを積極的に作ると、数のイメージが言語化され、実際のペーパーでも役立ちます。
また、同じ物を並べる・グループ分けをする・大きさ順に並べるといった作業も、数量と空間認識の両方を養うことにつながります。数を楽しむ会話が習慣化されれば、無理なく力を伸ばせるでしょう。
h3 親子で「しりとり」や「仲間分けあそび」で語彙力アップ
言語に関する出題は、語彙の豊かさや言葉の構造への理解を試す内容が中心です。「しりとり」や「仲間分けあそび」は、遊びながら語彙力を高めるのに最適な手段です。
しりとりでは「3文字以上」「食べ物だけ」「ひらがなで考えてみよう」といったルールを加えると、難易度が上がり自然に語彙が広がります。
一方、「果物チームと野菜チームに分けてみよう」「動物と乗り物、どっちに入るかな?」といった仲間分けあそびでは、分類の視点や論理的な思考が育ちます。また、カードやイラストを使って「どれが違うかな?なぜそう思った?」と理由まで言わせる習慣をつけると、発言力や表現力にもつながっていきます。机の上だけでなく、リビングでもキッチンでもできる日常学習としておすすめです。
【青山学院初等部】ペーパーテスト試験内容や対策方法についてプロが徹底解説!まとめ
青山学院初等部のペーパーテストは、単なる学力テストではなく、「聞く力」「考える力」「記憶する力」など、お子様の学びの土台となる総合的な力を見極めるために設けられています。
年々その内容は高度化し、表面的な演習だけでは太刀打ちできない構成へと進化しています。だからこそ、ご家庭での日常的な体験や親子のやり取りの中にこそ、大きなヒントが隠されています。
の上だけでなく、日々の暮らしの中で「楽しく、無理なく」学びを深めることが、青山学院初等部の入試を突破する近道なのです。
青山学院初等部の入試は2日間にわたって行われ、初日の適性検査Aにてペーパーテストが実施されます。問題はグループごとに教室で行われ、音声による指示に従って一斉に解く形式です。

青山学院初等部においてペーパーテストが導入された背景には、時代の変化に伴う教育ニーズの多様化と、入学後の学びをより円滑にスタートさせるための“準備段階としての資質”を見極める必要性があったと考えられます。
以下は青山学院初等部で過去に実施されたペーパーテストの代表的な課題例です。年によって構成や設問の形式は多少異なりますが、出題の意図や難易度は一貫しており、試験の本質を理解するための参考として非常に有効です。
青山学院初等部のペーパーテストは、単なる学力テストではなく、「聞く力」「考える力」「記憶する力」など、お子様の学びの土台となる総合的な力を見極めるために設けられています。
1.jpg)