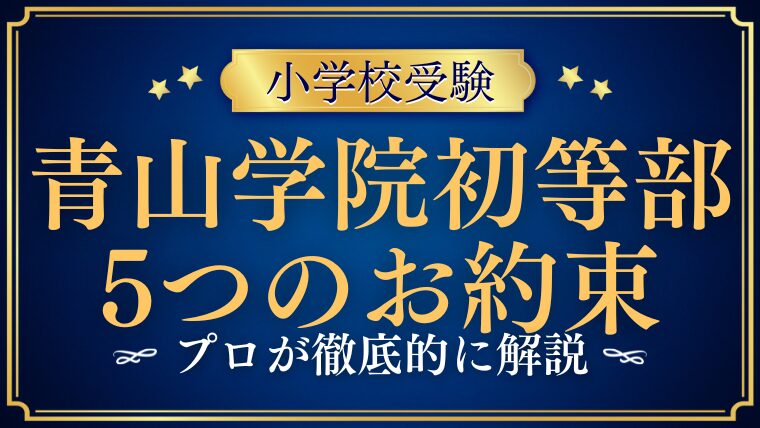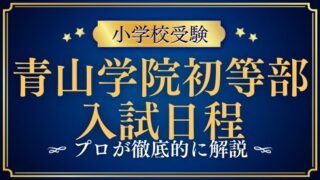青山学院初等部は、長い歴史と伝統を培う大学付属一貫校です。その成り立ちは、明治初期にアメリカから演帖された三人の宗教宗者に始まり、昭和12年に米山梅吉により開校された緑岡小学校に縁を発します。
米山梅吉は「人にしてもらいたいことは、自分も人にしなさい」という信条を返信に、お子様たちに日々教え続けました。この思想は、マタイ福音書第7章12節に基づいており、現在の青山学院初等部の教育の根幹となっています。
この思いを日常生活の中で実践するための施策として、青山学院初等部の児童手帳に記述されているのが「5つのお約束」です。
【青山学院初等部】「5つのお約束」とは
青山学院初等部で大切にされる「5つのお約束」は、お子様たちの社会性や人間性を深く根付かせるための指針となっています。ひとつひとつの意味や、その言葉に込められた想いをご紹介します。
しんせつにします
しょうじきにします
れいぎただしくします
よく考えてします
じぶんのことはじぶんでします
「しんせつにします」
他者への思いやりや優しさを持つことは、社会生活を送るうえで欠かせない基本です。青山学院初等部では、友達が困っているときに助けの手を差し伸べたり、誰かの気持ちを考えて行動したりすることの大切さを繰り返し伝えています。
小さな場面でも「今、相手はどう感じているかな」と考えながら行動できる力を、日常の積み重ねの中で育てていきます。
「しょうじきにします」
正直であることは、信頼関係を築くうえで最も重要な資質のひとつです。間違えたとき、失敗したときに隠したり取り繕ったりせず、自分の言動に責任を持って正直に向き合う姿勢を身につけます。
青山学院初等部では、結果よりも過程を大切にし、「正直であることは素晴らしいこと」と自信を持って行動できるお子様たちを育てています。
「れいぎただしくします」
礼儀正しさは、他者を尊重する心の表れです。青山学院初等部では、挨拶や言葉遣い、立ち居振る舞いの中に、相手への敬意を込めることの大切さを教えています。
型通りの礼儀だけでなく、心のこもったふるまいを重視し、日常の一つ一つの行動を通じて、自然と礼儀が身についていくよう丁寧に指導されています。
「よく考えてします」
行動する前に立ち止まり、よく考える習慣を身につけることは、判断力や責任感を育てる基礎となります。
青山学院初等部では、先生の指示をただ待つのではなく、自分で考えて次に取るべき行動を選び取ることを促しています。何かを決めるときに「これでいいのか?」と一度自分に問いかける習慣を、小さな場面から積み上げています。
「じぶんのことはじぶんでします」
自立心を育み、自分で考え行動する能力を伸ばすことは、青山学院初等部で特に大切にされている教育方針です。
衣服の管理、持ち物の整理、困ったときにまず自分で考えるなど、小さな「自分でやる」の積み重ねが大きな自信となります。親が先回りせず、お子様自身に経験させ、挑戦する機会を大切にすることが求められます。

【青山学院初等部】「5つのお約束」を定める理由
これらの「5つのお約束」は、単にお子様たちに守らせるべきルールとして表面的に教えられるものではありません。
青山学院初等部では、日々の生活の中で一つひとつの場面に応じて自然に実践できるよう、繰り返し丁寧に指導が行われています。
たとえば、朝の挨拶、授業中の態度、友達との関わり方など、さまざまな日常の中で「今この場面ではどう振る舞うのがよいか」を自分で考え、行動する力を育んでいきます。これは単なるマナー教育に留まるものではなく、お子様自身が主体的に周囲を思いやり、自らを律する力を養うためのものです。
こうした積み重ねが、将来的には他者と豊かに関わり合いながら、自立して生きるための土台となり、人格形成を支える大切な柱となっています。
【青山学院初等部】「5つのお約束」が求められる場面
青山学院初等部では、「5つのお約束」は協調性の教育や社会性育成の一環として日常的に求められます。また、学校生活のあらゆる場面で実践されることを前提とした指導が行われています。
h3 登園・登校時に求められる「5つのお約束」
登園・登校時には、「5つのお約束」が自然に表れているかがよく見られます。たとえば、玄関で先生や友達にきちんと挨拶ができるか、自分の持ち物を自分で管理できるかといった点です。
列に並ぶときは周囲に配慮して静かに行動すること、困っている友達を見かけたら声をかけることなども重要な観察ポイントになります。
特に青山学院初等部では、生活の始まりを丁寧にできるお子様かどうかが重視されるため、日常の中で基本的な生活習慣と、思いやりのある行動を徹底して身につけさせておくことが大切です。
集団活動・グループワークで求められる「5つのお約束」
集団での活動中は、「5つのお約束」がより高度に求められます。話を聞くときの姿勢、発言のタイミング、周囲への配慮など、協調性と主体性のバランスが問われます。
たとえば、話し合いの場面で自分の意見をきちんと述べつつも、他の子の意見にも耳を傾ける姿勢が求められます。また、順番を守る、役割を果たす、困ったときに自分で解決を試みるなど、普段の行動ににじみ出る「思いやり」「自律心」「礼儀正しさ」が試されます。
ご家庭で日頃から「みんなの中でどう振る舞うか」を意識づけることが重要です。
トラブル発生時に求められる「5つのお約束」
トラブルが起きたときこそ、「5つのお約束」が本当に身についているかが明らかになります。
たとえば、友達と意見がぶつかった際、怒ったり泣いたりするだけでなく、自分の気持ちを言葉で伝えたり、相手の話を聞こうとする姿勢があるかが大切です。また、問題を他人任せにせず、自分なりに考えて行動しようとする様子も評価されます。
青山学院初等部では、失敗や衝突そのものを否定するのではなく、その後の対応力を重視するため、家庭でも「困ったときこそ丁寧に」を合言葉に練習を重ねておきたいところです。
【青山学院初等部】ご家庭でできる、5つのお約束を身に付ける為の方法
青山学院初等部の合格を志すうえで、5つのお約束を身に付けることは欠かせません。ここからは、ご家庭生活の中で「5つのお約束」を身に付ける為の方法を具体的にご紹介します。お忙しい受験準備期間中でも、気軽かつ日常生活の中で取り組めるものばかりです。ぜひ楽しみながら気軽にやってみてくださいね。
日々の声かけと行動で「思いやり」を育てる
「思いやり」は特別な指導よりも、日常生活の中で自然と育まれます。たとえばご家族の誰かが困っているときに「どうしたの?」と声をかけたり、「ありがとう」と感謝を伝えたりする習慣を意識して作りましょう。
親御様自身が手本となる行動を取ることも非常に効果的です。お子様が他者の気持ちに気づき、寄り添うことができるようになるためには、小さな場面での積み重ねが何より大切です。
毎日の会話や行動を通して「他人を思いやる喜び」を感じさせることがポイントです。
自分のことは自分で!「自主性」を引き出す習慣づくり
青山学院初等部が求める「5つのお約束」には、自ら考え行動する力=自主性も欠かせません。
ご家庭では、身支度や荷物の整理整頓、翌日の準備などをできる限りお子様に任せる習慣をつけましょう。
最初はうまくできないこともありますが、失敗も経験のうちと見守り、声をかけながら自分で完結できる喜びを味わわせることが大切です。「自分でできた!」という成功体験の積み重ねが、学校生活でも自立して行動できる力へと育っていきます。
家族全員で取り組む「礼儀・マナー」の定着
礼儀正しさや言葉遣いも「5つのお約束」の大切な柱です。
ご家庭内でも、挨拶を欠かさない、食事中のマナーを守る、敬語を使うべき場面を意識するといった取り組みを家族全体で行うことが効果的です。
お子様だけに注意するのではなく、親御様も一緒に意識することで、家庭全体の空気が「丁寧なふるまい」を育みます。外食時や公共の場でも、正しい行動を実践する機会を増やし、自然と礼儀が身につく環境づくりを心がけるとよいでしょう。
【青山学院初等部】大切にされる「5つのお約束」とは?合格を目指すご家庭必見!まとめ
青山学院初等部が大切にしている「5つのお約束」は、単なる学力向上やマナーや振る舞いを目的とするものではありません。
他者を思いやり、誠実に生き、自ら考え、行動できる――。そんな人間性を育むことこそが、初等部教育の真髄なのです。
受験においても、テストの結果がよいだけでは合否が決まるわけではありません。日々の生活の中で自然に「5つのお約束」を体現できるお子様こそが、青山学院初等部が求める理想像に近づいていきます。
ご家庭でも、焦らず、押しつけず、お子様自身が「人としてどうありたいか」を考える時間を大切にしていきましょう。そして、たとえ受験という目標の先にある道がどう進んでも、この「5つのお約束」はお子様の人生を豊かにする大きな力となるはずです。
青山学院初等部を志すご家庭の皆さまが、心温まる日々を積み重ねながら、希望に満ちた未来へ歩み出されることを心より願っています。
1.jpg)