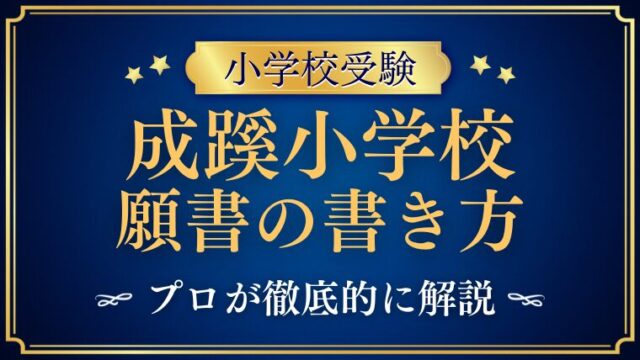塾長 Contents【青山学院初等部】絵画・工作試験とは
青山学院初等部の絵画・工作テストは、与えられたテーマや条件に基づいて、自分なりのアイデアを形にする課題です。
内容は年によって異なりますが、「ある場面を描く」「身近な素材で立体物を作る」「物語をもとに創作する」など、多様な形式が取り入れられています。
用意されている素材は画用紙、折り紙、クレヨン、のり、ハサミ、画材シールなどが中心で、どれをどう使うかも受験者の自由に任されています。
この試験で求められるのは、画力や器用さといった技術面だけではありません。発想の豊かさ、表現をやり遂げる粘り強さ、素材を工夫して使う柔軟性、そして他者と共有しようとする表現の意図──そうした“非認知能力”を含んだ総合的な表現力が見られています。
テーマを理解し、自分なりに構想を練り、制作に落とし込むまでの一連のプロセスを通して、その子の「らしさ」が自然と浮かび上がってくる試験と言えるでしょう。
 【完全保存版】青山学院初等部受験まとめ|入試・倍率・願書・学費・生活まで全網羅 \合格率97%/
青山学院初等部
オーダーメイド願書作成
詳しくはこちらをクリック ...
【完全保存版】青山学院初等部受験まとめ|入試・倍率・願書・学費・生活まで全網羅 \合格率97%/
青山学院初等部
オーダーメイド願書作成
詳しくはこちらをクリック ...
【青山学院初等部】絵画・工作試験が出題される理由
青山学院初等部がこのような絵画・制作課題を入試に取り入れているのは、同校の教育理念と深く結びついています。
青山学院初等部が重視しているのは、結果ではなく「どのように考え、行動するか」。つまり、思考や意図、工夫の跡を含めた“過程”を丁寧に見る入試です。
絵画・工作という表現活動は、お子様にとって最も自然で素直な自己表現の手段のひとつです。言葉では表しきれない思いや体験、感じたことが、線や色や形を通して表れる──その過程から、「この子が普段どのような感性で世界を見ているのか」「課題に対してどのようにアプローチするのか」が浮き彫りになります。
また、制作中の態度も重要な評価ポイントです。アイデアがうまくいかなかった時にどう対応するか、限られた時間の中でどれだけ集中して取り組めるか、道具の扱いや後片付けができるかなども、日常生活の反映として見られています。青山学院初等部は、こうした姿勢や意識が、入学後の学びや集団生活にも直結すると考えているのです。
【青山学院初等部】絵画・工作試験で見られている“当日の姿勢”とは?
青山学院初等部の絵画・工作テストでは、完成した作品だけでなく、制作に取り組む姿勢そのものが非常に重視されます。
例えば、教室に入室した際の挨拶、道具の受け取り方、制作中の集中力、トラブル時の対応力など、ひとつひとつの行動が丁寧に観察されています。特に注目されるのは、素材の扱い方や後片づけの様子です。
のりやハサミを丁寧に使っているか、使い終わったものをきちんと戻せているか、といった点から、日頃の生活習慣や礼儀、責任感が垣間見えるからです。また、うまくいかなかったときに諦めずに工夫する姿勢や、最後までやり切ろうとする粘り強さも高く評価されます。
作品の出来よりも、「その子らしさ」と「日常の延長にある行動」が見られる場面なのです。
【青山学院初等部】絵画・工作テストの試験内容
ここからは、青山学院初等部で過去に実施された絵画・工作テストの代表的な課題例をご紹介します。
どの年度も、制作物の出来栄えだけではなく、構想・工夫・取り組みの過程が重視される内容となっており、幼児教育の観点からも非常に示唆に富んだ構成となっています。
2024年度実施絵画・工作試験内容
■試験内容
男女共通で、ゼッケンの色ごとにグループ分けされ、各テーブルに用意されたさまざまな素材を使って自由制作を行う形式でした。制作テーマは「帽子とお料理」「お祭りの道具」「ボウリングピン」「クリスマスツリー」「飛び出す絵本」「お店屋さん」など多岐にわたり、いずれも読み聞かせ絵本が導入に使われていました。
■特徴
絵本の物語とリンクしたテーマを受けて、自分の発想で表現する課題が中心でした。完成品の出来映えだけでなく、「どう使うか」「なぜ選んだか」といった構想段階からの姿勢や工夫が観察の対象となります。また、素材の指定やルールも一部存在し、自由制作の中にも“意図を読み取って行動する”という思考力が問われる内容でした。
2023年度実施絵画・工作試験内容
■試験内容
絵本の読み聞かせをきっかけに、関連するテーマの制作を行いました。男子は「紙飛行機」「お弁当」「パクパクする生き物」、女子は「忍者の衣装」「クリスマスの飾り」「冠」「火星人への変身グッズ」など、想像力を活かす制作課題が多く出題されました。
■特徴
本年度も読み聞かせを起点とするテーマ設定がされており、子ども自身の解釈と発想力を活かした自由制作が評価の軸となりました。指定された素材の活用や台紙の図形を選んで組み立てる工程があり、手先の巧緻性や集中力に加え、ストーリー性や創造性が強く求められる内容でした。
2022年度実施絵画・工作試験内容
■試験内容
こちらも絵本の読み聞かせ後に、設定されたテーマに沿った制作課題に取り組む形式。男子は「お話の中の登場物」「ハンバーガー」「虫」「プレゼント」、女子は「水の中の生き物」「帽子」「宇宙にあるもの」「海の生き物」など、個性的なテーマが出されました。
■特徴
豊富な素材が用意され、制限の少ない自由度の高い制作形式だったため、子どもの個性が出やすい構成となっていました。色彩感覚や素材の組み合わせ方だけでなく、手順の工夫や発表までの流れにおける表現力、さらに協働場面でのふるまいも含め、総合的に観察されていたと考えられます。
h2 【青山学院初等部】絵画・工作テストと5つのお約束
絵画・工作テストでは、青山学院初等部の「5つのお約束」が自然に試される場面が随所にあります。
たとえば「よくかんがえてします」は、構想から制作までの流れに、「じぶんのことはじぶんでします」は道具の扱いや片づけに反映されます。また、「れいぎただしくします」は試験中の態度や姿勢に表れ、「しんせつにします」は他の子と道具を譲り合う際などに見られます。「しょうじきにします」は、自分で作ったことを偽らず誠実に表現する力とも言えるでしょう。
完成品だけでなく、“その子の姿勢”が評価されるこの試験では、まさに5つのお約束を日々の生活でどれだけ実践しているかが鍵となります。
【青山学院初等部】絵画・工作試験内容から考える対策
青山学院初等部の絵画・工作テストは、制作物の完成度ではなく「思考のプロセス」や「素材の扱い方」「発想の独自性」に重点が置かれています。
ここでは、2022〜2024年度の試験傾向を踏まえ、ご家庭で無理なく取り組める対策を3つご紹介します。
「読み聞かせ→制作」の流れを遊びに取り入れる
青山学院初等部では、制作の前に絵本の読み聞かせが行われ、その内容をもとに制作に入るパターンが多く見られます。この流れに慣れるため、ご家庭でもお気に入りの絵本を読み終えたあとに「このお話に出てきた○○を作ってみよう」と誘ってみてください。
制作には、折り紙や紙コップ、セロハンテープ、ストローなどの身近な素材で十分です。たとえば「バーガーボーイ」を読んだら紙でハンバーガーを作ってみる、「にんにんにんじゃ」を読んだら、スーパーの袋を使って忍者の衣装を作ってみるといった形です。
物語の理解→構想→制作という一連の流れを家庭内で体験することで、本番の流れにも自然と順応できるようになります。
「テーマ工作」で発想力と素材の扱いを養う
試験では「生き物を作る」「宇宙にあるものを作る」「お祭りの道具を作る」など、抽象的なテーマに対して自由に表現する課題が多く出されます。これに慣れるには、「今日は○○をテーマにして作ってみよう!」といった親子遊びがおすすめです。
例えば「海の生き物」と決めたら、モールでヒレを作り、紙皿で体を作るなど、素材を自分なりに工夫して形にするように促します。大事なのは「どの素材を選ぶか」「どう使うか」を子ども自身に考えさせること。
「どうしてその形にしたの?」「ここを工夫したんだね」と対話をしながら制作することで、発想を言語化する力も同時に育ちます。
「好きな素材で自由に作る」時間を定期的に確保
青山学院初等部では、共通素材が豊富に用意され、その中から自由に選び、時には指定された素材も活かしながら制作を進めるというスタイルが主流です。これに対応するには、家庭でも「選んで、組み合わせて作る」体験を重ねることが効果的です。
段ボール、紙皿、毛糸、カラーセロハン、ストロー、スポンジなどを1箱にまとめて“素材箱”として常備しておきましょう。そこから3つ選んで「これで好きなものを作ろう」と遊び感覚で取り組むと、選択力・構想力・組み合わせる力がバランスよく育まれます。
工作が完成したら「次は何を足してみたい?」などと展開を促し、制作意欲を楽しく引き出すことも大切です。
【青山学院初等部】絵画・工作試験内容や対策方法についてプロが徹底解説!まとめ
青山学院初等部の絵画・工作テストは、単なる「仕上がりの良さ」や「手先の器用さ」だけでは測れない、お子様の思考力・表現力・そして“その子らしさ”を見極めるための大切な試験です。
構想し、工夫し、やり遂げる姿勢の中に光る個性こそが、最も大きな評価の対象となります。日々の暮らしの中で「描く」「作る」「伝える」経験を積み重ねることで、本番でも自然体の魅力が輝くはずです。
焦らず、比べず、お子様の“今ある力”を信じて歩むことが、何より大切な対策になるでしょう。心をこめて、がんばってください。

絵画・工作テストでは、青山学院初等部の「5つのお約束」が自然に試される場面が随所にあります。
1.jpg)