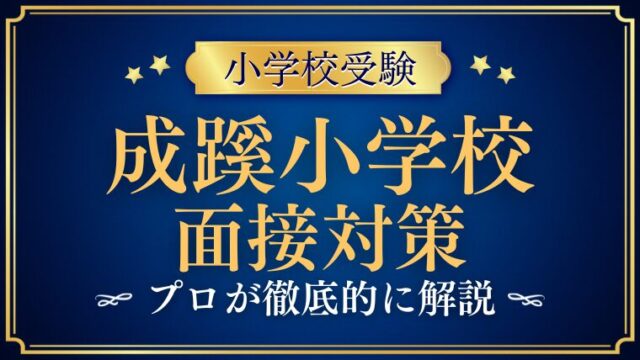青山学院初等部は、キリスト教に基づく教育理念を掲げ、「心の教育」と「知の教育」を両輪に、豊かな人間性を育てることを大切にしている共学校です
。都心にありながらも自然豊かな環境の中で、お子様たちは6年間、学びや友人との関わりを通して大きく成長していきます。
そんな青山学院初等部を象徴する行事の一つが、6年生が体験する「洋上小学校」。6年間の集大成とも言えるこの行事は、単なる旅行ではなく、お子様たちの心と体を大きく鍛える教育の場となっています。
【青山学院初等部】洋上小学校とは何か?
洋上小学校とは、青山学院初等部が力を入れる宿泊行事の集大成ともいえる、6年生で行われる宿泊行事です。客船を貸し切り、約9日間にわたって船上での共同生活を行います。
この情報だけを聞くと、一見「小学生が9日間の船旅なんて贅沢だ。」、「セレブ小学校のミーな行事だ。」なんてネガティブなイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、青山学院初等部の洋上小学校は、単に船旅を楽しむ観光目的の船旅ではありません。訪れた土地でのフィールドワークや、船内での活動・授業を通して、自然、歴史、文化を学びながら、仲間との絆を深める特別な学びの時間です。
この行事は昭和40年代に始まり、50回以上の実施を数える伝統行事。学校生活の枠を超えた「人生の節目」となる体験として、卒業生の記憶にも深く残る行事です。

【青山学院初等部】洋上小学校で得られる成長や学びとは?
洋上小学校とは、青山学院初等部の6年生が参加する宿泊行事で、客船を貸し切り、約9日間にわたって船上での共同生活を行います。
単に船旅を楽しむのではなく、訪れた土地でのフィールドワークや、船内での活動・授業を通して、自然、歴史、文化を学びながら、仲間との絆を深める特別な学びの時間です。
この行事は昭和40年代に始まり、50回以上の実施を数える伝統行事。学校生活の枠を超えた「人生の節目」となる体験として、卒業生の記憶にも深く残る行事です。
また、この洋上小学校は、青山学院初等部ならではの教育理念を体現する場でもあります。異なる地域の文化や風土、そして人との出会いの中で、お子様たちは自分自身を見つめ直し、新たな視点や価値観を身につけていきます。
教室では味わえない非日常の中で、心を揺さぶる出会いと経験が、ひとりひとりの成長に強く働きかけるのです。
洋上学校での学びとは?
航海中には、船上ならではの体験型授業が行われます。手旗信号やロープワーク、船速測定などを通して、船の仕組みや海に関する知識を学びます。
また、各寄港地では実際に上陸し、その地域の歴史や文化、自然を自分の目で見て、感じ、考える機会が設けられています。
さらに、船員の方々との交流を通して、社会の中で働く人々の姿に触れ、職業理解や感謝の心を育むこともできます。掃除や食事の準備など、日常生活に必要なこともすべて自分たちで行い、「生活力」を身につけていくこともこの行事の大きな意義です。
お子様たちの成長が垣間見える場面
船酔いに耐えながらも、自分の役割を果たそうとする姿や、甲板で満天の星空を見上げて感動する場面。
保護者の手を離れて、洗濯や時間管理なども自分でこなしながら生活する中で、お子様たちの表情や言葉には、これまでとは異なる自信と誇りが生まれてきます。
日々の活動の中で見せる姿は、まさに「顔つきが変わった」と教員が語るほど。大人への第一歩を踏み出す、貴重な経験となっています。
洋上小学校を支える安全体制と準備
洋上小学校では、お子様たちが安心して参加できるよう、万全の安全体制が整えられています。使用される船は、信頼性の高い旅客船。船内には医師や看護師も同乗し、急な体調不良にも対応できるよう配慮されています。
また、事前には保護者説明会や健康チェック、船内でのマナーや安全についての学習が行われ、お子様たち自身が安心して参加できるようしっかりと準備が進められます。
【青山学院初等部】洋上小学校のスケジュールや内容(2024年度参照)
ここからは、2024年度に実施された洋上小学校のスケジュールをもとに、実際の活動内容をご紹介します。
出航式と初日の航海
5月29日、竹芝桟橋で行われた出航式では、1年生のパートナーや保護者に見送られながら、児童たちは「小さな乗組員」として元気に旅立ちました。船上では避難訓練を行い、凧作りや船員との交流を楽しみながら、少しずつ船での生活に慣れていきました。
各地でのフィールドワークと学び
高知では高知城や坂本龍馬記念館を訪れ、明治維新の歴史に触れる体験を。鹿児島では、西郷隆盛ゆかりの地や知覧特攻平和会館を見学し、命や平和について深く考える時間を持ちました。
壱岐では凧揚げや釣りを楽しみながら、古代の歴史に触れ、門司・下関では関門トンネルや巌流島を訪れ、地域の文化や偉人たちの足跡を辿りました。松山では道後温泉や松山城を巡り、文学や歴史への理解を深めました。
船上での生活と活動
洋上では毎朝のラジオ体操や礼拝から一日が始まります。手旗信号やロープワークといった体験学習のほか、クラブ活動やプロジェクト活動など、自分の興味や役割に応じた活動にも取り組みました。生活のすべてが学びにつながっている数日間です。
最終日と帰港
最終日には、館山港でのセレモニーや入浴、城山公園からの眺望を楽しみました。船内では振り返りの時間を持ち、下船式では感謝を込めて歌を披露。竹芝桟橋に戻ったお子様たちは、笑顔で「ただいま」と手を振りながら、誇らしげに帰路につきました。
【青山学院初等部】洋上小学校の近年の航路と寄港地
洋上小学校の旅先は毎年異なり、その年のテーマや社会情勢に応じてコースが組まれます。お子様たちは、各寄港地での活動を通じて、その地域ならではの自然や文化、歴史に直接触れ、多様な価値観を身につけていきます。
2024年度(第50回)実施の旅
2024年は記念すべき第50回。出発は東京・竹芝桟橋から。高知、鹿児島、壱岐、門司・下関、松山を巡り、館山を経由して再び東京へと戻る、全日程実施の復活年となりました。
各地での学びは、歴史の偉人に触れたり、地域文化を体験したりと多岐にわたり、児童たちの心に深く残る旅となりました。
2022年度(第48回)実施の旅
2022年はコロナ禍を経て、3年ぶりに実施された洋上小学校。竹芝桟橋から出航し、岩手県の宮古市を訪れました。
東日本大震災の被災地で復興に取り組む地域の姿を学び、命の尊さと支え合う心を育む時間となりました。期間は短縮されていたものの、お子様たちは全力で各活動に取り組み、大きな達成感と感動を持ち帰りました。
2012年度(第38回)実施の旅
この年の航路では、高知、屋久島、対馬、隠岐、尾道、小豆島といった多彩な地域を巡りました。
屋久島の原生林や自然保護活動、対馬の歴史と動植物、隠岐での伝統文化体験、尾道での造船所見学、小豆島での文化産業への理解など、内容は非常に充実しており、まるで日本一周のようなダイナミックな旅程でした。
お子様たちにとって、多様な日本の姿を肌で感じる、かけがえのない経験となったことは間違いありません。
【コロナ】コロナ禍がもたらした「洋上小学校」の中止と、復活を支えた想いと工夫
青山学院初等部の伝統行事「洋上小学校」は、2020年と2021年の2年間、新型コロナウイルス感染症の影響により中止されました。
長い歴史を持つこの行事において、開催自体が見送られたのは非常に珍しく、学校関係者にとっても大きな決断でした。
6年間の集大成として、お子様たちが最も楽しみにしていた行事の一つが突如失われたことは、保護者にとっても残念で、心の整理に時間を要する出来事だったと言えるでしょう。
それでも、学校は歩みを止めることなく、お子様たちのために次なる実施の可能性を模索し続けました。状況が変わる中で、感染症対策や行事の運営方法について議論と準備が重ねられ、再開への道が少しずつ見えてきました。何より「安全」と「教育的意義」の両立をどう実現するかが、再開に向けた最大の課題でした。
2022年には、ついに3年ぶりの洋上小学校が実施されました。内容や航路は限定的でありながらも、船上で仲間と過ごすという原点に立ち返った学びの時間は、お子様たちの心に強く残るものとなりました。久しぶりの行事に、教職員も感極まり、保護者からも多くの感謝の声が寄せられました。
その翌年2023年には、内容も通常通りの規模へと戻り、そして2024年には記念すべき第50回を迎え、かつての姿を取り戻した洋上小学校が完全復活を遂げました。長く続く伝統を止めることなくつないだこの再開は、お子様たちにとっても学校にとっても大きな自信と希望につながっています。
【青山学院初等部】洋上小学校とは!?セレブな船旅?困難?苦しい?プロが徹底解説まとめ
青山学院初等部の「洋上小学校」は、単なる旅行行事ではありません。お子様たちが自らの手で生活を作り、仲間と共に学び、自然と歴史に触れる中で大きく成長する、まさに“生きた学び”の場です。
コロナ禍で行事中止の憂き目にあいましたが、困難な状況を乗り越えて再開されたその背景には、学校の情熱と保護者の信頼がありました。
青山学院初等部が大切にする想いが、洋上という特別な環境で輝く。そんな体験が、きっと児童一人ひとりの心に深く刻まれることでしょう。
1.jpg)