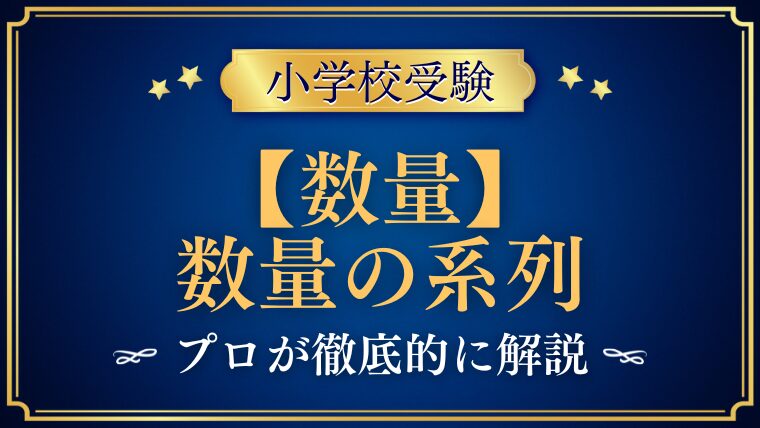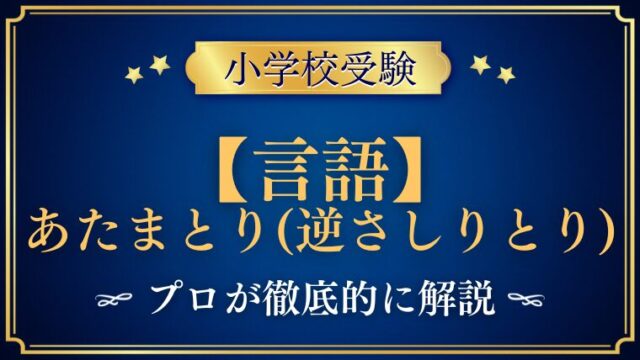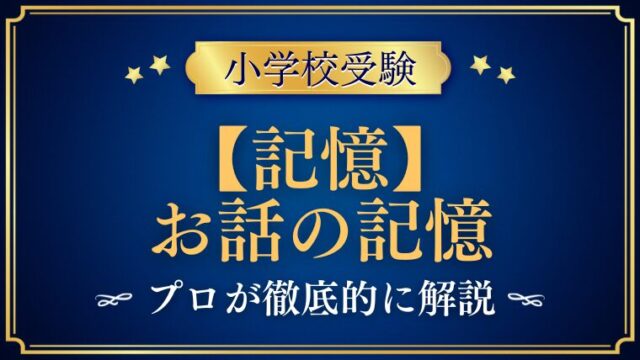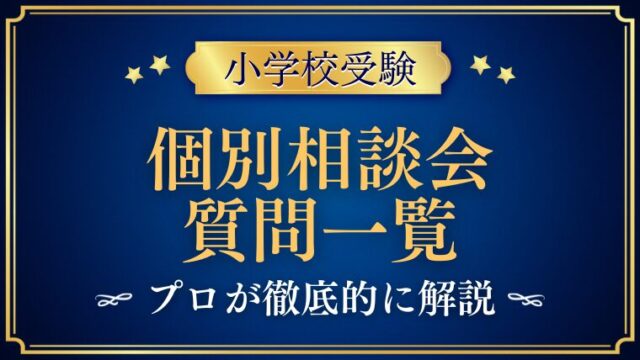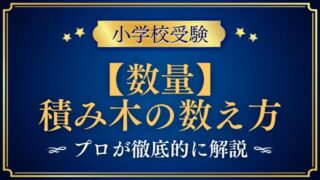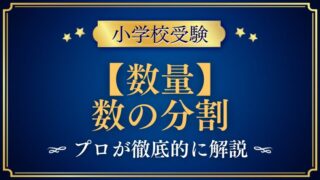【小学校受験】数量の系列の出題意図は?
「数量の系列」の問題では、基礎的な数量感覚が身についているか、論理的思考力があるかなどが評価されています。
基礎的な数量感覚が身についているか
「数の系列」では、量の多少、広さの大小、長さの長短の順番を感覚的に判断できることが大切です。感覚的に系列を判断することができれば、簡単に答えられるようになる問題がたくさんあります。数量感覚は、日常生活や遊びの中で鍛えることができるので、ご家庭の教育力を見られているとも言えます。
論理的思考力があるか
「数量の系列」では、数の並びの規則性を見つけたり、形を変形して広さを判断したり、ます目を頼りに長さを比べたりするなど、総合的な論理的思考力が必要になります。感覚的に解ける問題もありますが、難易度が上がると感覚的に解くのが難しくなるため、論理的に考える力も大切になります。
【小学校受験】数量の系列の出題方法は?
「数量の系列」の出題方法には、大きく2つの方法があります。
個別テスト・口頭試問
個別テスト・口頭試問による出題では、実物を示されて「この中で2番目に多いおはじきはどれですか」「この中で1番長いテープはどれですか。」などと問われる問題がよく出されます。また、数の系列が描かれた絵を見せられて、「四角に入る数はいくつですか。」と問われることもあります。あるいは、1個,3個,5個と積み木が並んでいて、「次に来る積み木の数を考えて、積み木を積んでください。」と出題されることもあります。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、「ある決まりで数が並んでいます。星のお部屋に入るりんごの数だけ、下の四角に丸を描きましょう。」「1番長い鉛筆の横にある四角に丸を描きましょう。」などと出題されるのが定番です。
【小学校受験】数量の系列の出題内容は?
「数量の系列」の出題内容には、主に次の4つがあります。似た問題に「重さの系列」がありますが、こちらは「シーソー」「重さ比べ」の問題に分類しています。
数の系列
数の増減を判断して答えるタイプの問題です。単純に1つずつ増減する問題もあれば、2ずつ増減したり、2倍で増減したりする問題もあります。20程度までの数を正しく数え上げたり、数え下げたりできることはもちろん、数の変化について感覚的に理解できることも大切です。
量の系列
「水が1番多く入っているコップを選んで丸で囲みましょう。」のように、量の多少を判断するタイプの問題です。「数の系列」と異なるのは、水、ジュース、砂、粘土などの連続量を扱うということです。見た目で感覚的に判断する問題と、めもりの数で量の多少を判断する問題があります。
広さの系列
「1番大きなレジャーシートを選んで丸で囲みましょう。」のように、広さの大小を判断するタイプの問題です。広さを表す言葉として、「大きい / 小さい」の他に「広い / 狭い」という表現を使うことがあります。また、「1番たくさんの子どもが座れるレジャーシートに丸をつけましょう。」のように、捻った表現で出題されることもあります。
長さの系列
「1番長いテープの横にある四角に丸をつけましょう。」のように、長さの長短を判断するタイプの問題です。テープ、鉛筆、直線など、まっすぐなものを扱う問題では、端が揃っている問題と、端が揃っていない問題があります。また、曲がったリボンや波線のように、まっすぐでないものを扱う問題もあります。
【小学校受験】数量の系列の解き方は?
「数量の系列」の解き方は、出題内容によって異なります。
「数の系列」では、数の変化の決まりを見つけることが大切です。変化の決まりには、「数が◯個ずつ増える(減る)」と「数が倍になる」の2パターンしかありません。数が増減する問題では、数え足したり、数え引いたりすれば問題を解くことができます。数が倍になる問題では、基準になる数ずつ丸で囲むと、視覚的にも理解しやすいでしょう。何回か問題を解いていくうちに、お子さま自身で「これは2ずつ増えているな。」と判断できるようになっていきますので、解き方を確認したら練習問題に取り組むようにしましょう。
「量の系列」「広さの系列」「長さの系列」では、感覚的に解く問題と論理的に解く問題があります。特に「広さの系列」では、色が塗られた部分の広さを判断する問題があり、パズルのような思考力が試されることもあります。それぞれの問題の具体的な解き方についてはこちらの教材で解説しています。感覚的に解いているだけではなかなか正答率を向上させることができませんので、早期に解き方を確認して問題を解く練習をすることで、「数量の系列」の解き方を身につけられるようにさせてあげてください。
【数量】数量の系列(教材サンプル)
【数量】6 数量の系列サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
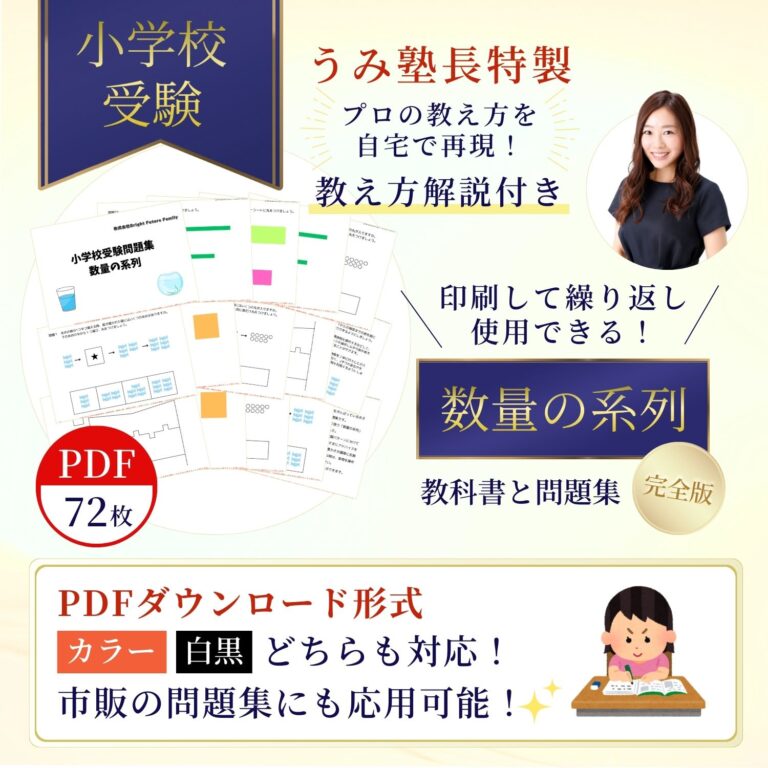
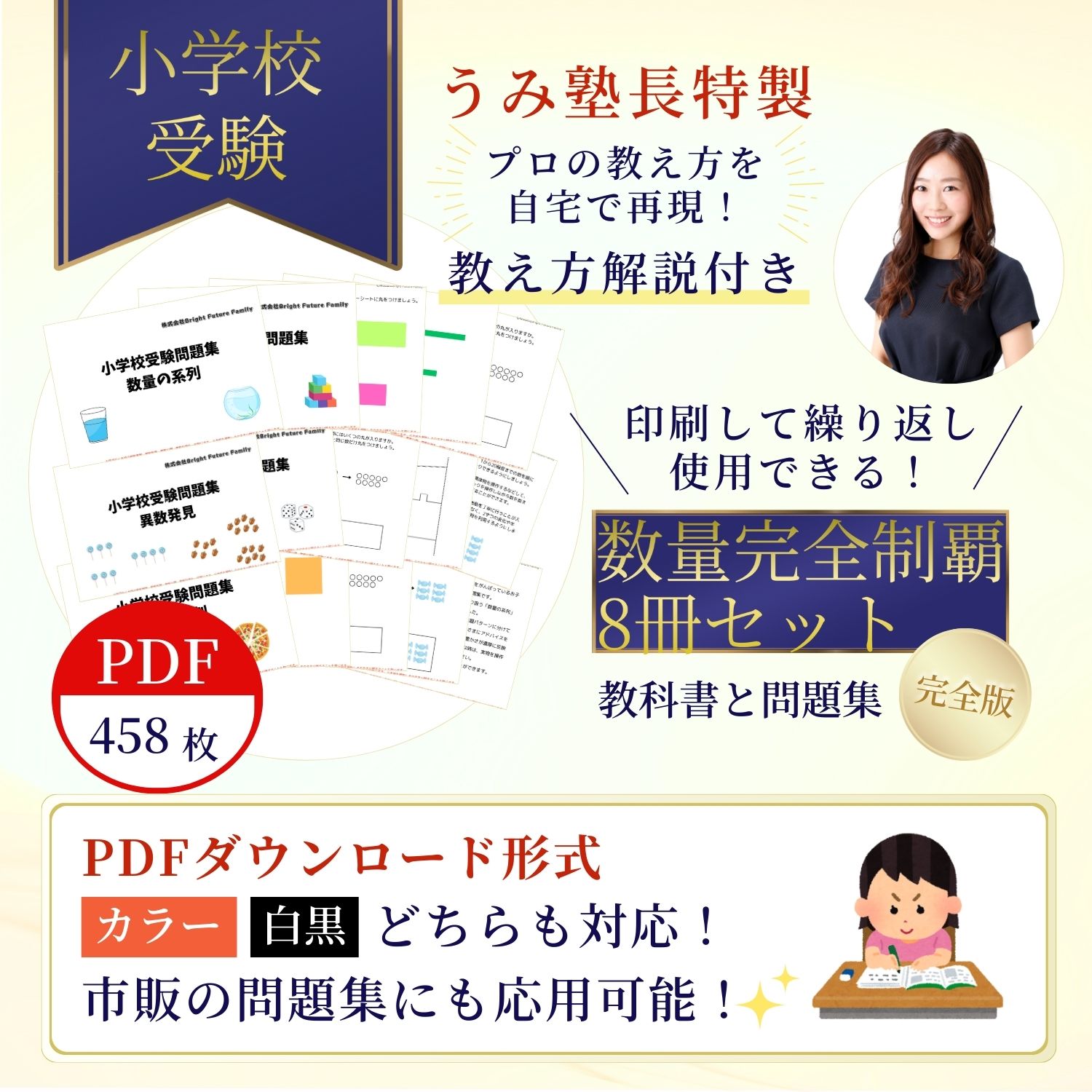
【小学校受験】数量の系列|まとめ
「数量の系列」は、基礎的な数量感覚と論理的な思考力の両面からアプローチする必要がある問題です。また、数・量・広さ・長さの理解は「理科的常識」にも分類される内容で、生活経験の豊かさも濃厚に反映されます。そのため、例えば、「コップに入ったジュースの量を比べる」など、生活経験を充実させることも視野に入れて対策をしてください。
1.jpg)