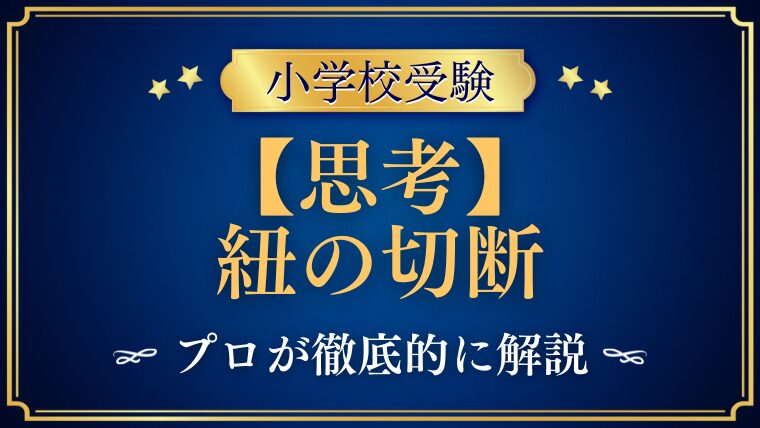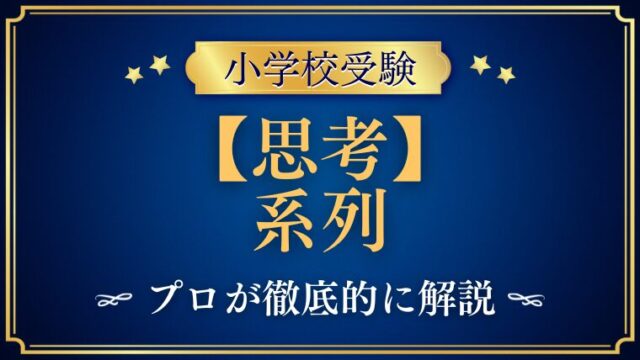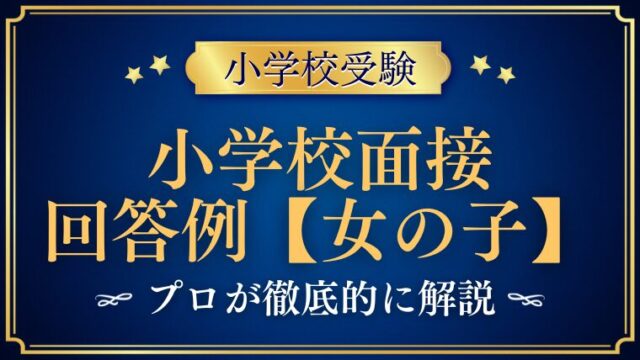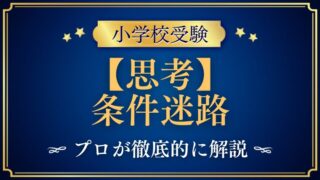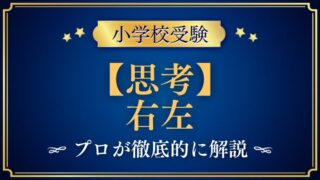【小学校受験】紐の切断の出題意図は?
「紐の切断」では、はさみを使うという生活経験があるか、紐を切るとどうなるかを判断する論理的思考力があるかなどが評価されています。
生活経験があるか
「紐の切断」の問題を解くためには、実際に紐を切る経験をしたことが重要です。はさみの練習は2歳〜3歳から始めることが多いですが、中には「ケガをしたら大変だから」と、はさみを使わせないようにする親御様もいらっしゃいます。確かにケガをしたら大変ですが、このような過保護な考え方を小学校側はネガティブに捉えます。安全面に配慮しつつ、はさみの練習をきちんとすることが大切です。
イメージ力があるか
紐を切った経験があったとしても、それを紙面上でイメージする力も必要になります。目の前に実物がない状態で紐をイメージするのは、幼児にとってなかなか難しいことです。ただ、解き方を理解していればイメージ力が身についていなくても問題を解くことは十分に可能です。
論理的思考力があるか
「1本の紐を1回切れば2本になる。2回切れば3本になる。」「1回切った紐を重ねて2本同時に切ると4本になる。」というのは大人にとっては常識です。しかし、そのような数の変化を意識したことがないお子さまにとっては、紐を切る手順や結果を論理的に推測しなければなりません。
【小学校受験】紐の切断の出題方法は?
「紐の切断」の問題は、主にペーパーテストで出されます。
ペーパーテスト
ペーパーテストでは、紐と切断箇所のイラストが描かれていて「点線のところで紐を切ります。切った後、紐は何本に分かれますか。」のように出題されます。問題を解く前に「練習問題」として、先生と一緒に実物を使って例題を解くこともあります。ただ、実際に紐を切る様子を確認してくれることはほとんどなく、多くはイラストを見て解答することになります。
【小学校受験】紐の切断の出題内容は?
「紐の切断」の出題内容は、大きく3つのパターンに分かれます。また、切るものが「紐」ではなくて「折り紙」などに変わることがあります。
単純な切断
1つ目は、単純に1本の紐をはさみで切るパターンです。「紐の切断」の問題の中ではもっとも基礎的な問題ですので、確実に解けるようにしておきましょう。1本の紐なので、1箇所切れば2本、2箇所切れば3本、3箇所切れば4本となります。
切り重ねの切断
「1本の紐を1回切った後、切った2本を重ねて切ると何本になるか」を問うような問題です。2本の紐を重ねて1箇所切ると4本、2箇所切ると6本となります。単純な切断よりも切断箇所が多くなるため、難易度が上がります。
折り重ねの切断
紐を折って切るパターンの問題です。1本の紐を半分に折って1箇所切ると、折った部分はつながっているため、3本の紐に分かれることになります。紐を1回折るだけでなく、2回、3回折って切ると、さらに難易度が上がります。
【小学校受験】紐の切断の解き方は?
「紐の切断」の問題を解くために大切なのは、紐を切る場面を具体的にイメージできることです。そのため、問題を解く前に紐を切って遊んでみたり、答え合わせの時に実際に紐を切ってみたりするようにしましょう。
「紐の切断」の問題では、端から順にチェックを入れながら紐の本数を数えるようにしてください。切断箇所が点線や実線で描かれていることがあるので、丸などの記号を使うのがおすすめです。
折り重ねの切断の問題は、紐と折り紙とでイメージが異なります。特に、折り紙の折り重ね問題はイメージしづらいかもしれませんので、やはり具体物を用いて練習をするのが望ましいでしょう。
こちらの教材では、単純な切断から複雑な折り重ね問題まで、幅広いレベルの問題を扱っています。また、具体的な解き方についても詳しく解説していますので、「紐の切断」の問題についてしっかりと理解することができるようになっています。
【思考】紐の切断(教材サンプル)
【思考】12 紐の切断サンプル
教材サンプルのダウンロードはこちらから
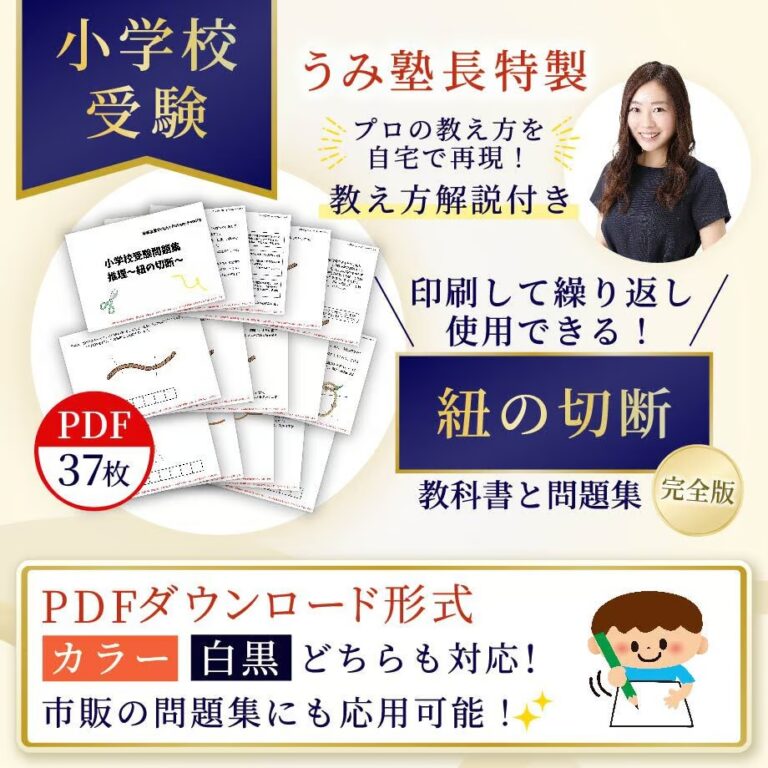
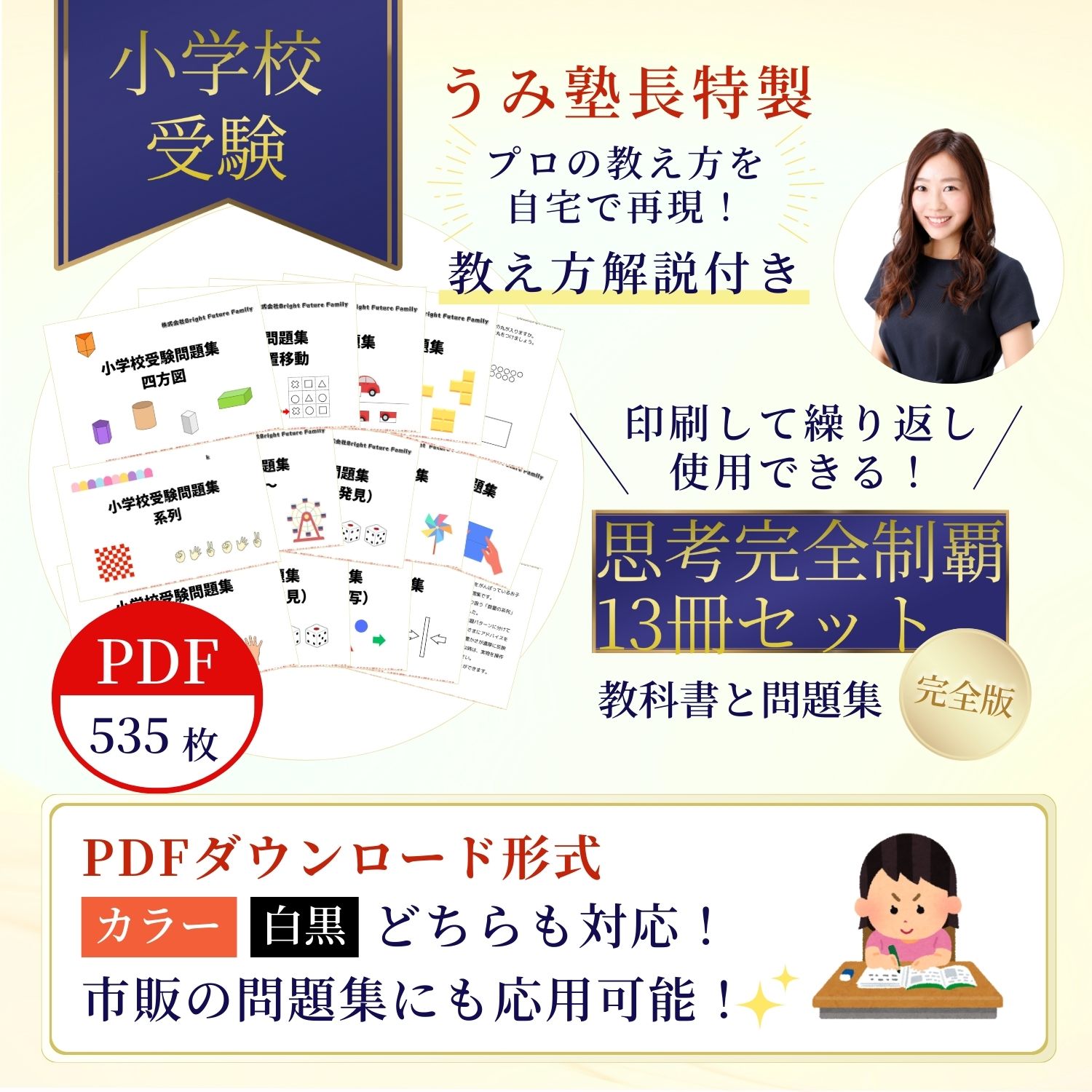
【小学校受験】紐の切断|まとめ
「紐の切断」は、日常生活と密接に結びついた問題です。紙面上に示されたイラストをもとに紐を切るイメージを持つことが大切ですので、実際に紐や折り紙を用いて体験的に学習するようにしてください。また、ペーパーの教材を使って問題演習をすることで実践的な解答力を身につけることができますので、本教材を活用して十分な対策をしていただけたらと思います。
1.jpg)