【立教女学院小学校】立教女学院小学校に受かる子の特徴は?
立教女学院小学校では、学力やスキルだけでなく、お嬢さまの性格やご家庭の価値観まで含めて、総合的に判断されます。入試の出題傾向や学校の教育理念をふまえ、合格につながりやすい3つのポイントをご紹介します。
「自由」と「敬意」のバランスが取れている子
立教女学院小学校は、自由な校風の中に「他者への思いやり」や「秩序ある行動」を大切にしています。そのため、入試では、のびのびと個性を発揮しつつも、ルールを守って行動できるか、周囲との関係性に配慮できるかが大切な評価ポイントとなります。
自分の気持ちを大切にしながらも、お友だちの意見に耳を傾け、穏やかに調和を図ることができるお嬢さまは、立教の校風に合った存在として好印象を持たれやすい傾向があります。
自分の言葉で感じたことを伝えられる子
型どおりの正解を答えるのではなく、心の中にある気持ちを自分の言葉で伝えようとする力は、立教女学院小学校の入試で非常に重視されます。特に面接や行動観察では、その場で感じたことや考えたことを、等身大の表現で話せるかが見られます。
表現力の巧さではなく、「自分の頭で考え、自分の気持ちをまっすぐ伝えようとする姿勢」が選考の中で光る場面です。家庭での日常会話の中でも、お嬢さまの言葉を大切に育ててあげることが、自然な力につながっていきます。
ひとつのことに誠実に向き合える子
立教女学院小学校の教育は、芸術・観察・運動・読書など多彩な体験活動に根ざしています。入試でも、制作や運動、巧緻性課題などを通して、粘り強く取り組む姿勢や、一つひとつの動作への丁寧さが見られています。
華やかな成果よりも、過程を大切にできる子。途中でうまくいかなくても投げ出さず、真剣に、そして最後までやりきろうとする姿勢が、最終的な評価につながります。

【立教女学院小学校】受かる子になるためのポイント・対策
立教女学院小学校の入試では、単なる知識や作業の上手さよりも、お嬢さまの人柄やご家庭の教育方針が重視されます。自由で温かな教育環境の中で、他者と共に歩む姿勢や、自分の考えを素直に表現する力が求められるからです。
では、ご家庭ではどのような関わり方をすれば「立教らしいお嬢さま」に近づくのでしょうか?特別な準備をしなくても、日々の中でできる工夫を3つの観点からご紹介します。
家庭の中で「自分の気持ちを話す時間」を大切に
立教女学院小学校では、自分の思いや考えを自分の言葉で伝える力が重視されます。その力を育てる第一歩は、家庭内での丁寧な対話にあります。
今日あったこと、楽しかったこと、ちょっとイヤだったことといった、日常の出来事をお嬢さま自身の言葉で話してもらう時間を、ぜひ意識してつくってあげてください。
「どう思ったの?」「そのとき、どんな気持ちだった?」と問いかけながら会話を重ねることで、感じる→考える→言葉にするという自然な流れが育っていきます。
一人の世界と、他人との関わりのどちらも経験させて
立教女学院小学校の入試では、個別課題と集団活動の両面が評価されます。これは、創造性と協調性をどちらもバランスよく持っているかを見ているからです。
そのため、ひとりで集中して取り組む遊び(お絵かき、工作、積み木など)と、お友だちと関わって楽しむ遊び(ごっこ遊び、簡単なルールのあるゲームなど)の両方を、日常に取り入れておくことが大切です。
「教える」より「見守る」姿勢を意識する
立教女学院小学校の教育では、子ども自身の気づきや挑戦を大切にする姿勢が貫かれています。ですから、保護者側が正解を教え込むのではなく、子どもが自ら考え行動する時間を見守る姿勢が求められます。
例えば、絵を描いているときや、何かに失敗して悩んでいるとき、「こうしたほうがいいよ」と口を挟むよりも、「どんなふうにしたい?」と問いかけ、じっと見守る姿勢のほうが、立教らしいお子さまを育てる土台になります。
大人が少し手を引いて待つことで、お嬢さまの主体性や創造性が伸びていくのです。
【立教女学院小学校】入試対策のポイント
立教女学院小学校の入試では、「ペーパーテスト」「個別・巧緻性課題」「行動観察」「運動課題」の4つの分野が、バランスよく実施されます。いずれの課題も単なる技術や正解率を見るのではなく、お嬢さまの人柄や取り組む姿勢、そしてご家庭での育ちがにじみ出るようなふるまいを総合的に評価するのが特徴です。
それぞれの分野に対する具体的な対策ポイントを確認しておきましょう。
ペーパーテスト:スピードと処理力が求められる
立教女学院小学校のペーパーテストは、私立小学校の中でも難易度が非常に高く、問題の質・量ともにトップクラスです。出題分野は、記憶・数量・図形・推理など広範囲にわたりますが、単に知識があるだけでは対応できず、スピード・処理力・初見問題への対応力が問われます。
特に注意したいのは、このペーパーテストで高得点を取ることが“選考のスタートライン”とされている点です。多くの関係者の間では、一定以上の得点を収めた受験者の中から、祖霊がのテスト(行動観察や個別課題、面接)を通して学校側との相性や素養を測られるとも言われています。
つまり、「立教女学院小学校らしさ」や「ご家庭の教育方針」といった個性を見る前に、まずペーパーで高い成果を出すことが前提条件となるということです。裏を返せば、どれだけ魅力的なお子さまでも、ペーパーで結果を残せなければ評価の土俵にも上がれないという厳しさがあります。
そのうえで、ペーパーテストで優れた結果を残したお嬢さまの中から、行動観察や個別課題などを通して、立教女学院小学校が求める「自律性」「思いやり」「自由と規律のバランス」を備えた子どもかどうかが慎重に見極められていきます。
対策のポイント:
時間制限のある問題に慣れ、制限時間内で正確に処理する練習を繰り返す
記憶や図形、推理など、分野を広げた演習を行う
単なるプリント演習ではなく、初見問題や応用問題にも対応できる力を育てる
日常の会話で「なぜそう思うの?」と問いかけ、思考の言語化を習慣に
個別・巧緻性課題:生活習慣と取り組み姿勢を見られる
立教女学院小学校の巧緻性や個別課題では、積み木・ひも結び・ハサミ・のり・箸などを使った日常的な動作や作業を通じて、手先の器用さ・集中力・丁寧さなどが評価されます。
大切なのは、完成度の高さではなく、手順を守って落ち着いて作業ができるかどうか。また、途中でうまくいかなくてもあきらめずに取り組み続ける姿勢も、非常に重視されます。
対策のポイント:
ハサミ・のり・セロハンテープ・割り箸など、家庭でもよく使う
親が手を出しすぎず、見守るスタンスをとる
ゆっくりでもよいので「最後まで自分でやる」経験を積む
行動観察:協調性と柔軟性、思いやりをチェック
立教女学院小学校の行動観察では、集団遊び・共同制作・ルールのある活動などを通して、社会性・自律性・協調性が見られます。立教女学院では、「自己主張と調和」のバランスがとれている子が好まれる傾向があり、出しゃばりすぎず、引っ込みすぎず、まわりと自然に関わる姿勢が重要です。
ルールを守る、相手に譲る、困っている子に声をかけるといった人としてのふるまいの基本が試される場面でもあります。
対策のポイント:
ご家庭や園での「ごっこ遊び」や「ルールのある遊び」の時間を増やす
「困っている子を見たらどうする?」など家庭内での会話の中に道徳的判断を取り入れる
習い事や外遊びで、他の子と関わる機会を日常に組み込む
運動課題:身体能力ではなく“指示理解”と“集中力”がカギ
立教女学院小学校の運動課題は、ジャンプ・平均台・ボールを使った動きなど、基本的な運動能力と理解力を測る課題が中心です。立教女学院では、運動神経の良し悪しではなく、「話をよく聞いて、その通りに動けるか」「周囲に合わせて行動できるか」といった注意力・観察力・落ち着きが大切にされます。
先生の指示を聞いて行動する「聞く力」や、「ルールの中で安全に行動できる力」が見られていると考えておきましょう。
対策のポイント:
「〇歩進んで、くるっと回ってジャンプ!」などの指示遊びを取り入れる
リズムに合わせて体を動かす遊び(手拍子・ダンス)などで集中力を養う
外遊びを通して、全身を使った動きに慣れさせる
立教女学院小学校の入試は、知識やスキルを詰め込んだからといって対応できるものではなく、「これまでどのように育ってきたか」「ご家庭でどのように関わってきたか」が、そのままにじみ出る試験です。
お嬢さまが自然体で力を発揮できるように、日常生活そのものを丁寧に見直し、「話す・聞く・やりきる・関わる」といった基本的な力を積み上げていきましょう。
【立教女学院小学校】ご家庭でできる対策・準備
願書対策も万全に
立教女学院小学校の入学考査では、受験者(お嬢さま)だけではなく、ご家庭の総合力で判断されます。そのため、ご家庭から学校へのファーストアプローチとなる願書の完成度は非常に重要で、内容の深さや表現力によって、ほかのご家庭と大きく差がつくことも珍しくありません。
当社では、立教女学院小学校の傾向に即した完全オーダーメイドの願書作成サポートをご提供しています。ご家庭ごとの教育方針や背景、お子さまの個性を丁寧にヒアリングしたうえで、そのご家庭にしか書けない願書を、専門ライターが責任を持って仕上げます。
立教女学院小学校の入試に特化した実績豊富なスタッフが対応いたしますので、「想いをどう表現すればいいかわからない」「願書だけで伝えきれるか不安…」という方も安心してご相談ください。
▶プロがご家庭の想いを伝える!オーダーメイド願書作成はこちら
家庭学習が合格のカギ
立教女学院小学校のペーパーテストは、非常に高い難易度で知られており、対策が簡単ではありません。さらに、巧緻性・運動・生活動作・行動観察など、多岐にわたる課題が出されるのも特徴です。
こうした幅広い出題に対応するためには、家庭での学習をただ詰め込むのではなく、効率的かつ計画的に取り組むことが求められます。プリントやおけいこに偏るのではなく、外遊びや家庭生活、お手伝い、家族との会話といった日常の体験を大切にすることで、お嬢さまの心と力をバランスよく育むことができ、それが合格への確かな一歩につながっていきます。
弊社では、合格率97%を誇る家庭学習サポートを実施しています。受験までのスケジュール管理や学習の進め方、日々の声かけの工夫まで、ご家庭に寄り添ったアドバイスと実践的なサポートを提供。無理なく、でも確実に合格へと導きます。
【立教女学院小学校】受かる子になるために家庭でできること
立教女学院小学校では、学力やスキルの高さだけでなく、人との関わり方や、自分らしく表現する力、丁寧に物事に向き合う姿勢など、「育ちの深さ」が重視されます。
こうした力は、特別なトレーニングではなく、日々の家庭生活の中で自然と育てていけるものです。
ここでは、ご家庭で今からできる3つの具体的な取り組みをご紹介します。
親子の会話で「感じたことを言葉にする」習慣を育てる
立教女学院小学校の入試では、子ども自身の言葉で気持ちや考えを伝える力が求められます。その土台となるのが、日々の親子の会話です。
「今日一番楽しかったことは?」「どうしてそう思ったの?」と問いかけることで、感じたことを言葉にする練習が自然とできるようになります。最初は答えがうまく出てこなくても問題ありません。焦らずに、子どもが自分の言葉で表現しようとする過程を大切にしましょう。
正確な言葉づかいや論理性よりも、「自分で感じたことを、自分なりの表現で伝える」ことに価値を置く姿勢が、立教女学院の求める子ども像に通じています。
ひとり遊びと集団活動の両方を経験させる
立教女学院の入試では、個別テストと行動観察の両方が実施されます。そのため、「自分で考えて動ける力」と「他者と関わる力」の両方が必要です。
一人でじっくり取り組む遊び(積み木、絵画、工作、図鑑を見るなど)は、集中力や創造性、丁寧に取り組む姿勢を養います。一方、兄弟や友だちと一緒に遊ぶ時間では、ルールを守る、譲り合う、協力する、といった社会性が育ちます。
日々の生活の中で、「今日は一人で何をして遊ぼうか?」「今度、お友だちとどんな遊びをしてみようか?」と話しかけながら、両方の経験をバランスよく積み重ねていくことが、試験当日の自然なふるまいへとつながります。
子どもが「自分でやりきる」経験をそっと見守る
立教女学院小学校の試験では、制作や巧緻性の課題が出題されます。これらの課題では、手先の器用さや結果の美しさよりも、「途中で投げ出さずに取り組む姿勢」や「試行錯誤しながらやりきろうとする粘り強さ」が評価されます。
ご家庭でも、ハサミやのり、折り紙などを使った制作や、身のまわりのことを自分でやる機会を意識的に増やしましょう。最初からうまくいかなくても、すぐに手を出さず、見守る姿勢を大切に。「どうやったらできるかな?」と本人が考える時間を尊重することで、自立心と達成感の芽が育ちます。
「できた!」という小さな成功体験の積み重ねが、試験当日の自信となり、お嬢さまの自然な表情や姿勢に表れてきます。
まとめ:立教女学院小学校に「受かる子」になるために今すべきこと
立教女学院小学校の入試は、出題の幅広さと難易度の高さに加え、お嬢さまの内面やご家庭の方針までが問われる、非常に総合的な試験です。だからこそ、家庭だけでなんとかしようと抱え込まず、信頼できる外部の力を上手に取り入れることが、合格への大きな後押しになります。
お子さまに合った学習の進め方やご家庭での関わり方を見直しながら、経験豊富な専門家のサポートを活用して、「今、必要な準備」を的確に進めていきましょう。
迷ったときや不安を感じたときは、どうぞ私にご相談ください。立教女学院小学校の対策に精通した講師陣が、合格というゴールに向けて、親子での歩みを全力で支えてまいります。
1.jpg)




















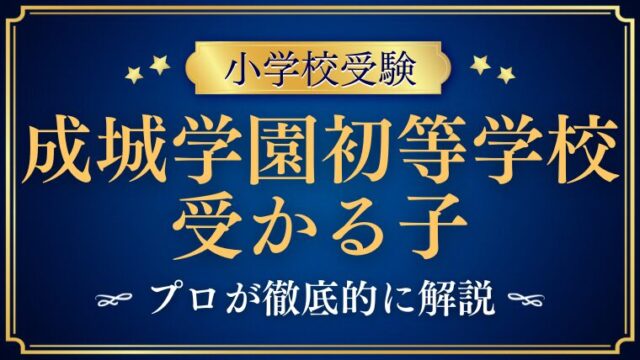

の書き方をプロが解説-640x360.jpg)


