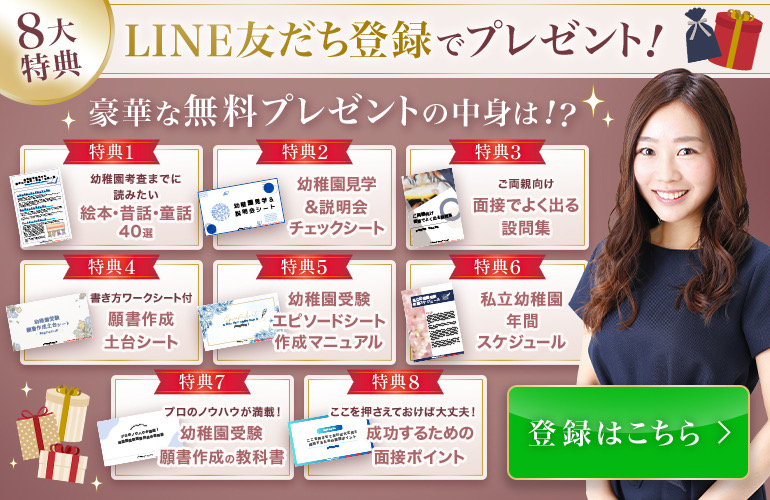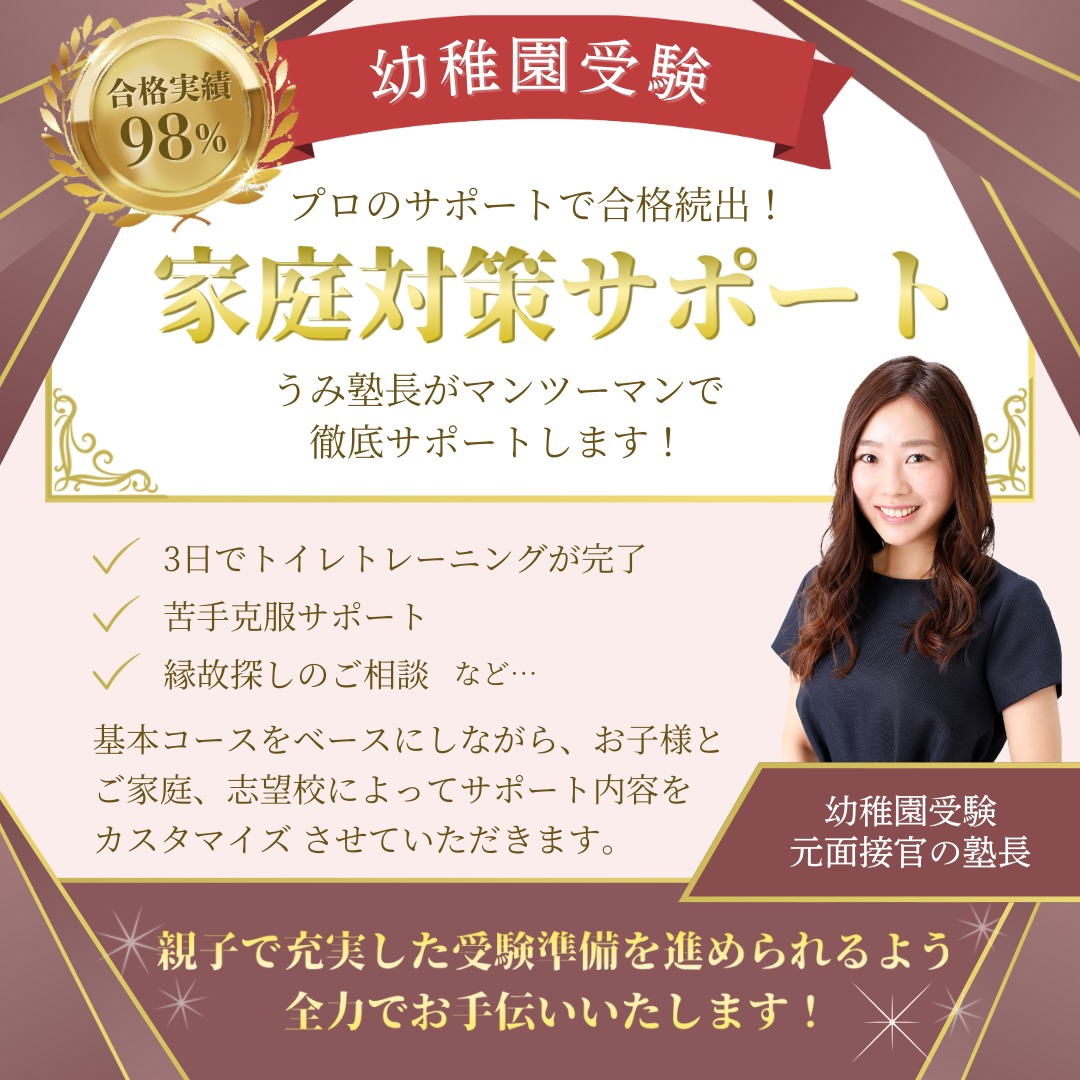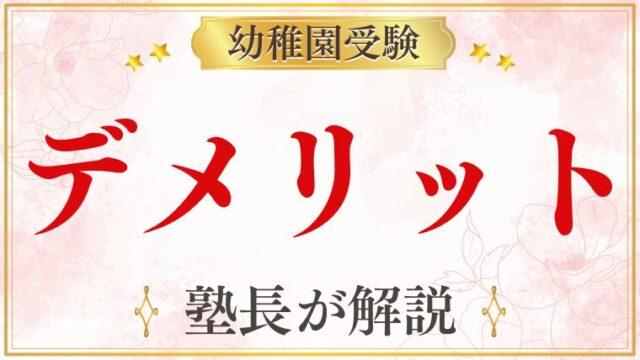「幼稚園受験の入園選考って、何をするんだろう・・」そんな疑問を多くの親御様がお持ちではないでしょうか。
幼稚園の募集要項を見ても、「入園考査」や「自由遊び」などとしか書かれておらず、何をするのかさっぱりわかりませんよね。
それに、入園案内を見ると、「ありのままの姿をお見せいただければ大丈夫です」や「特別な準備は必要ありません」と書かれていることがあり、期待と不安を駆り立てられることと思います。
そこで本記事では、幼稚園受験の元面接官である私が、「幼稚園受験では何をするの?」という疑問や不安にお答えすべく、幼稚園受験の試験内容について具体的に解説したいと思います。また、今回は特別に、それぞれの対策についてもお伝えしたいと思います。試験内容を知り、適切な対策を立てることで、幼稚園受験の合格を勝ち取りましょう。
【幼稚園受験】集団テスト・行動観察の対策
試験内容は幼稚園によって様々ですが、大きく「集団テスト・行動観察」「個別テスト・個別考査」「面接」の3つの領域に分けることができます。
すべてを解説すると長くなってしまいますので、本記事では「集団テスト・行動観察」に絞って解説をしていきます。
「個別テスト・個別考査」と「面接」についてはこちらの別動画で解説していますので、そちらもぜひチェックしてみてください。
集団テスト・行動観察
集団テスト・行動観察とは、集団の中での振る舞いが評価される試験のことです。先生の指示を正しく理解しているか、社会性が身についているか、落ち着いた行動がとれるか、コミュニケーション力があるか、協調性があるか、自発的に行動できるか、集中して取り組むことができるか、ルールを守ることができるか、場や人に適応することができるかなど、多面的な人間力が問われます。
集団テスト・行動観察の試験では、「指示行動」「生活習慣」「自由遊び」などの領域があります。指示行動は、先生の指示を理解して、指示された通りに行動できるかを評価する試験です。
指示行動
指示行動では、先生の話を集中して聞き、正しく理解して、適切に行動することが求められます。例えば、「ボールを取ってきて、カゴの中に入れましょう。」「笛が鳴ったら赤い輪の中に入りましょう。」「先生が言った通りに、立ったり、座ったり、手をたたいたりしましょう。」などの指示行動が行われます。当然のことながら、指示行動で大切なことは、先生の話をきちんと聞くことです。そのため、日頃から「一度で聞いて動く」という習慣をつけるようにしましょう。
普段の生活の中では、やはり親子の会話の中で聞く力を鍛えるのが1番です。親御様が意識するべきなのは、簡潔で明瞭な指示を出すことです。例えば、「これをあっちに持って行って」という漠然とした指示を出すのではなく、「シャツとズボンを、クローゼットにある引き出しの下から2段目に入れてきて」のように、具体的に指示を出すようにしましょう。また、親御様の中には、お子様に対して繰り返し声かけをしている方がいらっしゃいますが、これは「聞かなくても済む」という悪い習慣がついてしまう可能性があります。あるいは、指示を出す前に手を出して手伝ってしまう方もいらっしゃいますが、これもお子様が自分で考えて行動する機会を奪うことになるので控えた方がよいでしょう。お子様が「何をどうすればよいか」を理解して行動に移せるように、簡潔で明瞭な指示を出すことを心がけてください。
お子様にとって大切なのは、やはりきちんと話を聞いて理解できることです。「話を最後まで聞く」「話している間は静かに聞く」「相手の方を見て話を聞く」「何をすればよいか考えながら聞く」など、話を聞くための基本的な心構えや姿勢をしっかりと教えてあげましょう。例えば、絵本の読み聞かせの時間は静かに最後まで聞くなど、日常の中で話を聞く練習をしましょう。話を理解しながら聞くのが苦手なお子様には、「オウム返し」による練習がおすすめです。これは、親御様が言ったことをお子様がそのまま繰り返し言う練習法で、「聞く→記憶する→想起する→再生する」という段階を踏むことで、聞く力の向上を図ることができます。
生活習慣
生活習慣では、あいさつ、トイレ、服の着脱、片付け、食事のマナーなど、基本的な生活習慣が身についていることが重要です。生活習慣を身につけるには時間がかかりますので、長期的な視点を持って対策をしましょう。中には、入園する条件として「おむつが外れていること」を課している幼稚園もあります。特に、早生まれのお子様はトイレトレーニングが受験に間に合わないことがあるので、早期に対策を始めるようにしてください。試験では、例えば、「上着の着脱や靴の脱ぎ履きを自分ですることができる」「使ったおもちゃを、もとあった場所にお片付けする」「トイレの時間に自分でトイレに行くことができる」などが評価されています。
基本的な生活習慣を身につけるためには、日頃の家庭での過ごし方が重要です。毎日の行動が受験対策に直結していることを意識して生活するようにしましょう。「生活習慣」というくらいですので、「習慣」として当たり前にできるようになるまでサポートしてあげてください。
親御様のマインドセット
親御様のマインドセットとしては、「我慢」と「創意工夫」を大切にしていただきたいと思います。お子様がまだできないことをできるようにするわけですから、どうしても忍耐が必要になります。親御様がやってあげた方が時間がかかりませんし、丁寧にできることもたくさんあると思います。しかし、「お子様が自分の力でがんばろうとしていること」に目を向けて、たくさん褒めて伸ばしてあげてください。また、生活習慣を身につけさせようとすると、「ああしなさい」「こうしなさい」と口うるさくなってしまうことがあるかもしれません。しかし、それではお子様の自己肯定感を育てることはできません。例えば、「お片付けレース」と称して手際よくお片付けをする練習をする、お子様が行きたくなるようにトイレを飾り付ける、「ご褒美シール」でやる気を出すなど、創意工夫を生かして楽しく対策ができるとよいですね。
自由遊び
自由遊びは、その名の通り、お子様が自由に遊ぶ中で自発性・協調性・社会性・コミュニケーション力などが評価される試験です。遊びの中でもしっかりと感情のコントロールをしたり、状況を判断したり、まわりを思いやったりすることが重要です。試験では、例えば、「積み木やブロックなどの指定されたおもちゃで自由に遊ぶ」「複数のおもちゃが置かれた部屋で自由に遊ぶ」などの課題が出されます。
自由遊びは、お子様の「素」が出やすい試験です。そのため、自由遊びでどのような行動を取ればよいのかを具体的に教えてあげることが対策として有効です。同時に、無理に「型」にはめるのではなく、お子様の長所を生かして対策をすることが望まれます。
具体的には、「集団で遊ぶ機会を増やす」というのが有効な対策として挙げられます。公園、児童館、プレ幼稚園などで、他者と関わりながら遊ぶ経験をたくさんさせてあげましょう。遊びの中で、自然とおもちゃの貸し借りを学んだり、役割分担を学んだり、感情のコントロールの仕方を学んだりしていくことができます。
その中で、親御様はお子様の様子を見守り、自主性や問題解決能力を伸ばせるようにサポートしてあげてください。例えば、お友だちと喧嘩をしてしまったら「悲しかったよね。あの時、どうしたらよかったのかな?」と、お子様の気持ちに寄り添いながら、よりよい解決策を一緒に考えてあげてください。ご自宅でも、物を貸し借りする時は「貸して」「いいよ」などの会話を心がけることで、自然と社会性の基礎を身につけられるように気を配りましょう。
また、遊びの途中であっても、終わりの合図があったらすぐにやめられることも大切です。中には気持ちの切り替えができず、遊びをやめるのを嫌がるお子様もいます。そのようなお子様には、事前に見通しを持たせておくこと、お片付けの時間も楽しくなるように工夫すること、すぐに切り替えができたらたくさん褒めることなどを通して、気持ちを切り替えることの成功体験を積ませていきましょう。
自由遊びと趣向が似ている課題として、「親子遊び」という課題もあります。親子遊びは、親子での関わり方も評価される試験です。お子様の遊び方以上に、親御様がどのようにお子様に関わり、声をかけ、サポートをしているかが問われますので、「この幼稚園の試験では、どのような親の姿が求められているのか」という視点を持って、試験に臨むようにしてください。試験の例としては、「用意されたおもちゃを使って親子で自由に遊ぶ」「折り紙やちぎり絵など、指定された活動を親子で行う」などの課題が挙げられます。
親子遊び
親子遊びで大切なのは、親御様がお子様の主体性を尊重し、自立を促す働きかけをしていることです。お子様が甘えたり、親御様に依存したりしていないこと、親御様がお子様に合ったペースでサポートしていることが重要です。
普段からお子様が主体的に遊ぶ環境を整えて、その中で親御様も一緒に楽しむことが親子遊びの対策になります。例えば、「何して遊ぶ?」「どうやって作ろうか?」「お母さんは何をしたらいいか教えて?」など、お子様の発想や主体性を引き出す言葉かけをしてあげましょう。
親御様が手と口を出し過ぎないことも重要なポイントです。お子様の取り組みをじっくり見守る、完成度の高さを求めない、「すごい!」「なるほど!」などの肯定的な声かけをするなど、お子様が主体的に遊べるような環境を整えてあげることを意識してください。その中で、「こうしてみてもいい?」とよりよいアイデアをそれとなく教えたり、「ハサミの持ち手をちゃんとお母さんに向けて渡してくれてありがとう」などの社会性の発達を促す言葉をかけることも忘れないようにしましょう。くれぐれも「早くして」「そうじゃなくて、こうやるのよ」など、否定的な言葉を使わないようにしてください。
幼稚園の集団テストの試験内容には、
・指示行動
・生活習慣
・自由遊び
の観点から試験が行われていることを解説しました。
このように、「集団テスト・行動観察」は、集団での振る舞いを見られたり、生活習慣がどれくらい身についているかを見られたりする試験です。いずれの試験の対策も一朝一夕で鍛えられるものではありませんので、長期的な視点を持って対策をするようにしましょう。
私は、願書作成・面接レッスン・家庭学習支援など受験サポートをしているかたわら、子育てや受験に関するアドバイスも行っております。もし試験内容や対策の仕方で気になることがありましたら、ぜひ「幼稚園受験個別相談」のご利用もご検討ください。効果的な対策をして、できるだけストレスなく幼稚園受験を乗り切りましょう。
また、本動画で解説しきれなかった「個別テスト・個別考査」と「面接」については別動画で解説していますので、ぜひそちらも合わせてご視聴ください。
私が配信している公式LINEでは、幼稚園受験に関するプレゼントをお配りしております。概要欄にあるリンクからご登録し、プレゼントをお受け取りください。それでは今回の動画はここまでです。お子様のさらなる成長と受験の成功を願っております。ありがとうございました。
-2.png)